
 |
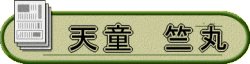
![]()
![]() ツランの子 ─ スオミ=フォンランド
ツランの子 ─ スオミ=フォンランド
(世界戦略情報「みち」平成18年(2666)1月15日第220号)
●本号の角田稿「大東亜戦争の意義」の中に、興味深い話が紹介されている。戦前の関東軍司令部で情報担当者だった吉川光が大東亜戦争中の昭和一九年一〇月ブルガリアの大使館付任務に就いていたとき、「ドイツが降伏文書に調印すれば、それから三ヵ月以内にソ連は対日宣戦する」という情報をフィンランド大使館の書記官から入手したという話である。
この貴重な情報は直接の上官にも大本営にも黙殺されたということだが、硬直した戦争指導部の中枢はいざ知らず、もしもこの情報が満洲や北方領土の最前線で対ソ戦に備えていた部隊にまで周知徹底されていたら……と思わずにはいられない。中央からは武装解除の指令が届いてまもなく、まさに不意打ちを喰らう形でソ連を迎え撃った前線部隊は無い無い尽くしの中であれだけ果敢に闘って玉砕したのである。ソ連侵攻が必ずあると事前に分かっていれば、たとえ玉砕は免れないとしても、もっと別の闘い方があったはずである。返す返すも無念でならない。
日本は情報戦に完敗したなどと言われるが、吉川光の例のように、情報がなかったのではない。上がってくる情報を分析・評価して、戦争指導の実際に活用するという柔軟な態勢が決定的に欠落していたのである。
日露戦役における児玉源太郎の戦争指導は高く評価されているし、日本海海戦における東郷平八郎・秋山真之の指揮下帝国海軍の闘いぶりは見事の一語に尽きるほどだが、その日露戦役においてもすでに軍の硬直化が始まっていたと小説の形式ながら指摘したのが、北上秋彦『白兵』(二〇〇一年二月、講談社刊)である。明治三五年一月に起きた「八甲田山死の彷徨事件」として有名な悲劇は実は厳寒の満洲における対露戦を想定した耐寒雪中行軍の訓練中の事故だった。不祥事として事件そのものが隠匿される中で、多くの犠牲者を出したその訓練の成果が厳寒の満洲の荒野で実際に闘われた奉天会戦になんら活かされなかったことを、北上は厳しく指摘している。
●吉川光の貴重な情報において注目したいのは、それを活用できなかった軍の硬直化ではない。その情報を吉川光に齎したのがフィンランド大使館勤務のフィンランド人書記官だったという点である。
自治領ながらロシア帝国領に組みこまれていたフィンランドが悲願の独立を達成したのはロシア革命後の一九〇七年一二月である。それに先だってフィンランド独立運動闘士のツィリアクス Kunni Zilliacus が帝政ロシアの内部攪乱工作において、対露戦に備え欧州で情報工作に当たっていた明石元次郎に協力したことはよく知られている。
日露戦役で日本が勝利しロシア帝国の崩壊に大きな打撃を与えたことをフィンランド人は感謝していて、対日感情は極めてよいのである。
そればかりではない。第二次世界大戦でもフィンランドにとってソ連は最大の敵だった。大戦が欧州で勃発するや否や、ソ連は五〇万の大軍をもってフィンランドに攻め込んだ。フィンランドはソ連軍を相手に果敢に闘うも衆寡敵さず休戦して領土の割譲を強いられた。ドイツの対ソ戦が始まるとドイツ軍への協力を余儀なくされ再び戦いに巻きこまれたが、戦局の不利を見て取るや、早くも一九四四年九月一九日に再度の対ソ休戦条約に調印したのであった。
ソ連対日宣戦の情報をフィンランド大使館の書記官が吉川光に齎した時点では、すでにフィンランドは戦線離脱していたのである。そうした状況の中で、貴重この上ないほどの決定的な情報を日本に伝えるということが、身の危険を伴わなかったはずがない。それにもかかわらず、書記官は吉川に情報を伝えてくれたのだった。その高貴なる行動には深く感謝し、永く記念して忘れてはなるまい。
だが同時に、その尊い行為を無にしたわが日本の硬直化を恥じるべきである。しかし、戦後六〇年経った今では硬直化はさらに病状進昂して「情報音痴」と歎かれる体たらくに日本はある。そうした状況をきっぱりと改め、いつの日かフィンランドに恩返しをしなければ、相手に誹られこそしないものの、日本は恩知らず恥知らずの国として汚名を雪ぐことができないであろう。
もっとも、フィンランド自身は一九二一年にアハベナンマー諸島の帰属がスウェーデン(オーランド諸島と称する)との間で争われたとき、国際連盟の採決でフィンランド側を支持したことを多として永く感謝していて、吉川への情報提供も、そのお返しという意味もあったのかも知れない。
多くの島々から成るアハベナンマー諸島は二万余という人口のほとんどがスウェーデン系だが、フィンランド最南に位置して温暖な同諸島は、国土の三分の一が北極圏に属する国にとって貴重な領土だったのである。
ちなみに、フィンランドというのは英語名であって、フィンランド人たちは自国のことをスオミ Suomi と呼んでいる。慣用上の便宜は別にして、正式国名としてはスオミと呼ぶのが礼儀であろう。だが悲しいかな、現在はまだスオミといったのでは何のことか意味が通じないので仕方なくフィンランドと書くことにする。スオミという国名が日本語で定着する日の来ることを願うばかりである。
●遠く遙かな国のこととて、フィンランドと日本との直接の交渉は数少ないが、鎖国時代の日本人漂流民に多大の恩義を与えて帰国のために尽力してくれたのがフィンランド人だった。
寛政四年(一七九二)根室に来たり、そこで越冬し翌年松前で幕府役人と通商交渉したアダム・エリコヴィッチ・ラクスマンのことは歴史の年表にも載っている。
その父親はフィンランド出身の博物学者、ペテルブルグ学士院会員にしてガラス工業家でもあったエリク・ラクスマンという。当時エリクはでイルクーツクに住んでいた。そこへ日本人漂流民の大黒屋光太夫がロシア人毛皮商に連れられてやってきたのだ。
光太夫は江戸に向かう途中に遭難しはるばるアリューシャン列島にまで流れ着いたが、そこでロシア人毛皮商に拾われ各地を転々、延々旅をしてバイカル湖のさらに西、広大なロシアのど真ん中に位置するイルクーツクにやってきたのだった。エリクは光太夫に大いに同情して、帰国の手だてを講じようと首都ペテルブルグまで同道、エカテエリーナ二世への謁見を取りはからったのである。
日本人漂流民の送還はともかく、日本との通商関係の樹立には女帝が心を動かし、使節の派遣とは相成ったのだった。エリクはその使節としてロシア海軍士官だった次男アダムを推薦し認められた。
わざわざ使節を仕立てるよう女帝を説得し光太夫を日本に送り届けてくれたのはエリク・ラクスマンとその息子アダム・ラクスマンというフィンランド人の父子だったのである。
●話はいきなり現代に跳ぶが、フィンランド人が最近に成し遂げた偉業は、何といってもコンピューター基本ソフトであるリナックス Linux の開発に先鞭を付け、それを無料で公開したことであろう。
一九九一年ヘルシンキ大学の学生であったリーナス・トーバルズ Linus Torvalds は、それまでコンピューターの基本ソフト(OS)といえば、ユニックス Unix や ウィンドウズ Windows に独占されていた状況にあって、それらに頼らないまったく新しい基本OSの着想を得て開発を始めることにした。しかもその開発を、ようやく世界的規模で利用可能になってきたインターネット上で公開して、みんなでいっしょにやりましょうと呼びかけたのである。
日本におけるリナックス情報提供サイトの「日本のLInux 情報」(http://www.linux.or.jp/)の中にトーバルズがLinuxを開発することになった経緯とその公開への歴史的な呼びかけの言葉を見つけたので紹介しよう。
「 Linux 一般に関する情報」という頁の中の「 Linux とは」にこう記されている。
もともと Linus は個人的なプロジェクトとしてカーネルのハックを始めました。そのきっかけとなったのは Minix という OS への興味でした ( Minix は Andy Tannenbaum によって開発された小さな UNIX システムです)。Linus 自身の言葉によれば「Minix よりも優れた Minix」を作るために開発を始めたということです. そしてこのプロジェクトをしばらく独力で進めたのち、彼はcomp.os.minixに以下のような内容の記事をポストをしました。
「Minix-1.1 のすばらしい時代、そう、男たちが真の男たちで、自分のデバイスドライバを自分自身で書いていた頃に憧れませんか? 良いプロジェクトに恵まれず、OS を自分の好みにあわせていじることもなく、ただぶらぶらしていませんか? Minix ですべてが順調に稼働している状態に、フラストレーションがたまっていませんか? かっこいいプログラムを動かすために徹夜するようなことも、最近なくなっていたりしませんか? このポストはそんなあなたのためのものなんです。
一月ほど前にも言ったように、僕は AT-386コンピュータ上で動作する、Minix ライクでフリーなものを作ろうとしています。どうやらなんとか動くところまできたので (「動く」という言葉の定義はともかく)、ソースをより広く公開したいと思っています。まだバージョンは 0.02 です… でも僕はこの上で bash や gcc、gnu-make、gnu-sed、compress などの動作を確認しています」
一九九一年一〇月五日、Linus は Linux 最初の「公式」バージョンである version 0.02をアナウンスしました。これ以降、多くのプログラマが Linusの呼びかけに応え、Linux を今日のような機能の揃った OS へと作り上げる手助けをしていったのです。(表記を一部改めた)
専門用語が頻出して私など門外漢には理解しがたい面も多分にあるが、あえて引用したことをお許しいただきたい。
このトーバルズの言葉には世界中の技術者たちが賛同して協力し、日本人も大いに貢献してきたと聞く。
それから一五年、日本の企業でも Linux を社内コンピューター・システムの基本OSとして採用するところが三分の一を超えたとの統計もある。
無料公開され世界中の技術者の協力により日進月歩を続けるリナックスは、欠陥だらけでしかも高額との悪評が高いマイクロソフト社のウィンドウズに対して充分拮抗するまでに育ってきたのである。
基本OSであるリナックス自体は無料なのだが、実際に導入するには高度の知識が必要とされるため、「理解できないがとにかくすぐ使いたい」という大多数のわがままな利用者には、いまいち難点がある。
だが日本人の感性にぴったりのワープロ・ソフトの代表である「一太郎」のリナックス版も昨年初頭に発売されてまだまだ割高ではあるが価格が落ち着いてくれば、リナックスの利用者は一挙に拡大するだろう。かくいう私もその一人となることを願っている。
●リーナス・トーバルズの言葉に大いに共感するのは、その中に一種の職人気質を感じるからである。
それは、出来合のお仕着せを断固拒否する自由な精神と自分独自のものを創り上げようとする矜持、そして出来上がればそれが皆の役に立って欲しいと願う謙虚さとが不思議にも同居する精神である。
こういう精神は、日本人には大いに分かる。だが、リナックスの開発・改善に向けて世界中のコンピューター技術者たちが協力しているということは、それは何も日本人に限らず世界の多くの人の共感を呼んだということであろう。
ここには、掠奪と支配を旨とする西洋近代文明の原理とは根本的に異なる考え方がある。しかもそれは世界規模で日夜進行しつつある実際の営みを支えている考え方なのである。われわれは新たな文明の誕生に出会っているのだ、と喜んでも決して間違いではないように私は思う。
著作権というものの在り方も、本来はこうあるべきではないだろうか。独創的で価値のある発明ならば、より多くの人が利用・活用することにこそ真の意義があるはずである。他人に使わせまいとする発明など本来は自己矛盾ではないか。実際に使ってみて役に立つ発明なら、利用者は発明者に心からの敬意と感謝の気持ちとを捧げるだろう。恥知らずの輩が感謝を捧げなくても、また剽窃しても、歯牙にも掛けないというのが、潔い高尚な態度である。
そして、能力ある者は自分もまたその発明の改善に向け自分なりの独自の工夫を加えて共同事業に参加して協力したいという気持ちになる。そう言う響きがトーバルズの言葉には感じられるのである。
能力のない者は肩身の狭い思いをしつつ利用するだけになるが、どこか別のところ自分にできる分野で貢献すればよい。そうすれば、ひとつの発明が多くの人を巻きこんでどんどん拡がっていくことになる。
ところが、現在の著作権の考え方は、その代価を過大に主張することによってせっかくの発明を利用させないように機能していると言ってよい。せっかくの発明を窒息させようと首を絞めているのが、外ならない著作権の保護を標榜する著作権法と言わざるをえない。
現在の著作権法が改悪を重ねてきたのは、アイディアに乏しいハリウッド映画が過去の資産の権利で食いつなごうとしたために際限のない著作権期間の延長を繰り返してきたことに根本的な原因がある。
そうした浅ましい根性とトーバルズの気高い精神とを比べてみれば、どちらに加担したくなるかは誰にとっても陽を見るより明らかであろう。
●ここからは私のまったくの独断であると自覚しているが、権利や金銭とはまったく異なる次元で、「いいものをみんなで作りましょう」というトーバルズの発想は、ツラン民族特有の考え方ではないかと思うのである。
先に挙げたわずかなフィンランド人の行為からも、彼らの底なしの善意が感じ取れよう。われわれはそうした行為に感動する。そしてそれに共鳴し、そうした行為を尽くされれば恩義と受けとる。打算や金銭とは次元を異にする、その気高い純粋な気持ちが分かるからである。
ユーラシア大陸の東の端からさらに海を隔てている日本と大陸の西の端に位置しているフィンランドとは、共通点は何もない。だが、なぜか共感できるものが多分にある。
その理由を強いて挙げれば、ツランの子としての遺伝子を共有するからとしか考えようがないのである。
もっとも、最近の日本人は「ヒルズ族」や「勝ち組」などの言葉が流行るように、強者の論理に振りまわされ強迫観念にまでなっているようで、ツラン民族の遺伝子は稀薄になっているのかも知れない。
そして、「ツラン民族」などという言葉は、一般には戦前の妄想として一笑に付されるのが落ちである。そう思ってきたところ、最近になって風向きが少々変わってきた。ツランという言葉が公刊された一般の書物に登場し否定的ながら評価されているのである。
世界的な規模での文明の大変動が、ついにここまで来たかとの感がある。
●「ツラン民族」を取り上げたのは、海野弘『幻想と陰謀の大アジア』(二〇〇五年九月、平凡社刊)である。
「極東の日本からユーラシアというスクリーンに投影された夢想映画」としての一〇個の「陰謀のセオリー」のひとつに「ツラン民族」という考え方が算えられている。
もっとも、海野自身は「ツラン民族」より「ウラル・アルタイ民族」という言葉の方を使いたがっているようだが、内容的には同じである。
海野が算えた一〇個の「陰謀のセオリー」はそのまま一章を与えられて論じられているので、それを列挙する。次の一〇個である。
1 満州国
2 ウラル・アルタイ民族
3 日本人・日本語の起源
4 騎馬民族説
5 大アジア主義
6 ユダヤと反ユダヤ
7 回教コネクション
8 モンゴル
9 シルクロード
10 大東亜共栄圏
これらを陰謀と位置づける海野のスタンスが奈辺にあるか、いまひとつ分かりづらい面がある。総じて「否定的な評価」を下していると言えようが、「否定」と「評価」とが均等の重みをもっているような否定であり、評価なのである。つまりは、魅せられつつも否定せざるをえないという奇妙な立場に海野は立っている。
その不安定なスタンスを海野が説明したのが、「プロローグ 歴史的想像力としての陰謀」である。一〇個の「陰謀のセオリー」を粗描した後で、海野はこう書いている。やや長くなるが纏めて読んでみないと意味をなさないので、あえて引用する。
それらのセオリーは日本がはじめて世界の場に出て、日本はどこから来たのか、世界の中で日本はどこにいるかを考えたものであった。それらは政治や軍事によってひどく歪んではいたが、日本が自らの起源を問い、世界観を語ろうとした試みであった。
第二次大戦の敗戦によって、日本は<満洲>や<大東亜共栄圏>について語れなくなった。それらは秘密のセオリーとなり、より陰謀的な色彩を濃くした。
<大東亜共栄圏>を禁句とするあまり、日本の歴史は大陸的なスケールや構想力を失ってしまった。日本史は、小さな地域や部分しかあつかわなくなった。その代表が<ヤマタイ国>である。日本中の各地がヤマタイ国に見立てられる。
おそらく、江上波夫の∧騎馬民族説∨は戦後の日本でほとんど稀な、大陸的スケールを持ったセオリーであった。だがそれは、戦前の大陸体験に起源を持っていたから、それについての論議は部分的にとどまり、展開はされなかった。
それらの説が解禁されるようになったのは、一九九〇年代になってからである。戦後の半世紀を日本はずっと閉じこもりで過ごしてきたといえるだろう。そして突然、外に出されて、呆然としているともいえる。イラク戦争やチェチェンの紛争のテレビ・ニュースを見ながら私はそのことを感じる。それらの出来事と日本、そして自分との関係をどうしてもつかみかねているのだ。
私たちは戦後、国際的になり、同時代的な情報に生きていると思っている。だがそうだろうか。戦前における東欧からやって来たユダヤ人、ウラルからやって来たトルコ・タタール系ムスリムなどとの不思議な絆は、それらの情報より、はるかにいきいきして、具体的だったのではないだろうか。
私は戦前に出された満州論、大陸論といった忘れられた本に興味をひかれる。そこでくりひろげられている歴史的想像力、あるいは陰謀のセオリーはもう無意味なのだろうか。しかしそれらは今なお私の想像力をかきたてる。そこに埋もれているが、私に気になることばを発掘してみたい。(同書一一~一三頁)
世界の出来事と日本、そして日本との関係をつかみかねていると正直に告白する海野の心境は無理もない。日本も日本人も自らの意志で生きていないからである。占領を解放と言い換えた敵のペテンをそのまま信じこみ、掠奪を市場原理だと納得しているようでは、世界との生きた関係が結べようはずもない。
本号「常夜燈」でも取り上げているように、その最たるものが現行の日本国憲法であることは言うまでもない。国家の骨格たる軍隊を違憲とする憲法など、一日も早く廃棄するに越したことはない。国家のために戦って死んだ英霊をお祭りした靖国神社に対する国家の祭祀も憲法違反だという。この伝で行けば、日本人そのものが憲法違反だとの判決も出かねまい。そういう憲法を「平和憲法」だからと護持を言い立てる政党がいまなお存在するのだから、日本人が世界の「出来事と日本、そして自分との関係をつかみかねている」のもしごく当然といえよう。
海野の口吻には南京大虐殺や従軍慰安婦をめぐる自虐史観ほどの事実無根さはないが、どうにも自虐的な響きが感じられてならないのは、私だけだろうか。
「ツラン民族」「ツラニズム」などの言葉が登場する第二章「ウラル・アルタイ民族」の末尾の方で、海野はこう言っている。
戦後、ツランとともに<ウラル・アルタイ>の語も埋もれてしまった。<ツラン>は、幻想的なことばであるが、<ウラル・アルタイ>は言語学から来た学問的なことばだったはずだ。なぜそれも消されたのだろう。学問的に否定されたかどうかはまだ疑問だが、日本帝国主義<大東亜共栄圏>などへのアレルギーに結びついて、使うのが避けられたという面が強い<満州>などの語と一緒に葬られてしまったのである。
……いかなる学問もまったく純粋というわけにはいかない。国策の都合を無視できないのである。問題は、それにもかかわらず純粋のふりをすることだ。ウラル・アルタイ説を唱えるのも否定するのも時代の都合を反映している。
……私が気になるのは、知識や体験が蓄積されていかないこと、つまり歴史化されないことだ。日本は戦前の知識や体験を敗戦とともにあっさりと清算してしまった。一億総ざんげなどといわれる。戦前と戦後がうまくつながっていない。(同書、六四~六六頁)
使うのさえ避けられ葬られていた「ツラン」や「ウラル・アルタイ」という言葉をあえて取り上げた海野の勇気には脱帽しよう。
しかし、戦前の歴史的想像力を封印したままで、そこから一歩も出ていない、そのどこがよいのか悪いのか聞かされていないと焦れったい思いを言うのなら、海野さん、あなたがやったらどうなのか、と私は言いたい。
ただ、この問題を解禁するという先鞭を付けた海野にそこまで求めるのは酷というものではあるだろう。
もちろん、「陰謀のセオリー」を歴史的想像力と捉える海野は関連の事実を丹念に拾っており、裨益されたことも多くある。この点は大いに感謝しなければならない。
ツラン民族」は『幻想と陰謀の大アジア』の中でどうのように取り上げられているのか。それは次号で……。 (つづく)★