
 |
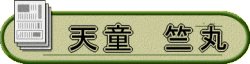
![]()
![]() フォンランド技術立国に貢献した日本人 1
フォンランド技術立国に貢献した日本人 1
(世界戦略情報「みち」平成18年(2666)2月1日第221号)
●わが国において「ツラン民族運動」を提唱しハンガリー・ツラン同盟より在外最高顧問「ツゥルル」に就任を要請された今岡十一郎[一八八八~一九七三]については、かつて本誌でも何度か取り上げたことがある。
今岡十一郎と「ツラン民族」との出会いは、大正三年(一九一四)来日したハンガリーの民俗学者バラートシ・バローグ・ベネディクの北海道・樺太研究旅行に通訳として同行したことが機縁だった。その後、今岡は一〇年間にわたってハンガリーに留学、帰国すると「ツラン民族運動」の日本における推進者となった。そのため『ハンガリーのツラン運動』(昭和八年)や『ツラン民族圏』(昭和一七年)を刊行している。
海野弘が「ウラル・アルタイ=ツラン民族」に興味をもったのも、今岡十一郎がきっかけだったと書いている。
『ウラル・アルタイ民族の人類学的考察』というH・ウィンクレルの著作を今岡が訳した本を読んだのである。この本は一九七〇年に審美社から刊行されたとあるから、今岡晩年の刊行である。
この本に今岡十一郎の「訳者のことば」が載っていて、海野は「ウラル・アルタイ民族」を説明するために、『陰謀と幻想の大アジア』の中にその文章を引用している。孫引きだが、ここに紹介する。
「ウラル・アルタイ民族とは、いったいどんな民族か──それは狭義においては、ウラル・アルタイ山脈にすむトルコ族その他の小種族のことをいう。また広義においては、遠い昔から、北はアムール・レナ・アンガラ・エニセイ・オビ・ルティッシュ・トボル諸河川の源泉におよび、南は黄河、バルカシュ・アラル両湖におよび、西はカスピ海にまで達するステップ草原にさすらう遊牧民、ヨーロッパ人の、いわゆる頭の丸い、めじりの上がったモンゴール型の民族をいう。あるいはまた、ウラル・アルタイ民族とは、これを言語的にみれば、ウラル・アルタイ語をはなす民族群団であるともいい得る」(海野同書、四六頁)
これに対して、海野はその構想の雄大さに驚嘆してみせつつ、それは日本が満洲を起点として中央アジアに伸びる連帯を求めていたからで、「ウラル・アルタイ=ツラン民族圏は、それにぴったりの理論であり、〈大東亜共栄圏〉に重なってくる」と謎解きをしてみせる。
さらに、「だからこそ、一九三〇年代から四〇年代はじめにかけて、ウラル・アルタイ論が花盛りなのである」とも付け加えている。
つまり、あえていえば、海野弘のウラル・アルタイ論に対する評価は、「雄大な構想」と感嘆しつつ、海外雄飛を国策とした当時の日本の国家意志に迎合する虚説であった、との含意が底流にある。
そして、いわば国家的なミーイズムに沈淪する現代にあって、たとえ虚説であるにせよ、雄大な構想を抱いて世界と直に向き合っていた戦前の日本を羨望するのである。
こういう毀誉褒貶の同居するアンビバレンツな心理は、私にはどうも苦手である。虚説というなら、どこが間違っているのか指摘しなければ、そこから先へ論が進まないはずであろう。それをただ、「雄大な構想だった」と感心してみせるだけでは、とどのつまり海野は何を言いたいのか、釈然としない。
総じていえば、『陰謀と幻想の大アジア』の中で各一章ずつ与えられて論じられる「満州(ママ)」から「大東亜共栄圏」までの一〇のテーマのそれぞれについて、海野は一方で感嘆しつつ、もう一方では嘲っているのである。
こうした態度は、戦後から現在まで続いている、「権力に迎合した」と嘲笑すればすべて終わりというレベルに比べれば、一歩を抜きんでる態度ではあるだろう。だが、あくまでもそれは、自分は安全圏に身を置いて他人が矛盾の最中で悪戦苦闘する様を「よくやるナー」と感嘆しつつ嘲笑する、傍観者の態度というべきである。
海野弘の著書を読んで、教えられることが多々ありながら、最終的に不快感を禁じえないのは、この辺に理由がありそうである。
海野は「ウラル・アルタイ民族説」を評していう。
「……ウラル山脈を中央として、ユーラシア大陸に広がる雄大な民族圏の構想なのである。そしてウラルとアルタイを一つにくくることができるなら、それはなんと極東の日本から、ヨーロッパのハンガリーやフィンランドまでつながっていることになる」(四六~四七頁)
そんな莫迦なことはありえないという口吻がありありと感じられよう。
確かに、言語学の最近の動向においては、「ウラル・アルタイ語族」として一つの言語グループとみなせるほど「アルタイ語族」と「ウラル語族」とは親近性がないとされているようだ。
だが、言語学を少々かじった経験からいえば、言語比較の方法論そのものが仮説の域を出ない代物であって、そうした物差しで測って割り出した「言語グループ」というものも、やはり「仮説」の域を脱しないと見なければならないように思う。
しかし、それでよいのではないか。色々な物差しを使って測ってみて、吟味していくうちに意外な事実や遠近関係が分かってくる。フィンランド語やハンガリー語がヨーロッパ諸言語の仲間ではなく、中央アジアに親近性をもつと分かっただけでも大きな成果である。さらに、アルタイ語として分類される諸言語とも、兄弟ではないにしても従兄弟くらいの関係にあるとすれば、現在では地理的に遠く離れた位置にあっても、かつて近隣に住んでいた時代のあることを想像させてくれる。
現在、「ウラル語」と「アルタイ語」の間にあまり共通性がないことから、これら二つの言語を一グループにくくるのは無理があるとされ「ウラル・アルタイ語」をいう呼称が敬遠されているが、将来新たな物差しが登場し、両者の決定的な親縁性を論証しないとも限らない。ただ、現在はもっとも説得的な仮説に従うというだけである。
●ところが、意外なところから、日本人の一部はユーラシア大陸のど真ん中からシベリア、樺太・北海道を経て、堅く凍った津軽海峡を歩いて渡ってやってきたとする証拠が出てきた。
NHKで放送された『日本人はるかな旅』という日本人の起源を問う連続五回シリーズの「第一集マンモスハンター ── シベリアからの旅立ち」では、まさに「ウラル・アルタイ民族説」が想定したようにウラル山脈とアルタイ山脈のちょうど中間あたり、現在のイルクーツク近辺でマンモスを捕って暮らしていた人々が地球規模の寒冷化のせいで緑地が次第に狭まってマンモスが捕れなくなり、止むなくマンモスの群れを追って東へ南へ移動するうちに日本列島に辿り着いたとの説を、CGをふんだんに交えて、それこそ目に物を見せて紹介した。
そのはるかな旅の証拠として挙げられたのが、「細石刃」といわれる高度な石器と土器の共通性である。その旅はおよそ三万年前から二万年前のころというから、いわゆる縄文時代の直前まで続いたことになる。
さらにまた、シベリアでマンモスを追って暮らしていた人々が日本列島に辿り着いて、今度は温暖化の激変に遭遇しマンモスなどの巨大獣が絶滅するという食糧危機に際会して、止むなく照葉樹林に住む小型動物や木の実の堅果(ドングリなど)を食糧とするにいたるさまが、説得力をもって描かれている。堅果の渋味やえぐ味を抜くために、シベリアではもっぱら貯蔵用として製作・使用された土器が煮沸という新しい用途のために改良されて縄文土器となった、というのである。
実に興味深い内容で、是非とも紹介したいのだが、同志の林廣さんが録画したものを二回ほど見せてもらったばかりなので、いつ放映されたのか、シベリアの遺跡(その名前も書き留めておかなかった)で発掘された土器は何というのか等々、詳細については後日を期したい。
ここではただ、中央アジア北部のシベリアからはるばると日本列島までマンモスを追って日本人の祖先がやってきたという説には、非常に説得力があったことだけを言っておきたい。
言語学が慎重を期して臆病になっている傍らで、考古学が物的証拠を挙げて壮大な仮説を証明しようとしているのである。
海野のように、戦前の日本の満蒙に対する強い関心を帝国主義的野望と断じて「途方もない夢を抱いたものだ」と感嘆したり嘲笑したりするだけの傍観者の時代はすでに過去のものとなりつつある。
さらに、使えそうな物差しとして私たちは「遺伝子検査」をも手に入れつつある。これが言語グループや考古学的遺物に適用されて動かぬ証拠を発見することがあるやも知れない。この物差しを使って、安田喜憲氏などが花粉分析という方法論によって考古学・文明論の分野で数多くの成果を挙げている事態を、さらに飛躍させるかも知れないのだ。
●海野弘に教えられたことは、数多くある。そのひとつは、「ウラル・アルタイ民族説」のそもそもの発祥はフィンランドだったという事実である。
「この雄大な民族圏、言語圏を最初に考えたのは、フィンランドのM・A・カストレーンであった。十九世紀の半ばに彼はフィン、サモイェード、チュルク、モンゴル、ツングースの間に血族関係があるとのべた。
重要なのは、この考えが、フィンランドやハンガリーから出発していることだった。これらの国々は、民族の起源を求めて、ユーラシア大陸に向かったのである。それはやがて民族独立運動へとつながっていく。つまり、ウラル・アルタイ論は純粋な言語学・人類学の枠内には収まらないのである。特にハンガリーにおいては、ツラン民族運動として、オーストリア・ハンガリー帝国からの独立運動として展開された。そしてハンガリーは第二次大戦前、極東の日本へツラン民族としての連帯を求めていたのである」(四七頁)
これは嬉しい事実である。これまでツラン民族説といえば、近代民族国家の建設に燃えるトルコで汎トルコ主義運動として始まって、ハンガリーで花開いた運動だとばかり考えていたが、それは間違いだったのだ。
では、この説を最初に唱えたというフィンランド人のM・A・カストレーンとはいかなる人物であろうか。
インターネットで調べてみると、いま日本でフィンランドについて積極的に研究・紹介の作業を行なっている第一人者は、どうやら東京大学教授でウラル言語学を研究対象とする松村一登氏らしい。氏は駐日フィンランド大使館公式ホームページ中の「国歌」や「歴史」の項を日本語に訳し、自身のホームページ(http://www31.ocn.ne.jp/~kmatsum)の中に含まれている「フィンランドのページ」(suomi.html)という欄に掲載している。
さすがは専門家と感心するのは、日本語では「フィンランドのページ」と題した欄をネット上のアドレス(url)では、きちんと「suomi」とフィンランドの正式国名で名づけていることである。こういう濃やかな配慮が貴重である。
ここには、松村氏のフィンランドに関する雑誌発表論文やさまざまな情報が公開されているが、その中にM・A・カストレーンについても紹介されていた。本で探すとなると、相当の時間と労力とお金がかかるだろうに、インターネットで検索してみると、駄目な場合もあるが、ある程度の調べは付く場合もある。居ながらにして、分かるのである。有難いことである。

上掲のカストレーンの写真も松村氏のホームページから借用させていただいたものであるが、その解説は次のように書かれている。
「カストレーン Mathias Alexander Castrén (一八一三~五二) 言語学者。ヘルシンキ大学の学生時代に、Z・トペリウスとともに、J・L・ルーネベリ家に下宿し,その影響を受ける。一九三九年夏、フィンランド文学協会の助成でカレリアに長期滞在。一八四〇年、ヘルシンキ大学講師。二回(一八四一~四四、一八四五~四九)の長期調査旅行で、ロシア・シベリアのウラル諸語、チュルク諸語・モンゴル諸語などの現地調査を行う。ヘルシンキ大学のフィンランド語講座の初代教授(一八五〇~五二)。フィンランドにおけるウラル比較言語学の方法を確立させ、サモエード諸語を初めとする西シベリア地域の諸言語の文法記述のひな型を作った。
ヘルシンキ大学本館のフィンランド語学科の研究室や図書室がある階を「カストレニアヌム」(Castrenianum) と呼ぶのは、カストレーンの名前に因んだもの。ヘルシンキのカリオ (Kallio) 地区にカストレーン通り (Castréninkatu) がある」(部表記を改めた)
気になったので、「インド・アーリア語」なる言語グループを定着させた印欧語比較言語学の完成者とされるマックス・ミューラーの生没年も調べてみた。こちらは(一八二三~一九〇〇)となっていて、カストレーンよりも一〇歳年下である。マックス・ミューラーはドイツ生まれであるが、英国東インド会社に招聘されて英国に渡り、英国によるインド支配の学問的根據となる理論を完成させた人物である。最後は英国に帰化した。
マックス・ミューラーは知る人ぞ知る人物で、カール・マルクスやジグムント・フロイトほど一般的には知られていないが、英国のシティーに中枢を置く世界権力にとっての学問的貢献という点とその理論の浸透度からいえば、まさに巨人と称すべきであろう。真の御用学者と呼んでもよい。「御用学者」と呼べば、呼んだ方も呼ばれた方も蔑称だと信じて疑わない日本からは想像を絶する「学問」の世界なのである。
比較してみると、カストレーンはミューラーより一〇歳年長だが、三九歳でなくなっているから、いかにも早逝である。その短い生涯の間に、「ウラル・アルタイ言語族」を創唱して理論づけたのだから、紛れもない天才と言うべきであろう。
主要な論文や著作の公表において、どちらが先だったのか、詳しく調べてみないと軽々には断じられないが、印欧語比較言語学の創唱者のマックス・ミューラーに比肩しうる学者がフィンランドに生まれ、フィンランド語がウラル・アルタイ語族の一員であることを創唱したことだけは確かである。しかも、フィンランドがまだロシアの属領だった時代に、である。大した人物がいたものだ。
●海野弘は先に引用した中で、フィンランドやハンガリーの国々は、「民族の起源を求めてユーラシア大陸に向かった」と言い、それが重要なことであるとも指摘している。
ではなぜ同じことが日本について言えないのか。それは明らかに、事実として日本にはそうした国策も行動もなかったからである。 だが、本当にそうだろうか。これまで言われてきたように、日本の安全保障や経済利権などの国益という観点からすれば、満洲建国にせよ徳王政権樹立あるいは汪兆銘政権支援にしても、果たして日本の国益のために成果があったのかどうか大いに疑問である。
本号の角田稿でも言うように、八千万人の日本が四億人の支那を支配しようなどというのは無謀であるし、米国に乗りこんでいって支配しようという例に譬えるまでもなく、狂気の沙汰であるには違いない。
収支計算から言っても、勘定が合わないのである。植民地収奪どころか、軍事費やら借款やらの名目で巨額の国費を傾け満洲や支那に注ぎこんだというのが実情に近い。しかも、日本本国では多くの国民が飢えに苦しみ生活が成り立たないという惨状を呈しているというのに……。
確かに日本が注ぎこんだ巨額の資金で満洲でも支那でも治安は良くなるしインフラも整備されたが、そんな善意の発露が目的だったわけではあるまい。
ともかく、やることなすことちぐはぐで、いかにも稚拙極まりないという感を拭えないのである。
実態としては、なぜかしら血が騒いで大陸へ大陸へと草木も靡くほどの入れこみようだったことだけは事実である。
これを、日本民族が民族の起源を求める行動だった、といえばどうか。ただし、それはまったく自覚されない衝動だったので、辻褄の合う理由を何とか付けようとしたのだが、いずれも説明には不十分で、訳が分からない始末になってしまったのである。
こんなことを言うのは暴論であることを承知しているが、海野がその著書で挙げた一〇の「陰謀と幻想」はそのどれも日本が民族の起源を求めてひたむきに紡いだ壮大な夢だったといえなくもない。
だからこそ、当時軍が唱導していた国家の利害や権益などとはまったく無縁のところで、単身何の準備もなく支那人や蒙古人の中に飛びこんで嬉々として大活躍する伊達順之助や小日向白朗の話を読むと、血湧き肉躍る大感激を味わうのである。
伊達や小日向は支那人以上に支那人の間で人望を得るし、蒙古人の間で蒙古人以上に勇敢に戦う。ただ一点において彼らと決定的に異なるのは、狡猾な駆引がからきしできないことである。まことに清廉そのものなのだ。だから読んでいて時に歯がゆく思うこともあるが、終始変わらないのは満腔の応援と拍手をもって味方してしまうことなのだ。
●最近しきりに想い出しては自分でも何だか楽しい気持ちになり、人にも語っていることがある。それは歌手の加藤登紀子がNHKで新旧のシルクロード・シリーズを前後して放映した番組のゲストとして呼ばれて語った話である。
加藤が大のシルクロードファンだというのはNHKへのリップサービスかも知れないが、シルクロード沿いの国々のほとんどを訪ねたことがあるというのは本当だろう。中共政権が進入禁止にしている新彊ウイグル自治区を除いて、シルクロードの全域に足を踏み入れたことがあるという。
その加藤登紀子が言うには、シルクロード沿いの国々はどこへ行ってもとても親しい気持ちが湧いてきて、よその国に来たとは感じられないのだそうだ。とくに、カザフスタンなどでは顔つきや態度振舞まで日本人にそっくりなので、なんら違和感を感じないという。 カザフスタンの人にそう言うと、当り前じゃないかとばかりに呆れた顔をするのだそうだ。そして、言うことが振るっている。
「もともと日本人も俺たちといっしょにここに住んでいたんだ。それが湖が干上がって魚が採れなくなったものだから、どうしても魚を食べたいという連中が東の海まで行って魚を食っている日本人になったんだ。俺たちは肉でも我慢できるから、ここにずっと暮らしているのだ」
湖が干上がったのが何世紀なのかなどと、野暮な詮索をしてはいけない。カザフスタンの人々がたとえ歓迎の冗談であったにせよ、日本人と俺たちは同じ民族だったんだと信じていることが大事なのである。私はカザフスタンに行ったこともないしカザフスタン人と付き合ったこともないから何とも言えないが、加藤登紀子の言によれば、カザフスタン人と日本人はそっくりなのだそうである。
同じ民族でも、俺たちが柔軟なのに比べて日本人になった連中は頑固で柔軟性に欠ける困った奴らだとの揶揄が込められているわけだ。こういう揶揄は素直に受け取ろうではないか。
●フィンランドに関して、是非とも書きたいことがあったのだが、末尾が近くなってしまったので脈絡を無視して、ここに挿入する。 ノキアというコンピューター関連製造会社のブランドがあるが、これがフィンランドの会社なのだそうである。それをわざわざ教えて頂いたのは、先号の拙稿を読んで会ってくださった方である。まことに有難いことである。お名前はあえて秘す。
別の話もあったのだが、私はノキアという会社がフィンランドの会社とは知らなかったし、ましてフィンランドがエレクトロニクスで立国するにいたる背景に、一人の日本人の貢献があったなどということは露知らなかった。
その日本人は久保田正さんという。紹介の話によると、昭和四年生まれというから今年で七六歳くらいの人である。父君は明治政府の検察官をしていた方だそうだが、北朝鮮で殺されたという。久保田正さん自身は一三人兄弟で育ったが、昭和五四年にフィンランドに行ったのだそうだ。
紹介はここまでなのだが、何とも嬉しいことに久保田さん自身の本から十数頁をコピーして持ってきて下さった。本の題名や出版社など聞きたくてたまらなかったのだが、何か聞くのを憚られるような気がして、すぐ調べようと思いながら今日まで時間が経ってしまった。
久保田正さんの本の「3 北欧は技術者の評価の仕方を知っている」という章の全部が手もとにある。
まずその章が左側から始まる右側(三六頁)の文章が目に飛びこんできた。その文章がいい。
「……技術者が本質的にもっているためである。そのような仲間がいなければ、自分の技術が育たないせいでもある。
刺戟を与えればいい、秘密がバレなければいいと言うが、たとえ最先端技術情報であっても、技術者が自分の技術を広く交流させることは、両者が共にその技術を高めることであり、決して企業を危うくするものではない。技術と営業努力とは短絡しない。『特許が切れて、他の競争会社が同じような製品をつくりだしてから、特許をもつわれわれの製品も売れ出した』というある企業のトップの発言は、技術者の交流の本質をついている」
欠落部分があるので、文章の流れの全部は分からないが、それでも久保田さんの言わんとすることはよく分かる。特許は特許として取得すればよいが、技術者はそれに縛られないで大いに交流する方が自分のためにも他のためにもなるという明快な論理である。
いささか自慢したい気持ちを抑えられない衝動に駆られるところだが、先号に著作権に関して書いた拙文の趣旨と同じだと考える。技術に関してまったく経験のない奴素人の書いたことが、超一流の技術者の言に適ったのである。喜んで悪かろうとは思わない。
技術は広く交流することが自他共に高めることだと久保田さんは説くのだが、その彼がフィンランドのエレクトロニクス立国に多大なる貢献を果たすのである。(つづく)★