
 |
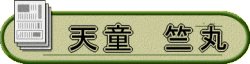
![]()
![]() フォンランド技術立国に貢献した日本人 2
フォンランド技術立国に貢献した日本人 2
(世界戦略情報「みち」平成18年(2666)2月15日第222号)
●最初にお詫びをしなければならないことがある。先号に書いた拙稿の内容に重大な誤りがあった点である。それがお話にもならないような恥ずかしい誤りだった。表題に掲げた「フィンランド技術立国に貢献した日本人」のお名前を、間違って表記していたのである。拙稿では「久保田正」氏と書いたのであるが、本誌の読者の方からのご指摘によって正しくは「窪田規」氏と書くべきことが分かった。耳で聞いたまま生来の早とちりで「久保田正」と勝手に思いこんで疑いすらしなかったのであった。
子供のころ、祖母に「うん知った鳩の巣」と何度も窘められたことを、今さらのように想い出す。ご承知のように、鳩は巣の近くに決して舞い降りず、まず遠く離れた所に舞い降りてやおら安全を確かめた後に巣に近づく。だから、鳩の舞い降りた所が巣だと思いこむような早合点・早とちりをするなと諭したのが、この格言である。
名前が間違っていたので、調べても分からないはずである。「窪田規」という名前で検索すると、化研テック株式会社のホームページ(http://www.kaken-tech.co.jp/)に特別欄として「TK銀粉生みの親 窪田規 博士」と題して紹介のページ(http://www.kaken-tech.co.jp/product/dr_kubota.html)がある。同社の技術顧問も務めておられることが肩書き欄で分かるのだが、その関係から窪田氏が紹介されているらしい。
その紹介ページに、以下の写真が掲載されている。百万言を費やしても隔靴掻痒の感のあるのが人物評であるが、たった一枚の肖像写真が多くを語ることは稀ではない。窪田氏のこの写真も、その人となりの多くを伝えているように思われたので、転載させてもらうことにした。

同じく肩書きの欄に、窪田氏の専門分野が「受動回路素子材料の物性とその応用技術」と書かれているが、門外漢には何のことやら判然としない。ただし、K氏から頂いた資料を読んで、どうやら「電子機器の部品を作る材料の素材」を研究してこられたのではないかと想像した。化研テックのホーム・ページにあるTK銀粉やTKペーストというのも、窪田規氏のイニシャルをとって命名された氏の発明・開発による製品であるらしい。
紹介ページの「職歴」という項を見ると、昭和二九年東京理科大学理学部化学科を卒業して株式会社タムラ製作所に入社して以来、昭和五三年にタムラ化研代表取締役とタムラ製作所取締役を退任するまでほぼ四半世紀をタムラ製作所とその系列会社で務めてこられたようだ。
●窪田規氏の著書については、拙稿を読んで下さったK氏からわざわざ電話を頂戴して、詳しく教えていただいた。窪田氏の名前を勘違いしていたため調べることも行き詰まって困っていたところに届いた救いの電話であり、重ね重ねのご厚意であった。身に余る過分の光栄と言うべきである。
『技術者の能力をひきだす』(一九八五年五月、草思社刊)というのが窪田氏の著書の題名で、「企業競争に打ち勝つために」という副題も添えられている。
豊富な品揃えを誇る近所の大型書店に早速問い合わせてみたところ、在庫もなく版元でも品切れだとのことであった。それでは古本ならどうだろうか、ウェブ上で探してみると、これがあったのである。注文を出しているが、届くまでには今しばらくかかりそうである。本稿はやはりK氏から戴いたコピーに拠って書くことにする。
●窪田規氏は永年勤めたタムラ製作所およびタムラ化研を退社してフィンランドに教えに赴くあたりの事情を、著書の中で次のように書いている。
「たまたま一九七八年(昭和五三年)五月に、在日フィンランド大使館の科学担当参事官でディール氏という人から会いたいという電話があった。当時の私は二十数年間、創立以来勤務したタムラ化研をやめて、親会社のタムラ製作所の取締役として本社に帰任していた。本社には私の研究の場所はなく、日々これからどうやっていこうかと思案していた矢先であった。相手は北欧の外交官であり、会社を紹介するチャンスでもあるので、日本のトランス会社の現状を見てもらいたいと思い、社長に報告すると、ぜひお招きしようということになった」
(窪田氏著書のコピーより三八頁)
こうしてフィンランドの外交官を迎えて、会社の概要を説明し、本社工場やタムラ化研の研究室と工場にも案内したのであったが、ディール参事官の目的はタムラという会社を知ることではなく、研究・開発者の窪田規という個人に接触することだった。
すべてが済んで夕方帰りがけに、窪田氏がふと気になって「私を名指しで尋ねてくださった目的はいったい何だったのだろうか?」と訊いたところ、ディール参事官はこう答えたのだった。
「実はあなたの論文を読んだ。そして昨年来日してからもあなたの講演(日本語)を聞いてぜひ一度会いたいと思っていた。自分はきっすいの外交官ではなく、ある電気会社の技術重役でハイブリッド技術が専門である」(同)
しばらく親しい付き合いがつづいた後に、ディール参事官から大使館のレセプションへ招待された。フィンランド国立オウル大学で電子工学を教えているレッバウォーリ教授が来日されて大使館でレセプションがあるので、そこで紹介したいというのである。
会ってみると、レッバウォーリ教授は窪田氏の論文をほとんど読んでいて、研究成果を高く評価していた。そして、教授からオウル大学で講義してくれないかと依頼されるのである。
「オウル大学は外国から専門の学者を招いて、一週十時間の集中講義を受けるユニークな客員教授の制度がある。あなたの専門の厚膜材料については研究論文も少なく、私の研究室で研究しているマスターの研究者にぜひ講義してほしい。自分自身もいま厚膜を使ったセンサーの研究をしている」(同三九頁)
ディール参事官の方も援護射撃をして窪田氏にフィンランドに来てほしいと説いた。
「フィンランドは日本のように工業立国をしたい。天然資源だけでなく、電子工業を育てたいと政府も力を入れている。そこで君もぜひ協力してほしい」(同)
参事官のいうフィンランドの天然資源とは、紙・パルプ・木材・合板などの森林資源や銅・ニッケル・コバルトなどの鉱物資源を指すのだろう。フィンランドはこれらの天然資源の輸出国なのである。天然資源をそのままで輸出するのではなく、加工しもっと付加価値を高めてから輸出したいと、フィンランドは願っていたのである。
おりしも、窪田氏もすでに引用した部分にあるように「本社には私の研究の場所はなく、日々これからどうやっていこうかと思案していた矢先」だったから、フィンランドからの客員教授にという話には、大いに心が動いたのは当然である。
もともと窪田氏には、死ぬまで技術者としての研究生活をつづけていきたいという素志があった。会社としては窪田氏がタムラ化研を育てた功に報いるため、子会社社長の職を解いて本社の重役に迎えたのであろう。だが、それは一生を研究者でありつづけたいと願う窪田氏から研究の場を奪うということを意味した。会社が良かれと思って用意した処遇が、かえって窪田氏には苦痛となったのだ。
窪田氏は正直に告白している。
「子会社を去って本社の役員に帰任した時、一部の方から祝いの言葉をいただいた。たしかに子会社の社長より親会社の重役は上席である。しかし技術者の私にとっては研究の場が全くない職場で喜びを感じることはできなかった。かつての先輩や上司との地位の逆転も気詰まりであった」(同)
こういう記述を読んでいると、素朴で純粋な窪田氏の人柄が偲ばれて心が洗われるような気持ちになる。地位が逆転した途端に昨日までの卑屈な態度を掌を返したように威丈高に変化させ、やたら権柄を振るいたがる輩が多い中で、窪田氏のように感じる人はまさに石中の玉ともいうべき存在である。
たしか、先ごろノーベル化学賞を受賞した島津製作所の田中耕一さんも「役員にしてもらうより研究を続けたい」と同じような心境を語っていたように記憶する。
窪田氏はこうも語っている。
「産業界に身をおく者が常に利益だけを追求するとは限らない。殊に技術者はそうである。自分からも望み、相手からも望まれる技術の研究と開発を生き甲斐にしたい」(同三九~四〇頁)
フィンランドの大学で専門とする分野について教えることは「自らも望み、相手からも望まれる」ことであったろう。その上に名誉なことでもある。
だが、窪田氏はここで「しばし待てよ」と考えた。
「しかし、それは望むべくして実現困難な理想論ではないだろうか。いい年をして理想の夢に惑わされるほど自分は愚かではないと、自らをたしなめてもみた。カスミを食べて生きていけるわけではないし、教育ざかりの子供も抱えてこれまで得てきた収入がとだえては困るとも思った」
(同四〇頁)
あれこれと悩んだ末ではあるが、窪田氏は結局フィンランドからの客員教授への招聘を受けることにしたのであった。
●窪田規氏のフィンランド国立オウル大学における講義は昭和五四年(一九七九)の八月二〇日から始まった。日本から客員教授を招いたことを聞きつけ、講義の初日に新聞記者が取材にやってきた。窪田氏の対応が珍しい。自分は日本の一市民であるから取材はお断りしたいと言ったのである。記者の方も了解して引き下がったという。なんとも清々しい話である。
それにしても、日本から客員教授が来たというので新聞記者が取材にくるというのは、日本人の客員教授が珍しいからでもあろうが(京大の塩崎教授が来講して以来、窪田氏が二人目だった)、フィンランド人に日本人には特別に親しみを感じるという気持ちがあったからではないだろうか。
●さて、これからいよいよ窪田氏の本領発揮である。大学で講義をするうちに、いろいろとフィンランドの事情が分かってくる。窪田氏にとって意外だったのは、フィンランドが西ヨーロッパから電子部品を輸入してそれを組み立てた電子機器を外国に輸出しているという現実であった。
これを聞いて、窪田氏はすぐにひらめいた。これはおかしい。フィンランドは北欧の先進国である。そのフィンランドが加工賃だけでこの先もやっていけるとはとうてい考えられない、と。
「日本も敗戦後しばらくは無一物だったから、安いレーバーコストを武器に電子機器を組み立ててかせいだ時代があった。しかし、それだけでは本当の利益は望めない。電子機器を組み立てる部品をつくらなくてはだめだ。優秀な部品をつくるには、すぐれた材料が必要である。そのために日本人は、素材の研究開発に努力して今日の技術を築きあげたのだ」(同四一頁)
敗戦後の混乱がようやく一段落した時期の昭和二九年に社会に出て、日本が復興する姿を目の当たりにしながら、自らもいわばその陣頭指揮に当たってきた、窪田氏ならではの鋭い洞察である。
日ごろは控えめで慎ましい人柄だが、こういうことになると黙っていられないのが純粋である所以であろう。窪田氏はフィンランド人に向かって歯に衣着せず説いた。
「近代工業技術と高い生活水準を誇るフィンランドの皆さんが、最も付加価値が生まれる電子部品の開発をあえて放棄し、外国から部品を輸入する道をえらんだ理由が私は全くわからない」(同四一~四二頁)
このことはフィンランドの研究者たちも痛感していることであるらしく、よくぞ言ってくれたとばかりに返事が返ってきた。
「実はわれわれも全く同感なのだが、政府筋の理解が得られないので困っている」
「人口四百五十万の国で行なう研究としては金がかかりすぎる、しかもこれからでは遅すぎるというのが当局の考え方である」
「だから他の欧米諸国や日本から部品を買う以外に方法はないと信じこんでいる。本当にそうだろうか」
フィンランドは日本からも部品を買ってくれていたのである。とすれば、このまま買いつづけてくれる方が、日本にとっては都合がいい。ただし、フィンランド政府の考え方は国家の政策としてやはり間違っている。そう考えると、黙っていられないのが窪田氏なのである。
「いや、それはまちがっている。良い部品を安くつくるところから付加価値が生まれる。良い部品は良い材料の開発から生まれる。だから素材の研究からはじめるべきで、そのことがすぐれた品質の電子機器をつくることになる。素材の特性を組み合わせて新しい機能をつくる、これがクリエーティブ・テクノロジー(創造的技術)で、いってみれば無から有を生ずる技術である。今あなた方がそれを決断しなければならない時だと思う」
実は、フィンランドの研究者たちはすでに決断していた。しかし、政府が動かなかったのである。そこで意見を同じくするからにはと、窪田氏に助太刀を依頼してきた。
「われわれも本当はそれを役所にPRしている。あなたは外国からこられた技術者だし、ぜひわれわれの希望を助力する発言をしてほしい」
窪田氏に否やがあろうはずがない。これこそ教育勅語にいう「一旦緩急あれば、義勇公に奉じ」の局面である。義勇を奉ずべき公とは、時に応じて必ずしも日本だけに限らないのが、公の公たる所以なのである。日本人たる窪田氏にとって、フィンランドのために尽くすこともまた、「義勇を公に奉じる」ことにほかならなかったのだ。
そこで早速にも、週末に新聞記者を呼んでインタビューを受け、日本人客員教授の意見として発表する段取りとなった。
先に新聞社の方から取材に来たときには、窪田氏が「日本の一市民だから」という理由で取材を断った経緯のあることを想い出してほしい。今度はこちらから依頼して、取材を受けようというのである。それは先と今度とでは、取材に応じる意味がまったく違うからなのである。一介の市民としては慎ましくあるべきであるが、公のためということであれば義勇を振るわなければならないと、窪田氏は考えたことだろう。
ともあれ、窪田規氏の話した内容が日刊紙「カレバ」の第一面で大きく報じられたのである。「フィンランドは電子部品を生産すべきである」という大きな見出しが付いた、その内容は、
「フィンランドにはシスー(フィンランド魂)があるではないか」
「日本人にも日本人の精神力があるように、フィンランドはそのシスーによって六百年もつづいたロシアの支配からぬけでて、今したかかにいきているではないか」
「材料革命こそわれわれの夢を達成する道である」
などというものだった。
今度の新聞取材に際しても、窪田氏はわざわざ個人の意見であると念を押したと言っているが、この話の内容たるや堂々たるもので、国家百年の計を指し示すものといってよい。しかも、それが数々の業績を上げてきた技術者の信念から迸りでたものだけに、いっそうの重みがあった。また、窪田氏の話した時期がフィンランドが今後の方針を決断する時でもあったのだろう。まさに時宜に適っていたのである。
その記事は大きな反響を巻き起こしたようである。窪田氏はフィンランドで「時の人」になった。自らも、次のように書いている。
「記事は好評をよんだ。三十億円もの年間予算をもつフィンランド・テクニカル・リサーチセンター(日本でいえば工業技術院の電総研にあたる)のエレクトロニクス部にもよばれて、『電子部品の未来』という講義もした」(同四三頁)
●結論からいえば、この窪田規氏の新聞記事がきっかけとなり、フィンランドは部品輸入・組み立て・製品輸出という「労働立国」から素材開発・部品生産・製品輸出という一貫した「技術立国」へと国家の舵を切り替えることになったのである。
ここにまことに不思議なことがある。窪田氏の記事が新聞の第一面に掲載されたその日、フィンランドでは何十人もの死傷者が出るという列車事故が起こっていたのだ。そして、その記事が第二面にまわされて、窪田氏へのインタビューが第一面に載ったのである。
これは窪田氏にも異様な処置だと思えたのだろう。その理由を考えて、フィンランドの技術を見る姿勢が高いからだとの結論に達している。
「技術者の発言がその国の代表紙の一面にのることは、まず日本ではありえない。国際情勢か政治家の話がのるだけである。しかし欧米では、技術者が国家や社会に及ぼす影響がきわめて大きいとみて、新聞の一面にもその意見をのせるのである。
フィンランドのカレバ紙の例も、単に自分の意見がアピールしただけではなく、彼らが技術をみる姿勢が高いから一面にのったと、私は考えている。何十人も死傷した列車事故を第二面に変更していた。日本では考えられないことである。ここにフィンランド人と日本人の技術や技術に対するものの見方や考え方の差があるように思えてならない」
それにしても、当の窪田氏自身の考えではあるが、フィンランドが技術者を評価する姿勢が高いからというだけでは説明できないものがあるように私には思える。
ふだんなら、窪田氏の考えがもっともだと納得もできる。だが、数十人の死傷者が出る列車事故となれば、先ごろ日本で起きたJR西日本福知山線脱線事故に匹敵ないしもっと大規模の悲惨な事故だと考えてよい。いかに技術を高く評価する国のこととはいえ、そのような大惨事の記事をわざわざ第二面にまわして、技術の将来について語る外国から来た客員教授の話を第一面に載せるというのは、やはり異様としか言いようがない。
大惨事の事故を報道する喫緊性に比べれば、国家百年の大計の話といえども、やはり胡乱の感は否めまい。それはいかに技術者を大切にするフィンランドでも変わりないのではないだろうか。実際にフィンランド人に聞いてみて、いやフィンランドではありうる話だと言われれば、黙って引き下がるしかないとは思うのだが……。
私としては、何かこの時に天意か神意のようなものがはたらいて、フィンランドでもふだんなら有りえないことだが、窪田氏の話がカレバ紙の第一面に掲載され、もともと第一面に載るはずだった列車事故の記事が第二面に変更されたのだと、思えてならないのだ。
●これが他の国であったらどうだったのかと改めて考えてみると、フィンランドにおける窪田氏の記事の取扱い方の異様さ不思議さが際立ってくる。まず有りえない事態だからである。
例えば、米国でもロシアでも日本人技術者の話を有力紙の第一面に載せることは決してあるまい。韓国でなら、いかにも重大に扱うように取材しておきながら、実際には小さく申訳程度に載せるのが落ちであろうし、支那あたりになると、満面の笑顔で熱烈取材しておいて、まったく載せないということを平然とやる。どうしたんだと聞くと、当局の意向でとか何とか誤魔化すに相違ない。
もろもろ考え合わせると、フィンランドはやはり日本にとって特別の国である。そして、日本にとって特別の国であるフィンランドに対して窪田規という人は特別の使命を帯びて客員教授に赴いたのだと言わざるをえない。しかもそれがフィンランドにとって特別の時であった。まさに天の時、地の利、人の縁が一致したのである。
この特別の関係を結ぶに至った深い理由はツランの同胞として関係を強化せよとの神意だと見るのは私の勝手であるが、そんな悠久の大義は別にしても、フィンランドとの関係をもっと密接なものにしていく必要があると私は考えるものである。
そもそも、まったく門外漢である私にK氏が窪田氏の著書のコピーを下さったこと自体が不思議であり、窪田氏とフィンランドとの特別の関係を知るに及んで偶然とはいえないある必然を感じるのである。(つづく)★