
 |
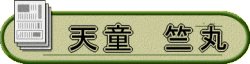
![]()
![]() ツラン魂は健在なり 2
ツラン魂は健在なり 2
(世界戦略情報「みち」平成18年(2666)4月15日第226号)
●ハンガリーのフン・マジャール協会という組織が開設した「ツランの土地と民族」なるウェブ・サイトの内容紹介ページを見ると、「ツランの歴史」という項目がある。
上段に「歴史上のツラン系帝国」と題した地図が掲げられ、下段に「ツラン民族の起源」という小見出しの小文が載っている。彼らが「ツラン民族」とは何であると考えているのか、その文章を見てみよう。
☆「ツラン民族の起源」
ツランとはカスピ海の東方地域を指す歴史的・地理学的な名称である。考古学的調査によって明らかにされてきたように、この地域にはシュメール(メソポタミヤ)を起源とする高度に発達した文明が広がっていた(S・P・トルストイ『古代ホラズミア』)。
シュメール人は既知の最初の文明の創造者であり、とりわけ農業も冶金も車輪も文字も、そして天文学もシュメール人の発明にかかるものなのである(S・N・クレイマー『歴史はシュメールに始まる』)。
一九世紀に古代メソポタミヤのシュメール語を発見し研究した学者たちは、シュメール語がツラン民族の言語と関連があるとの結論を下している(M・エルディ『シュメール語とウラル・アルタイ系マジャール語の関係』)。
比較言語学的分析の示唆するところでは、すべての民族言語グループの中でハンガリー語、トルコ語、コーカサス語とフィンランド語とがシュメール語に対して他に隔絶した近親性を有するとされている(K・ゴストニー『シュメール語語源・比較文法辞典』)。
このことは考古学的および人類学的な証拠によっても認められている。それによれば、シュメール人および関係する中近東の諸民族は今から数千年前に西はカルパチア盆地から東はアルタイ山脈まで、北はシベリアから南はイランおよびインドへといたる広大な中央ユーラシアの地域に移動定着したのであった(L・ゲッツ『東方に日は昇る』)。
そうしたシュメール系諸民族の子孫たちが、いわゆるスキタイ民族、サルマティア民族、メディア民族、パルティア民族、ホラズミア民族、クシャーン民族、フン族、アヴァール族、ブルガル族、カザール族、マジャール族などとして特に知られており、さらにフィンおよびトルコ・モンゴル系民族群の勃興をも促したのである。
これらのツラン系諸民族は繁栄する文化と国家を建設してヨーロッパや中東、ペルシア、インド、支那などのユーラシア周辺の文化に決定的な影響を及ぼすとともに、ユーラシア大陸のさまざまな民族・言語集団の形成にも大いに与って影響を及ぼした(「歴史年代記」参照)。
これによれば、「ツラン民族の再興」を願う現代のハンガリー人たちが「ツラン民族とはシュメール人の末裔である」と考えていることがはっきりと分かる。
上に挙げられている民族を見ても明らかなように、メソポタミヤを逐われてユーラシア中央の大平原へと移動定着したとされている「シュメール系諸民族の子孫」とは、つまり「遊牧騎馬民族」なのである。
●われわれが学んできた「世界史」によれば、シュメール文明をつくった人々が生きのびてスキタイ族やメディア族、パルティア族などになったのだという説は、異様に聞こえるであろう。
総じてわれわれは、さまざまな民族が興隆と滅亡を繰り返した歴史を学んだわけである。では、ある時に広域に支配を確立して国家・帝国を形成した人々が他の勢力の勃興により滅ぼされた場合に、雲散霧消して地上から姿を消してしまうのであろうか。
そんなことはあるまい。
多くの歴史の記述は新たに興隆した民族や国家へと視点を移していくために、滅ぼされた民族や国家は消えてなくなったかのような錯覚に陥っているだけである。国家組織などの支配体制は新興勢力のものに取って代わるであろうが、人間やその集団そのものが完全に消滅するわけではない。
確かに、ある民族がひとつの民族としてのまとまりと名称を失って、有力な民族の中に吸収されるという事態はありうる。
また、他の勢力に席巻されて一時的に歴史から消えたかに見えながら、再び勢力を盛り返して再登場するという場合もある。ただ、その場合に以前の名称や支配体制と異なっていれば、まったく異なる民族集団として記述されることになる。
よくよく考えてみるに、有史このかた首尾一貫した流れをもった歴史を有するとされているのは、いわゆる「印欧語族」と「ユダヤ民族」だけである。
一方は言語系統を同じくするとされる言語集団であり、片や一神教を奉じる信仰集団である。それを同じ「民族」という名称で呼んでいることは、血統的にも連綿として続いている「人種」なのだ、と錯覚しかねない。それは大いなる誤解である。
神話をもとにある民族が結束を固めることは大いに結構なことである。だが、その信仰を学問的真理だとして一般に押し付けるのは、また信仰を同じくする者がたちが起源も同じ「人種集団」だと主張することは、まったく次元の異なる問題である。
いわゆる「アーリア人=印欧語族」なるものも、学問的な成果というより、一五世紀より世界的植民地支配に乗り出した西欧の勢力、とくに英国の東インド会社を拠点にした寡頭勢力がその世界支配の理論的正統性を固めるために編み出した思想謀略(イデオロギー)なのである。
浅学ゆえに、こういう批判的視点で「印欧語族説」を論じた著作を私は知らなかったが、同志林廣さんの好意によって津田元一郎氏の著作を贈っていただいて蒙を開かれる思いがした。
●津田氏の著作の一つ『アーリアンとは何か』(人文書院、一九九五年、復刊二〇〇一年)にはこう書いてある。
マコーレー(Thomas Babington Macauley、一八〇〇~五九)は、「大衆を教育することは不可能だが、血と色とはインド人でも、趣味、考え方、道徳、知性においてイギリス人である人々を作り出すことはできる。そうすれば、教育はそれらの階級から大衆へと浸透してゆく」と語ったことで有名である。彼は、エリートに英語教育を施すことによって、彼らをイギリス化し、以て、エリートを大衆と分離分断する植民地教育体制を確立し、インド植民地支配に不朽の功績を残した植民地官僚である。彼はその功績によって、帰国後、貴族に列せられている。(同書一八頁)
さて、マコーレーは、インド教育を英語化するという歴史的使命を終えてイギリスに帰ると、ヴェーダの知識をもち、布教のためにうまい工作のできるようなサンスクリット学者をさがし始めた。H・H・ウィルソン(H.H.Wilson)とブンソン男爵の事務所を通じ、彼の意に沿う学者として、ドイツの著名なヴェーダ学者、マックス・ミュラー(Friedrich Max Müller)を知るようになった。
マックス・ミュラーの登場
マコーレーは、一八五四年一二月、マックス・ミュラーに会った。ときに、マコーレー五五歳、マックス・ミュラー三二歳であった。二人は長い間語り合い、マコーレーは、もし、ミュラーがヒンズー教徒の聖典であるリグ・ヴェーダを、ヒンズー教徒の信仰を混乱させ、打ち砕くような形で翻訳しうるならば、東インド会社は、一〇万ルピーの金を支出する用意がある旨を告げた。それを受けて、マックス・ミュラーはイギリスに渡り、オックスフォード大学のヴェーダ研究部の部長になり、一八五五年から一九〇〇年までの間、東洋学の名のもとに、所謂ヴェーダ研究を遂行することになった。(一九~二〇頁)
実に植民地支配の悪意を剥き出した露骨な申し出だったが、今日にいたるもヴェーダ学・東洋学の碩学として不朽の名声を恣にしているドイツ人のマックス・ミュラーは、この申し出に応じたのだった。してみれば、不朽の名声なるものも、英国東印度会社の意図に沿ったものだったわけである。
そして、もともと言語グループとして想定された「印欧語族」Indo-europian language groupを、「アーリア人」という一つの人種を思わせる言葉で置き換えるように提唱したのが、そのミュラーである。
一八五九年から六一年にかけて、マックス・ミュラーは、ロンドンの王立協会で講義をし、従来、「インド・ヨーロッパ」「インド・ゲルマン」といっていた言い方を、「アーリア」と言い換えるべきだと説いた。なぜならば、インドに侵入したサンスクリットを話す人々は、自らをアーリアと呼んでいたからだ、と説いた。先にも述べたように、一七八八年、カルカッタの最高裁に赴任したウィリアム・ジョーンズが、サンスクリットとギリシア語、ラテン語、ペルシア語、ケルト語、ゲルマン語などとが類似し、これらに共通の祖語を考えなければ説明がつかない、と主張しだしてから約七〇年後のことだった。
トーマス・ヤングは、この共通な祖語をもつ言語群の人々をインド・ヨーロッパ語族と名付けたが、その限りでは、言語の類似性の問題であり、人種や血の問題ではなかった。ところが、マックス・ミュラーになって、インド・ヨーロッパをアーリアと言い換えるべきだと言い出し、いささか様相が違って来、人種論に転化してしまった。
リグ・ヴェーダを研究し、そこに「アーリア」というひびきのよい呼称で呼ばれている集団があり、その集団が、原住民を征服して、古代インド文化を創造した、と解釈したマックス・ミュラーは、その「アーリア」こそヨーロッパ人、ペルシア人、インド人の共通した祖先である、と主張した。
晩年、彼は自説の謝りを認め、一八八八年、『アーリアンの言語と住地の伝記』(Biographies of Words and the Home of Aryans)の中で、「アーリア人種、アーリアンの血、アーリアンの髪について語る人類学者は、長頭人の辞書、短頭人の文法について語る言語学者と同様な罪人だと思う」と述べた。
言語の類似性を基礎とする言語学上の概念であるインド・ヨーロッパ語族を、人種的ひびきをもたせた「アーリアン」に言い換えたことは、言語と人種を混同することになることに、彼自身も気がついたらしい。
しかし、その時には、彼自身がアーリアン学説を説きだしてから、既に三〇年近い月日が流れていた。そればかりか、アーリアン学説は何よりも、一九世紀後半の世界制覇に向かうヨーロッパの時代的風潮に強く訴えるものがあり、既に、強固な学説として定着し、ひとり歩き出してしまっていた。それ以後は、ヒットラーによりナチス・ドイツにおいて、凶暴な人種論に仕立てられ猛威をふるうまで、次第にエスカレートしていった。そして、その原住地も、ヨーロッパ人の優越感を満足させるため、次第に西北ヨーロッパの方へとひきつけられていった。
(三五~三六頁、引用に際し一部改行)
言語学上の語族として想定された印欧語族が優越支配人種としての「アーリア人」へと転化する経緯はかくのごとしである。
その理論的根據は荒唐無稽であって、何もない。ヨーロッパ列強による世界制覇のための理論謀略だったことは明らかである。
語族というものは、われわれの実感としてもたしかに存在する。今日われわれは嫌でも英語を学ばなければならない不幸に見舞われているが、その英語たるや日本語とまったく発想そのものが異なり、大いに面食らうものがある。支那語もまた日本語とは似ても似つかない言葉である。われわれが呆れるように、向こうもまた大いに違和感を感じて日本語を学習して(しないか?)いることだろう。
今日相互に大きく異なる言語のグループとして、「膠着語」「孤立語」「屈折語」の三つが挙げられる。
「孤立語」とは他の言語と関係を有しない独りぼっちの言語という意味ではなく、文章の中で単語が何時も同じ形で孤立し(それ自身が語尾変化したり他の要素を付加しないでも)文法上のさまざまな意味をもつことを特徴とする言語集団の謂である。支那語やチベット語、タイ語などがこの言語グループに属する。
いわゆる「てにをは」をくっつけてやらなければ、文法上の意味が明確にならない言語が「膠着語」である。膠でくっつけるように小辞をつけて意味を明らかにする言語というほどの意味である。ツラン民族の言語の特徴はこの「膠着語」である。
「屈折語」とは、動詞も名詞も実際に文章の中で使われるときは、その文法上の意味(役割)によって語形を屈折(変化)させる言語集団である。津田氏の話に出てきた印欧語族は、この「屈折語」のグループに属する。
●言語学という学問そのものが、ヨーロッパ列強による植民地支配の必要から興ったものだと言っても過言ではない。支配の正統性を強弁するためである。したがって、印欧語族の研究は近代言語学の花形であった。
「ツラン」を考える場合、こうした近代言語学への反省が不可欠となる。なぜなら、もともと「アーリア」と対立する手強い異民族として「ツラン」は存在したにもかかわらず、歴史上の時々に興隆滅亡するバラバラの民族集団として描かれてきたために、そもそも「ツラン」なるものは歴史上存在しなかったかのように今日も思われているからである。
このバラバラに解体されてきた「ツラン」に歴史的な流れがあるという見通しをつけること、まずはそれがツラン問題の最大の課題であろう。
「ツランの土地と民族」というウェブ・サイトでも、こうした問題意識を充分に持ち合わせているようだ。シュメールにツランの起源を求めたのも、諾なるかなとの感がする。
だが、シュメール学自体が不確かな今日、シュメール人に自民族の起源を求めることができるかどうか、疑問といわざるをえない。
冒頭で述べたように、このウェブ・サイトには「ツランの歴史」という項がある。ツランの歴史をどのように説いているか、大いに興味をもって中を見てみると、先の小文の他に、その下位項目として、次のような内容が挙げられていた。
「ブルガリア史」最初のブルガリア人国家の建設
「ホラズム帝国」(地図)
「カザール帝国」(地図)
「クシャーン帝国」(地図)
「モンゴル史」
「トルコ史」古代トルコの神々
「ロシアによる一一~一九世紀の領土拡張──ツラン(ウラル・アルタイ)領の占領」
これでは、分断された歴史の、そのほんの一部を取り上げているだけで、とてもツランの歴史の流れをたどるなどと言える代物ではない。
しかも、(地図)とあるのは、「地図だけ」との断わりであって説明の文章がまったくない。ホーム・ページでオリジナルの地図一枚を作るのも大変なことは推察するに余りあるが、少々がっかりである。
さらに、(地図)だけではない項目も、他のサイトか文献へのリンクである。このサイト独自の内容は用意されていない。
では、「ツラン民族の起源」と題した小文の最後にある「歴史年代記」なるものはいったい何か、またまた興味津々で開いてみた。するとそれは、「ハンガリーの歴史」なのだった。
ハンガリーの人が運営しているサイトだから、「ツラン=ハンガリー」とするのも理解しないではないが、もう少し頑張って欲しいと思わざるをえない。先号の本稿冒頭で、内容が「かなり充実してきた」などと褒めたのだが、まだまだ途遠しの感がある。
だが、その「ハンガリーの歴史」の末尾には、「ハンガリー人の起源と原初史に関する論争」と題したかなり長い(A4判の紙に印刷したら典拠と文献リストを除いて一八頁になった)論文がある。
この論文はもと一九九六年ハンガリー建国一一〇〇周年の機会に、カナダのハンガリー研究協会において報告されたものだと序文に述べられているが、まずはじめに「八九六年のハンガリー建国から一一〇〇周年の機会に、厳密にはそもそも我々は何を祝うのか」と問いかける。
それはアルパド人の異端国家ハンガリーなのか、それともイシュトヴァン(ステファン)王のキリスト教国家ハンガリーなのか?
この難問については意見の分かれるところである。一般的には、現代のハンガリー史研究は優勢な西側の観点から過去一〇〇〇年のハンガリーの歴史により集中しているように思われる。そのために、ハンガリーの歴史は意図的に短く捉えられ、そのキリスト教以前の歴史的・文化的起源から切り離され、その起源は曲解もしくは黙殺されることになる。ハンガリーの歴史はより広範な、もっと均衡のとれた視点で再評価する必要がある。
相対立する主要な見解の一方には、紀元前にハンガリーの起源を求める伝統的な見解があり、こちらは一九世紀前半に始まった国際的な東洋学研究によって明らかにされたように、シュメール・ハンガリー関係の驚くべきほどの親和性を説く。
片や、より新しいフィン・ウゴール理論があるが、こちらは基本的にはハンガリーにおける外国支配体制の産物であった。すなわち一九世紀のハプスブルク朝と二〇世紀の共産主義である。
ハンガリー人の起源に関する伝統的な見解によれば、マジャール人とフン族とは同一の民族であって、その発祥は古代メソポタミアに遡る。シュメール・ハンガリー民族言語学の研究はこの見解を確証するように思われるのである。
フィン・ウゴール理論は一見科学的な言語学的方法論によってハンガリーの起源についての伝統的な見解とハンガリー・シュメール関係とを否定するのに躍起となってきたが、事実をもっと慎重に分析した結果、フィン・ウゴール派の方法論は非科学的であり、またフィン・ウゴール理論の提唱者たちの意図が政治的かつイデオロギー的であることも、曝露されたのである。
彼らの目的はハンガリー人の国民的抵抗を弱体化して外国による支配を強固ならしめるために、ハンガリー人に集団的劣等感を浸透させることにより国家のアイデンティティーを稀薄にすることであった。
現在ハンガリーにおける歴史研究の「主流」はフィン・ウゴール理論へと頑なに傾斜して、ハンガリー人は高度に文明化したヨーロッパに「遅れてやって来たアジアの原始的侵略者」だったという考えを喧伝している。
したがって、この公式の歴史解釈は、ハンガリー人の古代ツラン民族起源やシュメールスキタイフンアヴァールマジャールの同一性と持続性、さらには紀元一〇〇〇年以前の千年間にハンガリー民族が成し遂げた文化的・政治的・軍事的業績などを、無視もしくは黙殺することを特徴とする。まさにそれこそがハンガリーという国家の基礎を築いたにもかかわらず……。
こうした文章を読むと、ハンガリー人の魂から迸り出たような叫びが胸に響く。言語学上のフィン・ウゴール理論がハンガリーにおいてはこのような政治的イデオロギー的意図をもっていたとは、想像だにできなかった。しかも、そのフィン・ウゴール理論が現代のハンガリーでは主流であり、公式の歴史的な見解となっているという。「ツラン民族説」はハンガリーでも少数派なのである。
●しかしながら、このウェブ・サイトの作者は少数派であるとは百も承知で「ツラン民族説」に夢を託すのである。その信念の根據が多くを「ハンガリー・シュメール関係」、つまりハンガリー人とシュメール人の親近性にあることが、同文書の第三部「シュメール問題」において明らかになる。
一九世紀の前半に英仏独の考古学者や言語学者たちはメソポタミヤおよびその周辺地域において世界最古の記録文書を発見、解読した結果、これら古代の刻文に用いられた言語が印欧語でもセム語でもなく、一つの膠着語であるとの結論に達した。そして、その言語は当時ツラン民族言語族として知られていた膠着語族と有意の親近性を示したのであった。ツラン民族言語族にはハンガリー語やトルコ語、モンゴル語、フィン語などが含まれる。後にウラル・アルタイ語族といわれる語族である。
シュメールとツランの間に民族言語的関係のあることを認める傾向は国際的な東洋学者たちの間に一八七〇年代まではますます顕著であった。ところが、二つの要因がこの分野における研究のさらなる進展をぶち壊すことになる。
第一には、ハンガリーでは一八四八年から四九年にかけての独立戦争以後に、フィン・ウゴール理論が押し付けられた結果として、シュメール問題に関するあらゆる研究が奨励されなくなり、この公式の態度はハンガリーでは今日でも優勢となっている。
第二の要因は国際的なレベルで甚大な衝撃を与えたものであるが、「かつてシュメール人なるものは存在したこともなく、その言語というのもバビロニアのセム系神官が秘密通信のために発明したにすぎない」という説が流布されたことである。
この説をデッチあげた人物はブカレスト出身でソルボンヌ大学に教授の地位を得ていたJ・ハレヴィというラビ(ユダヤ教僧職者)だった。この途方もない妄説がその数多くの欠陥と、見え見えのイデオロギー的意図にもかかわらず、東洋学者の間に不和を招く効果をもたらし、それまでにせっかくシュメール・ツラン関係の提唱者が得ていた弾みを台無しにしてしまったのだった。
それ以後、シュメール問題は少数派の地位に貶められ黙殺されてきたのである。おかげでシュメール語は近代の民族言語族と何らの親近性をもたない起源不詳の孤立した(独りぼっちのという意味──念のため)民族言語族として一般的には忘れ去られてしまったのだった。
何と! 今日のシュメール語の系統不詳説はここに発端があったとは。いったん膠着語言語族との親近性を指摘されながら、それがユダヤ人によって意図的に破壊されたのである。米軍による今次のイラク侵攻において、まっさきにバグダット博物館が吸収されて、その人類共通の財産であるシュメールの秘宝が略奪されたことを考え合わせると、ユダヤ人がシュメール問題にいかに神経過敏であるか見当がつこうというものだ。 (つづく)★