
 |
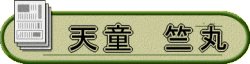
![]()
![]() ツラン魂は健在なり 3
ツラン魂は健在なり 3
(世界戦略情報「みち」平成18年(2666)5月1日第227号)
●「かつてシュメール人なるものは存在したこともなく、その言語というのもバビロニアのセム系神官が秘密通信のために発明したにすぎない」とは驚くべき妄説であって、今日では誰も顧みる者はあるまい。厖大な楔形文書をはじめとする考古学的発見によって、紛れもなくシュメール人もシュメール文明も歴史上に確かに存在していたことが次第に明らかになってきたからである。
しかし、まだシュメール学が生まれたてのころには、この妄説によって東洋学研究者の間に動揺を招いたのだという。なかんずく、シュメール語が「膠着語」であることを端緒としてツラン民族の起源をシュメール文明に求めようとしていたハンガリーの東洋学研究者たちの主張をも打ち砕く効果をもたらしたのであった。
だが、それでもハンガリーの東洋学研究者たちは挫けることなく研究を続けて、第二次世界大戦後にその成果を発表することになる。その経緯は後に述べるとして、いまは噴飯の極みというべきこの妄説を公表し学会を攪乱したJ・ハレヴィとは一体何者だったのかを追求してみたい。
「ハンガリー人の起源と原初史に関する論争」の文中には典拠を明示する註が数多く付加されているが、「シュメール人もシュメール語も存在しなかった」という箇所にも典拠を参照するための番号(30)が付いている。
そこで文末の「典拠一覧」を見てみると、件の文章はニューヨークのギルガメシュ社から一九七四年に出たエルディ・ミクロシュの著書の一七〇頁に依拠していることが分かる。さて、問題はその著書であるが、その標題は「A Sumír, Ural-Altaji, Magyar rokonság kutatásának története」とあり、ハンガリー語(たぶん)の表記であるために正確な書名が分からない。
ひょっとすると、すでに本誌先号で引用した「ツラン民族の起源」なる一文の中に登場したM・エルディとここで典拠とされているエルディ・ミクロシュとが同一人物であるという可能性もある。日本と同じくハンガリーでも人名を「姓─名」の順で表記するのが通常であるが、英語表記に際し人名ミクロシュを「M.」と略してエルディという姓の前に置いたとも考えられるからである。
その場合には、その著書は『シュメール語とウラル・アルタイ系マジャール語との関係』(こちらは英語で表記されている)という本と同一ではないかと思われるのだが、若干の疑問が残ることも念押ししておきたい。
いずれにせよ、「シュメール人もシュメール語も存在しない」との妄説を発表して学会に害毒を振りまいたユダヤ教ラビがいたことを記しているのは、おそらくはアルタイ語学者であったハンガリー人エルディ・ミクロシュの、「シュメール語とウラル・アルタイ語系のマジャール語との関係を扱った著書」であることは間違いなかろう。
そのJ・ハレヴィというユダヤ教のラビは「ブカレスト出身でソルボンヌ大学で教授」をしていたと紹介されている。果たしてこれだけで分かるかどうか心許なく思いつつも、『ブリタニカ』を検索してみた。案の定というか当然というか、該当する人物は見あたらない。そこでユダヤ百科事典『ジュダイカ』(CD版)も念のために引いてみた。
「Halevy」で検索すると、いくつかの人名が候補リストに出てくる。ひとつ一つ当たってみると、それは画家や音楽家のハレヴィさんのことだった。そのほかに「ハレヴィ」とは「ハレヴィ」であって「レビ族の」という意味なのだという余計なことなど目について、「シュメール学者」ないし「東洋学者」と思しきハレヴィさんは、なかなか容易には姿を見せてくれない。
●ほとんど諦めかけていたとき、「これだ」という人物を見つけた。
まず最初に「ハレヴィ、ヨセフ(一八二七~一九一七)、フランスの東洋学者にしてヘブライ語作家」とある。年代的にも一致するので、この人物だろうと見当を付けて、説明文を読んでいくと、「ハレヴィはシュメール語が非セム系言語だという見解に反対して執拗に議論を行なった」と書かれている。事ここにいたって、件のJ・ハレヴィとはこの人物に間違いないことを確信した。
以下、ユダヤ百科事典の記述に拠って、この人物を紹介してみたい。
「ハレヴィ、ヨセフ」
ハレヴィ、ヨセフ(一八二七~一九一七)、フランスの東洋学者にしてヘブライ語作家。ハレヴィの経歴は彼の誕生の地であるトルコのアドリアノープルでヘブライ語教師として始まり、その後はルーマニアのブカレストでも教師をした。
先の一文では、「ブカレスト出身」と紹介されていたが、彼にはさらにその前があったのだ。トルコの「アドリアノープル」の生まれだという。この町は現在エディルネと呼ばれているところで、ギリシアとの国境に近い、トルコでもっとも西北に位置する都市である。
オスマン・トルコがコンスタンチノープルを陥落させて同地に首都を移転させるまで、短期間ではあったがエディルネがオスマン・トルコ帝国の首都だった時期もある。
そこの生まれだというから、もともとこの地に続いていたユダヤ人の家系なのか、それとも「棄教か追放か」と迫られイベリア半島を逃れて渡ってきて住み着いた家系なのか。とまれ、寛容なトルコの宗教政策が半島から逃げのびてきた多くのユダヤ人を迎え入れたことは確かな歴史的事実である。
ハレヴィはその後ルーマニアのブカレストに転じている。だから、「ブカレスト出身」とされたものであろう。
一八六八年、彼は万国イスラエル連盟の後援の下にファラシャ族研究のためエチオピアを訪問する。その報告書(未公刊)は忘れられていたこの部族が紛れもなくユダヤ人だと主張したため、彼らを救えという広範な慈善運動が巻き起こった。
一八六八年といえば、ハレヴィが四一歳になった年であるが、『ジュダイカ』の別の項目「ベータ・イスラエル族(ファラシャ族)」によれば、ハレヴィがエチオピアへ旅行したのは前年一八六七年のことになっている。そこに引用されたハレヴィの万国イスラエル連盟中央委員会宛の報告書が同連盟の一八六八年版『報告書集』に所収とされている点を考慮に入れると、旅行そのものは一八六七年のことだったかも知れない。
ヨセフ・ハレヴィのエチオピア旅行の後援をした「万国イスラエル連盟」とはユダヤ人の世界的な連絡組織として一八六〇年にパリで結成された、この種の組織の嚆矢となった機関である。ウォルター・ラカーによる浩瀚な『ユダヤ人とシオニズムの歴史』(高坂誠・訳、第三書館、一九八七年)によれば、皮肉を込めて、
反セム主義的な民話によると、一八六〇年にパリで創設された「万国イスラエル連盟」(Alliance Israéllite Universelle)は、秘密のユダヤ人世界政府であった。しかし実際には、その主要な仕事は、モロッコやバルカン諸国での学校建設だったのである。(四六頁)
と説明されている
いずれにしても、世界のユダヤ人に対して、エチオピアの地でユダヤ教の儀式を守りつづけている「ファラシャ族」がユダヤ人同胞であると声高に知らせたのがヨセフ・ハレヴィであることに変りはない。
ファラシャ族がユダヤ人同胞だと肯定した最初の人物は一六世紀のダヴィデ・イブン・ツィムラというラビだとされている。彼は、ファラシャ族をイスラエル十二支族のダン族の末裔と見なして、同族だと認めたのだった。
ハレヴィはファラシャ族の問題を専門的に扱うよう弟子のジャック・フェトロヴィッチ教授に薦めて、そのフェトロヴィッチ教授が精力的に運動した結果としてファラシャ族のユダヤ人であることが公的に認められることになってゆく。
同時にイスラエル建国後にはファラシャ族を政情不安定なエチオピアからイスラエルへ「帰還」させることが、歴代の政権にとって大きな政治的課題となった。
中でも世界的に有名となったのは一九九〇年五月二四日から二五日にかけて行なわれた「ソロモン作戦」と呼ばれる一大空輸作戦であろう。このとき、「エチオピア系ユダヤ人」が一万四〇〇〇人以上も一時にイスラエルへと運ばれたことは、まだ記憶にある人もいるかもしれない。
こうした「帰還作戦」の結果、五万人以上の「ベータ・イスラエル族」がエチオピアからイスラエルへと「帰還」を果たしたとされている。
ただし、ユダヤ教を信奉しないキリスト教徒ファラシャ族がまだ二五万人から三〇万人ほどエチオピアに残っていると『ジュダイカ』も認めているので、ユダヤ教徒のファラシャ族は全体の六分の一から七分の一という少数派だったことが分かる。
ちなみに、「ファラシャ族」とは、他からの蔑称であって、彼らはみずからを「ベータ・イスラエル族」と呼ぶ。『ジュダイカ』もそう呼んでおり、括弧付きで「ファラシャ」と添えている。
たしか、一世を風靡したかの感がある佞書グラハム・ハンコック『神々の指紋』の中にも、「失われた聖櫃」と「モーゼの律法板」を伝えているのではないかと期待されて、この「黒いユダヤ人」が登場し、そして結局は期待外れに終わったように記憶するが……。
●余談に流れたので、急いで話をハレヴィにもどすことにしよう。ハレヴィがファラシャ族の言語や文献(エチオピアの古言語であるゲーズ語で記されたモーセ五書など)、そして習慣や習俗を研究したことを「学術的成果」だとして注目した者がある。フランス学士院の「碑文学会」である。
この学術団体がヨセフ・ハレヴィに新たな調査を依頼してきたのだ。それはソロモン王と結婚して一児を為したのちに故国へ帰ったとユダヤ伝承で伝えられた「シバの女王」の国の碑文を探して欲しいというものだった。「シバの女王」の国はアラビア半島の南部にあったと考えられていたのだ。それは今日のイエメンのあたりであるらしい。
ハレヴィが「シバの女王の国」で碑文を探した旅は、そのガイド役を務めたイエメン系ユダヤ人のハイム・ハブシュシュがアラビア語で手記にまとめていたものが、英語による要約を付し『イエメンの旅』(一九四一年刊)として公刊されたので、広く知られることになった。ハレヴィは身の安全のために学者としてではなく、貧者への喜捨を集めてまわるエルサレム在住のラビの姿に身をやつしたというのだが、どうして学者の姿が危険だったのか、いまいちピンとこない。
この調査旅行は大成功だったといえよう。というのも、ハレヴィは六八六ものシバ語の碑文(一部はシバ語の姉妹語であるミネア語で記されたものだったが)を発見したからである。
その研究成果を「シバ語研究」と題して、ハレヴィは『アジア学報』の一八七三年版と一八七四年版に二回にわたり発表した。また、調査旅行に関する二つの報告書も執筆した。「イエメン考古学調査報告書」(一八七二年)と「ナジランへの旅」(一八七三年)である。
それらの調査研究は単に「シバ語とシバ文化」の研究として高く評価されたばかりでなく、「聖書の研究」にも資するとして評価されたのだった。
●そうした評価のおかげで一八七九年には、パリ高等専門学校でエチオピア語を担当する教授としてハレヴィは迎えられることになる。ブカレストのヘブライ語教師がパリの一流学校の外国語教師となったのだから、大した出世というべきであろう。
そればかりではない。ヨセフ・ハレヴィは同時にフランス「アジア協会」の司書として雇われたのである。「司書」とはいうものの、それは一人前の「東洋学者」と認められたことを意味したのだと私は解したい。
ユダヤ百科事典の説明を引用しよう。
一八九三年には、ハレヴィは一つの学会誌を創刊している。『セム語古代史碑文研究報』である。この学会誌にハラヴィも自らセム語碑文および「聖書研究」に関する多数の論文を発表したが、そのうちの「聖書」に関する論考をまとめたものが『聖書研究』(一八九五~一九一四、五巻)である。これは「創世記」の前半二五章(全部で五〇章ある)についてバビロニア語・アッシリア語による新発見を採り入れて解釈したものであって、いわゆる「グラーフ・ウェルハウゼン資料仮説」(※)に激しく反対する内容となっている。(括弧は天童)
※「グラーフ・ウェルハウゼン資料仮説」とは、ユダヤ教聖典の「モーセ五書」ないし「ヨシュア記」を含めた「モーセ六書」が、神のモーセに与えた内容をそのまま記したものではなく、成立の時期を異にする三つもしくは四つの資料から取捨選択して編纂されたとする仮説である。それらの主要な資料としては、「ヤハウェ資料」「祭司資料」「エロヒム資料」「申命記資料」などが挙げられる。
ユリウス・ウェルハウゼン(一八四四~一九一八)の『イスラエル史序説』(一八八三年)によって確定的となり、今日に至ってなお学界の通説と言い得る、と関根正雄訳『旧約聖書創世記』(岩波文庫、一九五六年)の「解説」にもある。関根正雄はまた「そこには限られたいくつかの成立の段階があると見るべきである。その成立の事情を明らかにしたことは近代の旧約学の成し遂げた輝かしい業績の一つである」と評価するのだが、ハレヴィはこうした非ユダヤ人による「資料仮説」をてんから認めないものと見える。
「モーセ五書」について「資料仮説」を確立したとされるドイツ人のウェルハウゼンは、年齢的にはハレヴィより一七歳年下であって、「この若造が」という敵愾心もハレヴィにはあったのかもしれない。
ここで特に注目したいのは、「バビロニア語・アッシリア語による新発見を採り入れて」と赤字にしておいた部分である。そうだとすれば、すでにハレヴィはここにバビロニア語と書かれているアッカド語(たぶん)やアッシリア語に通じていたのだということになる。そこからシュメール語への距離は、古代メソポタミヤ諸言語の専門家をもって任じる当人の自負からすれば、ほんの一歩か半歩くらいに思えたのだろう。実際には、それらの古代言語とシュメール語とはまったく系統を異にする非セム系の言語だったのではあるが……。
ハレヴィは「聖書」に関する論考を自らが創刊した『セム語古代史碑文研究報』誌上ばかりでなく、『ユダヤ研究報』や『宗教史報』『批評報』にも盛んに発表した。
さて、いよいよ問題の「シュメール語およびシュメール文化の存在を否定した」に相当するユダヤ百科事典からの下りを紹介することにしよう。
自分自身がセム人(ユダヤ人)であり、かつまたセム語の専門家であるという自負にも促され、ハレヴィは「シュメール語は非セム系の言語であり、シュメール文化と楔形文書はセム系の後継言語に先行するものである」とする学説に頑なに異を唱えた。
ハレヴィが今日では通説となっているこの学説に猛反対したのは、シュメール語が一個の(独立した)言語ではなく、アッシリア・バビロニア時代の神官たちが彼ら自身の目的のために発明した神聖な人工的文字だったと信じこんでいたからである。
この問題に関するハレヴィの著作の一つが『シュメール主義とバビロニア史』(一九〇〇年)である。
フランス在住のユダヤ人の間では同化主義(ヘブライ語やユダヤ文化に固執せず在住地、この場合はフランスの言語や文化に同化する考え)の傾向が強かったのだが、それと対照的にハレヴィは熱烈なヘブライ語復帰論者で、さらには「シオンを愛する者」(Hovev Zion、シオニズムの先駆思想としてパレスティナ帰還を主張した思想の共鳴者)でもあったのだ。
若いころハレヴィは『巡歴者』(Ha Maggid)『レバノン』『エルサレム』などの(そのころ相次いで創刊された)ヘブライ語定期刊行物に散文や詩を欠かさずに送る寄稿者だったのである。後には、そうした作品が『Mahberet Melizah va-Shir』(いまだ邦訳できません)と題する本にまとめられている。彼の詩の題名に付けられた「父祖の地」「ヨルダン川のほとりにて」「わが夢」などの言葉は、「イスラエルの地」(Erez Israel)への強い執着を示すものである。(一部の原語表記を除いて括弧は天童)
「ハンス・ヤコブ・ポロツキー」という署名が文末にあるこのユダヤ百科事典の記事は、シュメールの言語も文化も存在しないと否定したハレヴィの誤りを誤りとは認めながらも、ハレヴィが熱心なヘブライ語復帰論者でありパレスティナ帰還論者であったというゆえをもって、大目に見ようとするかのような論調に貫かれている。ただ、誤りをはっきりと認めている点は評価できる。
●ここで私が特に注目したいのは、ヨセフ・ハレヴィにあの極論を唱えさせるに至った、その熱情の拠って来たる淵源についてである。
ユダヤ人はパレスティナを神がユダヤ人に与え給うた「シオンの地」であると頑なに信じている。そしてその「シオンの地」の範囲が「創世記」の一節に「ナイルからユフラテまで」とはっきり謳われていることを根據に、「拡大イスラエル主義」という侵略主義が成立する。
それは、そこで数千年にわたって繰り広げられた歴史的経緯も、現にそこに住む人々の存在をも均なみに無視する思想なのであって、信仰における伝承を現在の国家政策にそのまま生かそうとする暴論であり、危険極まりない狂信である。
ヨセフ・ハレヴィによる「シュメール語とシュメール文明の否定」は、この狂信が人類の初期文明におよんだ場合、熱心なユダヤ教信者ならどう考えるか、それを端的に示してくれる格好な例だと見るべきである。
天地創造をも行なった彼らの神が、彼ら自身の言語であるヘブライ語より先立つ言語を創造するはずがない、という狂信がそこにはある。まして、ヘブライ語と系統を異にする非セム系の先行言語の存在など彼らにとっては断じて認められないのである。
ヨセフ・ハレヴィは熱心なユダヤ主義者であったがゆえに、それだからこそ東洋学者として決定的な誤謬を犯したのだと言わなければならない。
ヨセフ・ハレヴィは過ちを犯したかも知れないが、一方で彼はユダヤの大義の熱心な信奉者だったのだから、多少の過ちは許すべきであるという口吻がユダヤ百科事典の記事には窺われるが、こうした論理はまったく成立しないのである。ユダヤの大義に熱心であったがゆえにこそ、ハレヴィは過ちを犯したのだから。
なかなかそこまでは、ユダヤ人として認められないことは充分に理解できる。しかし、あの「虐殺者」と囁かれたアリエル・シャロンでさえ、パレスティナ人との共生を決意してガザからの撤退に踏み切ったことに鑑みれば、事が人類文明の初期の問題においても、彼らの信仰と学問とを何とか分別し、良心的かつ正直な態度で研究するよう祈るばかりである。
このような狂信がさらに激しく嵩じれば、正直かつ良心的な東洋学者たちがシュメール語とシュメール文化の非セム的独自性を認めるのを防ぐためには、どんなことだって許されるという論理が出てこよう。それは人類共通の財産であるべき考古学資料の隠匿や破壊にまでおよぶこともありうる。
今次のイラク侵攻に際して、バグダッド博物館の考古学的秘宝がどこかへ持ち去られたままになっている事態の背景に、こうした狂信が存在しているのではないかと、私は気になって仕方がない。
●現代の政治問題として、イスラエルによる「拡大イスラエル主義」を警戒し、研究し、警鐘を鳴らす論者は数多い。もちろんそれは該当地域に住む人々にとって、現在ただいまの生存そのものに関わる喫緊の問題である。
だが、一見胡乱に思われるかも知れないが、「文化的拡大イスラエル主義」もまた同じように危険である。
メソポタミヤやエジプトの人類初期文明史をユダヤの大義に忠実に歪曲しようとする例はその後も跡を絶たない。一通り検証した感想からすれば、邦訳もあるゼカリア・シッチンの一連の古代文明に関する論考も、こうしたユダヤの大義に忠実な狂信に駆られた暴論・佞書の類ではないかと私は疑っている。
シッチンによれば、エジプト文明もシュメール文明も地球外からやって来た高度な知的生物の所産であり、ユダヤ人はその高度知的生命体の遺伝子と猿の遺伝子の結合手術から生まれた最初の人類だという。
こうした人類初期文明史に関するユダヤ人の狂信を、「文化的拡大イスラエル主義」と命名したいと私は思うのだが、それはこの狂信がもたらす害毒の激甚さと広範さ、そして後々までも残る時間的執拗さとを恐れるがゆえである。
そういう警戒の意味で、ヨセフ・ハレヴィがシュメール語とシュメール文明とを否定した『シュメール主義とバビロニア史』をぜひとも入手して読んでおきたいものだと願っている。
ここまでくると、ユダヤ人たちがなにゆえに「ツラン」に対して神経過敏なまでの反応を示すのか、その背景まで納得できるのではないだろうか。
それは、ユダヤ人の信仰の中に潜んでいる、「文化的拡大イスラエル主義」ともいうべき狂信から来る反応なのである。
伝承によれば、モーセの率いるイスラエルの民がエジプトを脱出し砂漠を放浪した後にカナンの地に辿りついたのは紀元前一四〇〇年のころとされている。シュメール文明はそれに二〇〇〇年も先立つ可能性がある。そもそもユダヤ人の最初の父祖とされるアブラム自身がシュメールの都市国家ウル(「創世記」では、カルデアのウル)の出身だと記されているではないか。
にもかかわらず、非セム系先行文明の存在を彼らは許せないのである。もし、古代文明が存在するとしたら、それはユダヤ人の系統的な先祖たるセム系であるはずで、また絶対にそうでなくてはならないのだ。(つづく)★