
 |
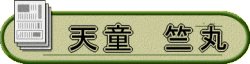
![]()
![]() ツラン魂は健在なり 4
ツラン魂は健在なり 4
(世界戦略情報「みち」平成18年(2666)5月15日第228号)
●ユダヤ人のヨセフ・ハレヴィが頑強に「シュメール語は一個の(独立した)言語ではなく、アッシリア・バビロニア時代の神官たちが彼ら自身の目的のために発明した神聖な人工的文字だった」と主張したにもかかわらず、その後のシュメール学会の大勢はハレヴィの暴論を完全に否定する方向へと進んできた。
本稿で取り上げてきたハンガリーのツラン問題のウェブ・サイトにおいても、「ハンガリー人の起源と原初史に関する論争」という文書の参考文献の一つとなっているのがシュメール学の世界的な権威だったサミュエル・ノア・クレイマー(一八九七~一九九〇)の著書『シュメール人 ── その歴史と文化および特徴』(シカゴ大学出版局、一九六三年)である。クレイマーはウクライナで生まれたユダヤ人で、ロシア皇帝ニコライ二世のポグロム(ユダヤ人迫害)から逃れるため故郷を離れた家族に連れられて一九〇五年に米国の東海岸フィラデルフィアへとやって来た。クレイマーのシュメール研究の集大成の一つが『シュメール人』である。
この著書の中でクレイマーは巻末の付録Aでシュメール語楔形文字の書法体系を、そして付録Bでシュメール語そのものを論じている。
付録Aでは、楔形文字が人類最古の文字であり、それがシュメール人たちに発祥することを認めている。
「A・楔形書法体系の起源と発展」
おそらく楔形文字の書法体系を初めて使ったのはシュメール人であった。これまでに発掘された最古の印刻文字 ── 一〇〇〇点以上におよぶ紀元前三〇〇〇年ごろの粘土板とその破片とは、あらゆる可能性を検討してみても、その使用言語はシュメール語である。この文字を発明したのがシュメール人であっても、あるいはそうでなくても、楔形文字というものを、書き記すのに打ってつけの道具の域にまで、紀元前三千年紀に仕上げたのがシュメール人であったことは、ほぼ間違いない。
この文字を使ってみると実際に便利であることから、次第に周辺の諸民族にもその価値が知られるようになり、シュメール人から借用してそれぞれの言語に用いるようになったのだった。こうして楔形文字は、紀元前二千年紀までには、中東の全域に広まったのである。
楔形文字は絵文字として始まった。それぞれの記号は一つ、ないし複数の具体的な対象物の似姿であって、その象られた対象物それ自体を意味する言葉もしくはそれと密接に関連するものを意味する言葉を表わしていた。
この種の書法体系には二つの欠点がある。対象物を表現するために必要な記号の形がどんどん複雑になっていくこと、そして夥しい数の記号が必要になること、この二つである。そのため手に負えなくなって、とても実用には向かなくなるのである。
シュメールの書記たちは次第に記号の形を単純化および様式化することによって第一の難点を克服したのだが、その結果として、ついにはその絵文字の原型が何であったのかが分からないまでに至ってしまった。
では、第二の難点についてはどうであったか。シュメール人書記は様々の便利な工夫を用いることで記号の数を減らして、一定の数の限度を超えないようにしたのである。
そうした工夫の中でもっとも重要なものが、「形」で表わす代わりに「音」で表わすという工夫だった。(同書三〇二頁)
本稿はシュメール語のイロハを解説することが目的ではないので、詳細に立ち入ることはできるだけ避けたいと願うのではあるが、「人類最初の文字である楔形文字における画期的な工夫の中でも最も重要なもの」と言われると、ではそれはいったい何であるのか気にされる向きも必ずやいらっしゃると思いめぐらせて、序でに書いておくことにする。

上図はクレイマーの著書の巻末に「図6、楔形文字の原型と発展形」と題して掲げられた代表的な楔形文字の例一八個の、紀元前三〇〇〇年から紀元前六〇〇年までの変遷を示した表の後半部分で、ここに九つの代表的文字が挙げてある。
「画期的な工夫」の例として説明されているのが、第二段目(元の図6で第十一番目)の二本の波線で表わされた文字である。
この文字についてクレイマーはこう説明している。
第十一番目の文字は川の流れの象形である。この文字は単語「水」(a)を表わす[意味が「水」で、その発音が「a=あ」であるということ]。
この文字はわれわれに、シュメール文字がその扱いづらい象形文字としての性格を失って次第に表音文字の体系へとどのように変遷していったのか、その過程の格好な具体例を提供してくれる。
この第十一番目の文字で表わされるシュメール語の単語「a」は、本来は「水」を示すのに用いられたのだが、同時に英語の「in」[~の中に、~で]の意味をも持っていた。英語の「in」は物と物との[位置]関係を示す単語であり、こうした概念を象形文字によって表わすことは困難である。
そこで、シュメール文字の創作者は独創的な名案を思いついたのだった。すなわち、「~の中に」という意味の単語を表わす象形文字を発明しようと悪戦苦闘する代わりに、「水」を示す単語を使えばいいじゃないか、と思いついたのである。というのも、「水」という言葉と「~の中に」という言葉の発音は、まったく同じだったからである。
つまり、初期のシュメール人書記が洞察するに至った名案とは、こういうことだった。ある特定の言葉に使われている文字を、まったく意味の異なる他の言葉にも、もし二つの言葉の発音が同一であるなら、使うことができる、ということだ。
この手口が次第に広まるにつれて、シュメール文字はその象形文字としての特徴を失って、純粋な表音文字へと成り変わる傾向をますます強めていったのである。([]は天童、三〇三頁)
図で示されているような、文字の形の五段階の変遷が問題にされているのではないのである。形では表わしえない、つまり、この図では表現できない画期的な発明がシュメール楔形文字に起こったというのだ。それが赤字部分で要約されている。
●いま手許にその本がないので、記憶を頼りに言うので心許ないが、漢字の起源である甲骨文字の発生に関して、白川静氏が「甲骨文字は一挙に生まれたのだ」という意味のことを書いておられたように思う。
それは人面魚の文様が描かれている彩陶土器が新たに発見されたニュースのコメントを求められての発言だったように記憶するが間違いかも知れない。ただそこで、「文字は一挙に発生する」と発言された内容は他のところでも書かれているので、白川静氏の独創的見解であることに間違いない。
つまり、どんなに文字に似た文様が古い時代に発見されても、それは文字とは見なされないということだ。文字であるためには、相当数の基本的な言葉を表示しうるような体系(セツト)を備えていなければならないのである。
言葉は文字がなくても、永い時間に熟して一つの言語体系として成り立つものである。それが文字に発現するかどうかは、特殊な事情に左右されるのであって、必ずしも言葉の発展の自然過程として起きることではない。
端的な例が、漢字=甲骨文字の発生である。「甲骨文字は神に対する恫喝として発生した」という意味のことを、白川静氏は言っている。商王朝の宮廷占人集団だった「貞人」たちが自らの占断の結果の正しさを永遠に刻印して神への見せしめとするために甲骨文字は発生したというのである。
それは実に驚くべき見解であるが、亀甲(稀に獣骨)に刻印された占断例のほとんどが占断とその結果とを併記していることから導きだされた考えだった。たとえば、「某月某日に雨が降るか否か」と占断した例が記されると、ほとんどの場合にその脇に「果して実際に某月某日に雨が降った」と記される。単に刻印されるばかりではない。刻印された文字は、さらに、その刻線に朱を注がれて聖別される。文字そのものが聖化されるのである。なにゆえにわざわざ朱添までして文字を聖化する必要があるのか。
先ほどの降雨の例でいえば、まず、雨が降るということは今日のわれわれが考えるような自然現象ではないということが前提としてある。
雨を降らせることは神の行為なのである。ただ、それを神が自らの意志で行なうのか、それとも貞人たちの占断の結果に神が従うから雨を降らせるのか、それが問題なのである。
かつて支那大陸の黄河流域は象が棲むほどに温暖で湿潤であったという。それが次第に乾燥気候へと変化するにつれて、そこに住む人々の生存が脅かされるにいたる。
伝説の聖王である堯も舜も、黄河の治水に粉骨した功によって帝位に就いたとされているが、そもそも雨が降らなければ、治水も何もあったものではない。雨が降るかどうか、否、雨を降らせるよう神に命じられるかどうか、それは王朝の正統性に関わる大問題であったといえよう。
神と人との、この緊張を孕んだ対決に勝利した凱歌こそが、甲骨文字なのであった。雨が降るかどうかと「貞(と)う」ことは、雨を降らせよと神を恫喝し、神に命ずるのに等しいのだ。白川氏はもっと別の言葉で書いていたかも知れないが、それはほとんど神への恫喝である。そう私は記憶した。
したがって、「雨が降るかどうか」と貞うて、「実際は雨が降らなかった」と記す例は、ありえない。それは貞人の占断行為自体を否定することになり、ひいては商王朝の統治の正統性の自己否定にも繋がるからである。
商の後継王朝の周は、孔子が文公を「西方の人」として尊崇したことからも分かるように、西方起源つまり西戎から興った王朝である。それに対して、商(殷)王朝はもと東夷から興ったと言われる。
神を恫喝するとは、まことに凄まじいばかりの、神への人の挑戦である、と言わなければならない。冒黷的といえば、これほどの黷神、神に対する人間のこれほどの独善的な思い上がりはあるまい。
ただ、そう思うのは親潮に鍛えられ黒潮に育まれる火山島弧という恵まれた環境に住むわれわれ日本人の勝手であることも、忘れてはなるまい。
神々をも恫喝して人間の都合に従わせなければ、人間の生存が覚束ないという苛烈激越な環境の中で生きのびるには、それが人間にとってギリギリの究極の選択であったことを理解しなければならない。
支那の神話はズタズタに引き裂かれた神々の物語の断片に過ぎないとは、よく言われることである。もともとは神々の連なる脈々として流れる神統譜があったはずなのだ。それが早くに失われた。神々の多くは神の座から顛落して妖怪変化の類へと零落した。あるいは限りなく人間に近づいた。堯も舜も禹も、もとは間違いなく神であったろう。それが伝説の聖王とはいえ人間として形象されたのは、神にとっては零落の姿にほかならない。
●いずれにせよ、こうした苛烈極まる特殊な状況の中で甲骨文字は発生したのである。シュメール文明においても、この文明に固有の、文字を必要とした特殊な事情というものが必ずやあったに相違ない。
それは今日考えられるような、人間同士のコミュニケーションのためでもなければ、人間の営みを記録する手段でもなかった。甲骨文字の例に鑑みれば、シュメール文字もまた神と人との特殊な緊張関係の中でのみ発生したであろうことは容易に想像がつく。
これに関して充分に説得的な説にはいまだお目に掛かったことがないが、その理由は材料の不足の為せる業ではなくして、問題意識の希薄さ、ないしまったくの無さがもたらす必然的な結果だと思われる。
サミュエル・クレイマーが楔形文字の欠点としてあげている二つの事柄をもう一度思い起こしてみよう。文字の形が複雑になること、そして文字の数が膨大になること、この二点である。
たかだか二十数個の表音文字ですべての言葉を書き表すことに慣れた文明圏の人間が、こう言うのは理解できる。しかし、我を是とし彼を非として彼の特徴を欠点だと断ずるのは、行き過ぎではなかろうか。
漢字に慣れたわれわれからすれば、多くの画数からなる文字があり、多くの異なる言葉を表わすためにそれぞれの文字があって総体として膨大な数を数えるに至るのは、至極当り前の事態なのである。それを複雑であるとするのはまだよしとするも、欠点であるとか、手に負えないなどと非難するのは、多くの言語に通じた言語学者にもあるまじき不見識である。
表音文字書法体系とは異なった表意文字(象形文字)書法体系が存在すると口では認めながら、どうしても感性の部分で初めから優劣を区別しているために、特徴を特徴として踏みこんだ理解へと及ばないのである。
斯学の世界的権威とされる専門家がこうした不見識を披瀝するということは、重大な問題をわれわれに教えてくれる。それは表意文字書法体系で母国語を書き表す学者がシュメール文字を研究しなければならないという単純な真実である。
ハンガリーのツラン研究のウェブ・サイトではシュメール語を膠着語の一種として自国語との関連性を追求していて喜ばしい限りだが、それでもまだ求められる課題の半分に応えることに過ぎない。
もっとも望ましいのは、表意文字を母国語として書くことに慣れていること、そしてシュメール語が膠着語であるとするなら(確かにそうなのだが)、母国語が膠着語であること、この二点を満たす学者なのである。
そうすると、思わざる見落しがあるやも知れないが、ざっと見渡した限りでは、この二つの条件を満たすのは、日本人しかいないのではないかと思われる。
●さらに、日本人をしてシュメール語の研究へと向かわせる特徴がこの古代言語には存在する。それはシュメール語が「言霊」の言語だったという特徴である。
まず、クレイマーはシュメール語が印欧語やセム語などのような屈折語ではなく膠着語であると認めて、膠着語のトルコ語やハンガリー語また数種のコーカサス系言語との少なからざる類似を指摘している。
それはシュメール語の言語としての独自性とシュメール文字の存在を抹殺しようとしたヨセフ・ハレヴィの暴論が学会を攪乱してから半世紀以上の時間を経て、ようやく同じユダヤ人自身の専門学者がその暴論を正したという意味があることに注目しなければならない。佞論久しからずとは、この一事をもって知るべし。
その後にクレイマーの指摘する重大なこと、それがシュメール語はもともと一音語から構成されて出来上がった言語だという特徴である。
それはほんの序でに関説したという按配で、クレイマーも自分でもその重大性にまったく気づいていない。だが、それは取りも直さずシュメール語が「言霊」の言語であると認めるのと同じ重大な指摘と考えるべきである。
ある言語が本質的に独立した意味をもつ一音一音から構成されているなどと言っても、表音文字体系を是とする連中には、何の意味もないことであろう。もちろん、表音文字体系の言語においても、単語としての一音語は存在する。英語でのa(一つの、ある)とか、フランス語のy(そこに)などの単語がそれである。だが、その数は非常に乏しく、各言語に一つか二つあるだけであろう。
一音語では、すべての言葉がもともと意味のある一つひとつの音から成り立っていて、複数の音からなる言葉もそれを構成するもとの一音一音の意味を残して影響を受けている。それらが複合総合されて新しい意味が出て来るのだ。
ここで新しい言葉として「一音語」を提案したい。「一音語」を一つの音からなる一単語という意味に止まらず、言語が総体として語源的に一音の言葉から成り立つ、すなわち言語の重大な特徴を謂う意味をも敷衍できるようにしたいのである。
幸運にも[言霊の幸はふ国」に生まれ合わせた日本人は、言葉が文字である以前に「音」であることを、骨身に染みて分かっている。ひとつの言葉はもともとそれぞれ相異なる香りと勢いと風格を持っていた痕跡を、われわれはかすかに記憶している。
だから、ユダヤの聖典に「はじめに言葉ありき」というとき、その言葉は文字ではなく、音の響きだったとまず思ってしまう。それこそ永い永い悠久の時間に養われた言葉の豊穣なる香りと勢いと風格をもっていて、言葉の意味とはそのほんの一部が文字に表わされるだけであることもわれわれは知っているからである。
したがって、膠着語である特徴にも遙かにまして、シュメール語が「言霊」の言語であると確認できたことから、わが日本語とシュメール語とは本質的かつ密接な関係にあるとここで断言することができる。(つづく)★