
 |
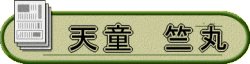
![]()
![]() ツラン魂は健在なり 5
ツラン魂は健在なり 5
(世界戦略情報「みち」平成18年(2666)6月1日第229号)
●もともと「一音語」からなる祖型語から出発して、そのさまざまな組合せにより豊富な語彙を発展させながら、現在もなお「一音語」としての本質を色濃く残しているのが日本語である。そういう日本語を母語として親しんできたわれわれにとって、シュメール学の泰斗クレイマーが指摘した一音語というシュメール語の特徴は、にわかには聞き捨てにできない重要性をもっている。
というのも、「一音語」という特徴こそ、今日では他に例を見ない日本語独自の特質であって、もしシュメール語が本質的に「一音語」であることが十二分に証明されるならば、日本語とシュメール語の関係は、膠着語などという緩やかな関係を飛び越えて、急激かつ一挙に接近することになるからである。
だが、日本語が一音語であるという特質は、残念ながら一般にはほとんど認識されていない。たとえば、「爪」という言葉の発音は「つ」+「め」であるが、その「つ」にも「め」にも、もともとは独自の意味があって、それが組み合わさって「つめ」という言葉ができていると言っても、ほとんどの日本人にはちんぷんかんぷんで、頭の中には「???」が一杯に浮かぶことだろう。
在野の学として続いてきた「言霊学」に触れたことのない人には、日本語のもっとも基本となる要素は単語であって、単語を構成するひとつ一つの音のそれぞれにも独自の意味があるなどという主張は戯言(たわごと)としか受けとられないからである。
ところが、伝統的な「言霊学」とはまったく無縁なところで、「一音語」という日本語の特質に気づいたひとりの建築家がいた。
実は本稿を書きはじめたときから、この建築家が著わした本のことが気になっていたのだが、遙か昔に求めた本である。何度も引越しをして、果して今でも家にあるかどうか定かでない。しかも義父から生前贈与された蔵書が部屋の中央に未開封のまま段ボールの山を築いていて、記憶にある書棚の場所に一朝一夕には辿り着けそうもないので、なかなか言い出せないでいたのだった。
このほど意を決して段ボールの山を取り崩しつつ目当ての書棚に到達したところ、何と! ちゃんとあったのである。ひとまずツラン問題からは脱線するのだが、日本語のもつ「一音語」という特質を独自に発見したこの本について紹介することにしよう。
●それは望月(もちづき)長與(ながよ)なる建築家が書いた『一音語のなぞ 日本語の発掘ノート』(昭和四七年、六藝書房)という本である。専門とする分野ではないものの、日本語の起源や語源には昔からなぜか強い関心があって、これはと思う本に出逢う度に、懐具合と相談しつつぼつぼつと集めてきた。安田徳太郎や金沢庄三郎、大野晋や村山七郎、川崎真治の本などと同じく、この本も脈絡なくただ漠とした期待から買い求めた本である。
一読して驚いたのは、日本語の言葉の一音一音に意味があるとして、その成り立ちを丹念に跡づけている、その努力の積重ねの途方もなさであった。そして、その努力の集積が一定の説得力をもつまでに整理されていることにも、敬意を感じずにはいられなかった。これを手がかりとして自分なりに出発してみようと思うまでには説得されなかったが、それでも著者のユニークな「日本語=一音語」という見解は深く心に残ったのだった。
著者の望月長與は日本語祖語としての一音語をどのように発掘していったのか、その発掘の光景を伝える文章が『一音語のなぞ』の巻末にある「発掘のよろこび ── あとがきにかえて」の中にある。
冬のある日、私は火鉢を脇に置いて本を読んでいました。火鉢には鉄びんがかかっていましたが、炭火はもうだいぶ燃えつきていました。母親に鉄びんの湯のかげんを問われたのでしょうか、息子がかけ込んできて、いきなり指先を鉄びんに触れたようでした。すると熱かったのでしょう、思わず「あつっ」と声を出しました。驚いて振りむきますと、息子は鉄びんにふれた指先を耳たぶに押しつけていました。幸い、火傷するほどの熱さではなかったとみえて息子はそのまま母親のところへ駆け去りましたが、私の耳にふと、「あつっ」ということばが浮かびました。文字にかくと「あつっ」となりますが、発音はむしろ「つ」が強調されていて「あ」はほとんど聞きとれないほどのものだったのです。一音一音のもつ意味を探し求めていた私は、さっそく息子のまねをして鉄びんに指をあててみました。その拍子に思わずついて出たことばはやはり「つ」でした。そしてみると、人が熱いものに触れたときにに出す音は「つ」に違いないと考えました。同時に、人が、あるものが熱いかどうかを確かめようとするときには、おそらくまず指を触れるのではないかと考えました。まさか顔や腹を押しあてることはないと思いました。とすると、「つ」という音は、人が指先で熱いものに触れたときに思わず発する音で、この音が指の呼び名として名付けられたのではないかと思いました。(後に私は、熱いものに触れる場合だけでなく、氷や冷水などの冷たいものに触れても、同様に「つ」という音が発せられることを発見しました)一音語で「つ」とは指のことを意味するのではないかと思い当ったのです。私はさっそくノートにメモしました。
つ …… 指
と。(同書二〇一~二〇二頁)
この下りを読んで大方の人が抱くであろう感想は、「?」ではなかろうか。われわれが熱いものに触れたときに、「あつっ」と叫んでしまうことは納得できるとしても、その意味が「熱い」ではなく「指」だと言われると、首を傾げてしまうだろう。
単にこの光景だけでは、「つ」が指を意味する一音語であるとする著者の発見に、全面的な賛同を表わす気持ちにはなれない。その発見なるものが、恣意的な思いつきの域を出ないと思うからである。
だが、著者自身もこの一事だけで、「つ」=「指」と決めつけたわけではない。先に、著者の途方もない努力の積重ねに驚いたと記したが、他方ではいくつもの例に当たって何度も何度も確かめるという作業が行なわれているのである。
●さらに、日本語の言葉が一音一音の組合せから成り立っているとすれば、二音や三音から成る言葉において、それを構成する一音一音の意味を改めて確かめるという方法も、一音の意味を確定する上で助けになる。
望月長與はある一音語の意味に見当を付けると、さらには意味の明らかになった一音語同士を付き合わせて二音語を作り、それが元の意味を反映して矛盾を来さないかどうかを確認していったのである。
先の引用につづけて、望月はこう書いている。
私のノートには、すでにいくつかの一音語がこのようにしてメモされてありました。たとえば、
め …… 芽=皮を破って出るもの
く …… 直角
か …… 堅い
のように。
一音語「つ」の発掘は、じつはここにメモされただけではありませんでした。私はまず「つ」と「め」、「つ」と「く」、「つ」と「か」というように、意味の判然とした一音語どうしを組みあわせて、二音語をつくりました。すると、「つめ」「つく」「つか」になり、それぞれ、つめ(爪)、つく(突く)、つか(握)のように、意味のある二音語ができあがりました。
そこで、こんどはそれぞれの一音語の意味を単純に結合させてみました。まず、つめ(爪)は「指」と「芽」です。私はじっと自分の爪をみつめました。爪は確かに芽のように、指の皮膚を破ってはえているのでした。つめ(爪)という二音語は、つ(指)とめ(芽)という一音語から成り立っているという確信を得るのでした。
つく(突く)はどうでしょう。同じように意味を結合させますと、「指」と「直角」ということになります。これはそう簡単にはいかないようです。そこで私は、指でノートを上から突いてみました。そして、突くという動作をつぶさに思い描いてみたのでした。すると、指を直角に立てて物に当てる動作、つまり一音語のつ(指)をく(直角)にあてる動作こそ二音語つく(突く)があらわす動作にほかならないことに気づくのでした。
第三のつか(握)は、私にとって貴重な発掘でした。すでに私は、日本身度尺度称として、つか(握)というものがあることをつきとめていましたが、その呼び名がどこからきたか、また、なにを意味するのかがわからないために、尺度研究の進行がストップしていたからでした。
一音語の意味の結合から、「指」と「堅い」ということになります。とすれば、この二音語つか(握)は、指を堅めるということになりそうです。じつは、さらに別の一音語む(力む)をつなぎ、三音語つかむ(握む)ということばを考えますと、その意味は一層明瞭になります。すなわち、つかむ(握む)は、指を堅めて力を入れる状態をさしています。(同書二〇三~二〇四頁)
引用文中の赤字部分「日本身度尺度称」とは耳慣れない言葉であるが、無理もない。それは望月長與の独創にかかる言葉なのである。これについては後に述べることとして、とどのつまり望月は、さまざまな言葉における一音語の組合せの例からもともとの一音の意味を帰納するという作業を一方で行ないながら、同時にもう一方では、こうして類推された一音語の原義を二音語や三音語として組合せた例によって確認する作業を行なっているのだ。
そうした作業の中で、「つか」の「か」が「堅い」という意味だと分かっていながら、では「つか」の「つ」は何か、何が堅いのか、どう堅いのかと突きつめていく厖大な努力の果てに、息子が鉄瓶に触れて「あつっ」と叫ぶという劇的な瞬間が訪れる。
すでに多くの例から、最後の最後のぎりぎりの点まで煮詰まっていた着想が、その叫びとともにはっきりと形を現すのである。「つ」とは「指」だ!と。
それはちょうど、アルキメデスが風呂に浸かって溢れ出る水を見た瞬間にアルキメデスの原理を発見したのと同じく、考えに考え抜いても解けなかった難問が、ふとしたことがきっかけとなって一挙に解決するという、まさに発見の瞬間だったと言ってよい。
だから、望月はこう書くのである。
一音語「つ」の発見は同時に他の一音語とつらなって二音語をつくり、さらには三音語にも発展していくのでした。こうして、一つの破片としてつまみあげたものが、他の破片と密着することにより、原始人の偉大な遺物は復元されていくのでした。私は、よろこびに字まで踊らせて、メモして行くのでした。
つめ(爪) ……… つ(指)め(芽)
つく(突く) ……… つ(指)く(直角)
つか(握) ……… つ(指)か(堅い)
つかむ(握む) ……つ(指)か(堅く)む(力を入れる)
と。
いま、ふりかえって発掘作業の一例をここに書き示すだけでも、私の胸は小躍りをはじめるのです。
ここにあげた発掘作業は、ほんの一例にしかすぎません。ひとつの破片を発掘するたびに、なんど胸を躍らせてきたことでしょう。しかも、もっとうれしいことには、破片として発掘した一音語が二音語になり、三音語になり、限りなく発展していくことです。 (同書二〇四~二〇六頁)
ここまで読み直してみると、今度は望月長與の喜びまでが伝染して来そうな気がする。もちろん、日本語がもともと一音語であるという望月の主張にはとっくに賛同している。
私の場合には、有難いことに、同志三橋一夫や藤原源太郎の教示によって「言霊学」への蒙を啓いてもらったので、今はなんの抵抗もなく望月長與の発見に賛同することができる。そして、「言霊学」に触れることなく、独自の研究の成果として一音語という日本語の本質に迫りえた望月の独創と発見とに、遅まきながら満腔の敬意を捧げたいと思うのである。
●そもそも望月長與が日本語の語源に関心を抱き、日本語の一音一音が意味をもっているのではないか、と疑うに至ったのは、日本古来の尺度の研究を進める中でのことだった。
『一音語のなぞ』のカバー折り返しに掲げられた望月長與の写真を転用させてもらって参考までに載せておこう。

同じく同書のカバー折り返しと奥付に記された望月の経歴にはこうある。
著者略歴 望月長與(もちづきながよ)
明治三十四年、山梨県中富町西島に生れる。早稲田大学理工学部建築学科に学び、大正十三年、岡田信一郎建築事務所に勤務。在勤中に設計担当した主要建築物に、東京都立美術館、明治生命保険本社ビル(競技設計一等当選)、ニコライ堂改修工事などがある。その他競技設計入選のおもなものは、神戸市公会堂、地下鉄本社ビル、山梨土建会館など。早稲田高等工学校講師、芝浦工業大学講師を歴任。現在、望月長與設計事務所(東京都三鷹市)代表。著書「日本人の尺度」一九七一年。
この経歴を見る限り、望月は紛れもない建築家である。建築家がどうして日本語の語源に関心をもつようになったのか、その経緯を望月は「はじめに」に次のように記している。
私は昨年[昭和四六年──天童]同じく六藝書房から「日本人の尺度」という本を出しました。私は建築設計を仕事とするかたわら、日本建築のモデュロール(黄金尺)に興味をもち、日本の古代尺度の研究をはじめたのです。そのなかで、尺度はそれぞれの民族の身体の度に発生起源があること、日本にも日本人の身体の度から発した、つえ(丈)ひろ(尋)あた(咫)つか(握)き(分)などの古来の度称(私はこれらを日本身度尺と呼んでいます)があることをつきとめたのです。
日本身度尺は、朝鮮や中国古来の尺度とその実長を異にしていることから、ここに用いられている丈・尋・咫・握・分などの漢字はおおむね周時代の中国の度称に用いられていたもので、それが日本へ伝わり、日本古来の身度尺つえ・ひろ・あた・つか・きにそれぞれ当て字されたものであることが判明したのですが、ではいったい、日本身度尺にいう、つえ、ひろ、あた、つか、きという度称の起源はなにかをつきとめる必要が生じてきたのです。
私の日本語源の研究は、これを動機として、ここからはじまったのです。(同書五~六頁)
望月長與が洞察した「尺度はそれぞれの民族の身体の度に発生起源があること、日本にも日本人の身体の度から発した、つえ(丈)ひろ(尋)あた(あた)つか(握)き(分)などの古来の度称がある」という事実は、その後の数々の考古学的発見によって確認されることになった。出雲大社の創建時にまで遡る遺構が発見され、そこに用いられた基準尺度が日本独自のものであることが確認されたのをはじめとして、それより遙かに時代を遡る縄文時代の三内丸山遺跡や日本海側の豪雪地帯に建てられた巨大建築物などにおいても、同じ尺度が用いられていたという、驚くべき事実が明らかになっている。
●いま手許に典拠とすべき書籍がないので間違っているかも知れないのだが、東大寺創建時の建築に用いられた尺度も日本古来の尺度であったように記憶する。すなわち、望月長與が発見した「日本身度尺」である。
東大寺創建に関する古文書として有名な「東大寺流記資材帳」を分析した久野健によれば、東大寺という当時の世界最大の木造建築の設計を担当したのは、ササン朝ペルシアの亡国の遺民たちであった、という。
古代ペルシアの旧都ペルセポリスに興ってシュメールの故地メソポタミヤまで版図を広げたササン朝ペルシア(二二四~六五一)は、ローマ帝国やビザンチン帝国と拮抗しつつ四〇〇年以上も続いた末に、台頭するイスラム勢力との戦いに敗れて国が滅びた。
ササン朝最後の皇帝のヤズダギルド三世がメルブで暗殺されたのが六五一年で、東大寺大仏の開眼供養が行なわれた七五二年からは一〇〇年もの隔たりがある。なにゆえに一〇〇年も前に滅びた遠い国の遺民たちが、はるばるわが国に辿り着いて東大寺の創建に関わったのか。
そこには、王朝再建に望みを繋いで支那に亡命し唐朝の庇護を受けた王子ペーローズ(唐では卑路斯なる漢字を宛てた)の存在がある。実は、長安に亡命したこのペーローズの物語こそ、トリノ冬季五輪で荒川静香が使ったことから日本でもにわかに有名になったプッチーニの歌劇トゥーランドットの元になった史実なのである。
そして、ペーローズが斉明朝の日本に使節を派遣して王朝再建への援軍を求めたのではないかという可能性すらあるのだ。
それは、斉明紀に出てくる童謡(わざうた)の謎が古代ペルシア語で解けると教えてくださった孫崎紀子氏(前イラン大使の孫崎亨氏夫人)のササン朝と斉明朝との交流説(強引に懇願して本誌への掲載許可を頂いているので、近くご紹介する予定)に基づいて、私が勝手に構想した独断なのではあるが……。
だが、東大寺創建には建築家として紛れもなくペルシア人たちの名前が登場する。ただし、注目したいことは、建築設計にはペルシア人の手を借りながら、建築の尺度には望月長與のいう「日本身度尺」が用いられている点である。その「日本身度尺」に象徴されるように、わが国には古来より独自の巨大木造建築の技術が伝承されていたので、設計を託された渡来ペルシア人たちもまた、建設工事に従事する大工たちが指針とする実際の建築尺度には日本古来の尺度を用いるほかなかったのである。
その日本古来の尺度の名称が、実は日本語の起源と密接な繋がりがあると気づいたことが、望月長與の日本語の語源研究への出発点となる。
さて、尺度はどの民族でも、そのはじまりには民族特有の身度に基準を求めている。だとすれば、その身度を表わすことばには身体の名称が使われていなければならないという考えにやがて行きつくまでには、かなりの過程があったのです。この発想はさらに転じて、身体の名称が度称に使われていたとすれば、身度尺はその民族のあいだにはきわめて早期に発生しうる可能性があり、きわめて原始性のあるものとなりますから、ことばの発生およびその発達過程と密接な関係があったのではないかという考えに思いあたったのです。(同書六頁)
やがてこの着想が「一音語こそ日本語の祖型である」という独創的な卓見へと導いてゆくことになるのである。
(つづく)★