
 |
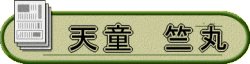
![]()
![]() ツラン魂は健在なり 6
ツラン魂は健在なり 6
(世界戦略情報「みち」平成18年(2666)6月15日第230号)
●望月長與が発見した「日本身度尺」としての、つえ(丈)ひろ(尋)あた(あた)つか(握)き(分)など日本古来からの度称が身体の部分の名称に由来していることは、すでに分かっていた。すると、ある長さをなぜ一定の名前で呼ぶかという問題は、体のある部分をどのような状態にしたときの長さであるかを明らかにしなければならないと同時に、身体の各部をなぜそう呼ぶかという問題へと繋がっていく。
日本語を構成する「て、に、を、は」など一音の助辞にそれぞれ意味があることは誰しも納得するところだろう。だが、「つめ」(爪)や「あたま」(頭)というときの「つ」「め」や「あ」「た」「ま」のそれぞれに意味があるなどというと、そんな莫迦な、と一笑に付されるのが落ちである。
他ならぬ私自身、望月長與の著書を初めて開いたときには、大いに疑いをもっていたのである。一読した後には、「そうかも知れないなァ」と思うようになったものの、そのまま長い間等閑にしていたのだった。今回改めて具に読んでみると、日本語の一音一音にはもともと意味があった、ということは動かないと確信するに至った。
ただ問題は、一音一音のもともとの意味(原義)をどのように定めるか、にあることに気がついた。原義の確定に当たっては、数多くの合成語(二音語、三音語……)の例に当たらなければならない。合成語で原義がどのように生かされているか、元の意味が敷衍しているとすれば原義のどの部分が発展しているのかなどを確認した上で、元の一音の意味を、それぞれ類推していくわけだ。なにせ資料も典拠もない未踏の世界である。どうしてもそこには、恣意的な思い付きの要素が入ってくることを排除できない。すなわち、一音の原義の確定に当たって、絶対的な保証は何もないのである。
だが、だからといって、一音一音に意味があることを疑うのは早計だ、と私は思うようになった。望月の独創的な発見の一端なりとも紹介できればと願うのだが、この短い一文を読んだ後に果して読者諸賢がどう思われるか、日本語の一音一音にはもともと意味があると思って下さるかどうか、まずは祈るような気持ちである。
●望月長與が身体の名称・状態に由来する「日本身度尺」の発見から日本語の祖型をなす「一音語」の着想を得る上で、決定的に重要なことがあった。それは「手」や「目」「毛」など体の部分の名称には一音語が多いという点である。また左右対称に二つあるものには「頬」や「乳」「耳」など同音を重ねて二音語になっているが、これも本来は一音で呼んだものが、左右二つあることから、同音を重ねて二音語になったもので、もともとは一音語だと見なせる。
体の同じ部分を指すのに、別の名称がある場合がある。たとえば、「目」を「め」というほかに、「まなこ」とも呼ぶ。だが、そうした複音語よりも一音語の方がより古いと考えることに無理はない。複音語は一音語の原義を踏まえて後に合成されたと考えられるからである。
この一音語の身体名称こそもっとも古く、おそらくその発生以来変化していないとすれば、これらの身体各部がなにゆえそう呼ばれるのか考えれば、日本語の中の一音語の意味を解明することができるし、さらに二音語や三音語がこの原義を組み合わせ説明できることになれば、一音語こそは日本語の祖型語であったと言うことができる。望月長與はそう考えたのだった。
われわれの生活環境において日常の使用道具、家具、什器の類は文化の進展とともに目まぐるしく変化していきますが、原始の時代から変化のないものは自然物や自然環境、そして人間の身体の構造でしょう。これらの名称は早期につけられ、単純かつ素朴であるため、後世にも使用便利で、改名改称の必要を迫られることが少なく、ひさしく保存される性質が備わっていることが多いようです。一音語がもっとも原始性があり、もっとも祖型的であるならば、これらの名称のなかに容易に見出されなければなりませんし、じっさい、人間の身体各部の名称に、すぐに思いあたります。
まずこれを略図[上図参照──天童]で示してみますと、単純音語が非常にに多く、なかでも目立つのは一音語名称です。ちち(乳)とかみみ(耳)などのように、同じもの左右対称にダブっているものは同音語を重ねて二音語になっていますが、これは一音語と見なされるべきものです。
一音語が身体名称に十以上二十近くあるということは、まことに驚異的です。そしてこの一音語名詞は今日でも抹消されずに使われているのです。このことは、単純で便利であって、いままで改称する必要が認められなかった証拠であるというべきでしょう。(『一音語のなぞ』七~八頁)
「原始の時代から変化のないもの」として望月が自然物や自然環境を挙げていることは、今日から見れば奇異の感を否めないが、まだまだ昭和四〇年代はそういう認識が常識として通用するような古きよき風儀が残っていた時代だったのだろう。今日では自然物や自然環境こそ激変を余儀なくされている代表のような感がある。それだけに、古代より日本語で使われてきた一音語の身体名称が今日なお依然として変化することなく使用されていることは、まさしく驚くべきことである。
そしてその一音語が日本語の祖型ともいうべき古い意味を保存しているとすれば、それがシュメール語と直接に結びつくかどうかはさて措き、必ずやモンゴル語やトルコ語、ハンガリー語、フィンランド語などツラン系の言語の祖語と密接な関係をもつはずである。もしも日本語以外でもツラン系言語が一音語によって成り立っていることが確認されるなら、それはツラン系言語の系統論においても、また各言語祖語の研究においても、前人未踏の画期的な沃野を切り拓くことになるだろう。一人でも多くの関心ある人々が一刻も早く一音語の研究に着手しなければ!という焦慮に駆られるのを、私は禁じえないのである。
というのも、日本語の身体名称ほど時代の変化に対して強靱なものはないなどと手を拱いて嘯いているだけでは、日本語そのものがいつ何時死語になるか知れたものではないのである。他から強制されて使用禁止になるか、それとも自ら放棄して死語となるかは問わず、古来より死語となって使われなくなった言語は枚挙するに遑がないのだから。また昨今の英語のように、「一般大衆のコミュニケーションに便利な」だけの、総語彙数が六〇〇語やたかだか九〇〇語から成る平板な幼稚言語にわが日本語がいつ堕するやも知れないのだ。少なくとも、含蓄を湛えた古来の言葉が敬遠されて「常用語」から追放の憂き目に遭うという事態は日々に進行しているのである。
●さて、古来より一貫して使用されつづけてきた「日本身度尺」の名称が、なにゆえにそう呼ばれるのか、それを考究する前に、一音語で表わされることの多い身体各部の名称それぞれの意味を見ておかなければならない。
望月も「原始日本人の使用していた原始尺度と、その呼称に関する原始語ついて考察してみたい」と言いながら、そのすぐ後で、「身体名称の発生源について、もう少しくわしくし、その発展過程をたずねてみましょう」と言わなければならなかったように、「つえ」(丈)「ひろ」(尋)「あた」(咫)など多くが二音語から成る「日本身度尺」の語源を求めるには、それに先だって身体各部の一音語名称の語源を明らかにしておくことがまず要求されるのである。
身体の名称の語源について望月独自の考えが述べられるのは、次のあたりからである。上掲の図を参照しながら、読んでほしい。
脚(Legs)は全体をしと呼んだようです。その先端の足(Foot)をたと呼びました。足を踏む音がたんたんときこえるところから、この音声をとらえてたと名づけたのでしょう。のちに足袋をはく時代になって、これをたびというのも当然です。手袋は、あまり古くはなかったかもしれませんが、もしあったとすればてびだったでしょう。
手もあたと呼ばれることがありました。手も、両手で拍子を打てばたんたんまたははたはたと響ききこえます。したがって、手をたと呼ぶのも異例とはいえないのです。
たのいちばんもとは舌で、舌を上顎に叩きつけて発音するとたという音が出ます。このた音が舌の名称となるのも当然すぎるほど適切です。このようにたのつくものが舌、手、足と三つもあるのですが、舌が第一のおおもとのたであることから、ひたというようになりました。(後で説明しますが、ひは最初とか第一という、数詞の第一番目のことです)。それは手を足と区別するため、て(手)としたのと同じ考慮からでしょう。
はじめにでてきたあの音語は、発展してものの端につけられるようにもなりました。頭全体が、まえにも説明したようにまるい形をしているのでたまであり、身体の最上部にあるたまはあたまとなりました。手は足とともにたで表現されたが、たがてになまっててといい、うでの先端にあたる部分はあたといいます。し(脚)の先端にあをつけて、あし(足)と呼ぶのは、みなこの類例です。
顎は、物を食べるとき、下顎がぐきぐき動くところから、あぐと名づけられています。手には指があります。指は原始語ではつという名称になっていたようです。やはり一音語です。
つは、今日でも原始的に発音されることがあります。たとえば、沸騰したやかんにうっかり手を触れたとき思わずつーという音が口から飛び出しますし、おもしろいことに、冷水などに手を触れてもやはりつーといってしまいます。温度計などがもちろんない原始時代には、物が熱いか冷たいかをはかるのにもっとも便利に使用したのは人の指でしょう。そして思わずつーと声を出すことが日常茶飯事だったと思われますが、このつーという発声が指の名称となったのでしょう。
爪はつ(指)の芽ですからつめです。一音語名称が二音に重なった複合名称です。
(同書三〇~三一頁)
多くの創見が随所に鏤められている文章であるが、別の箇所で説明されているのでここでは省略してある一音語の語源の考察もあり、これをいきなり読まされたのでは、納得できない部分もあるであろう。ここに取り上げられた一音語について、別の個所での説明も参照しつつ、私の気づいた点を補足してみよう。
◎「し」(脚)……脚を「し」と呼ぶのは二次的な呼称で、一次的には「棒」を意味したと別の個所(二〇頁)にはある。棒をなぜ「し」と呼んだのかという「語源の基礎」と称する欄には、「腕、脚、棒などで家畜を追いまわすときに思わず口から出るしーしーという音からの発想」と書かれている。
望月は一音語の拠って来たる語源として、「思わず口を突いて出る」音に注目している場合が多いが、その語源説明には充分首肯できるものもあれば、首を傾げざるをえないものもある。しかし、望月の説明に納得できなければ、自分で探求してみればよいので、語源の説明そのものにさほど目くじらを立てる必要はないと私には思える。小異を捨て大同を採る寛容な度量が、一音語研究にはとくに必要であると、思われるのである。
ここで重要なことは、細長い棒状の物を「し」と呼んだということであり、人間の体の中で「細長い棒状のもの」として脚全体を「し」と呼んだという説明には説得力がある。その脚の「し」に、物の端や先端部分を意味する接頭辞的一音語の「あ」が付いて、「あし」(足)というようになったという説明も疑いを挟むところはない。
「し」が「細長い棒状のもの」を共通に意味していると気づいたのは、望月長與の独創的な発見だと言ってよい。細長い棒状の物を「し」と呼ぶことが動かないとすれば、これを基礎にして「し」を含む二音語や三音語の語源の解明へと進むことができる。
たとえば、望月は別の個所で「むし(虫)のしは棒状のことで、ふつう棒はそれ自体は静的なものですが、人がそれを使用することによって、むち(鞭)にもなり、杖にもなるのです。体全体が棒状をなしている虫は、動くのに力を入れて屈伸します。この屈伸がむで、むし(虫)は力を入れて屈伸する棒の意味です。昆虫は六本のし(足)があるので数詞のむ(六)という数からむしと呼ばれます」(四二頁)と言っている。
それは「むのつくことばは力の入った意味のことば」の例として挙げられたものだが、一方で「力を入れて屈伸する」(む)「細長い棒状のもの」(し)だから、「むし」(虫)と呼んだのだと言い、また一方で「し」(足)が六本あるので六本足という意味で「むし」(虫)と呼んだと言うのは、虫と昆虫という違うものを、どうして同じ名称で呼んだのかとの疑問が残るが、「し」のもつ「細長い棒状のもの」や「脚」という原義は、いずれの場合にも一貫して保たれている。
「はし」という二音語の意味する言葉の内に、橋と箸とがあるが、望月長與はその語源がともに「二つの」「細長い棒状のもの」から来ているとする。「は」が「二つの」という数詞を意味するかどうかここではさて措くとして、「橋は、発生源的には川あるいは谷間にかける場合、丸太一本ではすべって危険ですから、必ず丸太二本をつるや縄でゆわえてかけたことでしょう。はしは二本棒のことです」という説明を聞けば、なるほどと思える。
鳥の嘴も、「くち」+「はし」で、口にある「重なり合った二本棒」と解すれば、容易に語源の理解ができる。
いずれの場合も、「し」という音が共通して「細長い棒状のもの」を意味していることを確認することができるのである。
◎「た」(舌、手、足)……一音語の「た」は舌と手と足という異なる三つの身体部分を意味していた、と望月は主張している。
あるものに名前をつけて呼ぶことは他と区別することが本来の目的のはずである。それが同じになってしまう場合には、同じ名前で呼ばれるそれぞれのもの同士に、共通の特徴がなければならないはずである。
自然の事物や人間に関係する事象の中で、どうしても名前をつけなければ不便でしようがない「もの」が出てきたとき、名前をつけるべき対象は数多いのに、命名する際に用いる「音」には限りがあるという事態に、われわれの祖先は直面したに相違ない。
そこで、できるだけ「音」の使用を節約しようと知恵をはたらかせたのであろう。ただし、異なるものを何でも同じ名称で呼んだのでは、命名するという行為自体が意味をなさなくなる。相異なるものが同じ一音で表現されるには、その音が本来もっている雰囲気とか響きなどの特徴が、名づけられるべき対象となるものの中に見出されることが前提となる。
これを逆にいえば、一見表面的には異なる事物の中に、共通の本質ないし特徴を見つけ出すという鋭い観察眼を、わが祖先は備えていたことになる。
望月によれば、舌・手・足という相異なる身体部位を呼ぶのに用いられた「た」は、それぞれが発する「たっ」や「たんたん」「ばたん」「はたはた」などの「た」音に由来するという。
総じて望月が説く一音語の語源説明には、この「た」音の場合のように、しばしば擬音や擬態音が持ちだされるのだが、今日でも「もくもく煙が出る」とか「ぴしゃりと叱る」などと表現すると途端に情景が髣髴としてきたり、また、「名文家とは一に擬態音の使用上手をいう」などとも言われたりすることを考え合わせれば、一音語の語源として擬音や擬態音に望月が着目したのは、これまた卓見というべきだろう。
今日では「もくもく」「ぴしゃり」などの擬音語、擬態語を日本語ほど多用する言語はちょっと他に見あたらないように思うが、古来よりずっとそうなのかどうか。漢文脈の文章語は論外としても、純和文の文章にはよく出てくるという印象がある。
曖昧模糊とした話で恐縮なのだが、オロチョン族だったかギリヤーク族だったか、いずれにせよロシア圏に住む北方狩猟民系のある民族では、狩猟の様子を物語るのに全編ほとんど擬態語と擬音語で語りつづける、という話を本で読んだかテレビで見たかした記憶がある。もしもそれがツラン系に属する北方狩猟民であるとするなら、擬音語や擬態語の多用という切口によってツラン系言語を検証してみることも、面白いかも知れない。
望月の多くの卓見には感服のほかないが、ただ、何度もいうように、個々の語源説明が当たっているかどうかは別問題である。
手を「て」と呼ぶ以前に「た」と呼んでいただろうことは、手首より先の部分を「あ」(先端)+「た」(手)で「あた」(咫)と呼び、「たなごころ」(掌)という手に関連した言葉があることからも確かであろうが、その「た」が手を打ち鳴らしたときの擬音に由来するのかどうか、俄には賛同できないような気がする。多くの例に当たって確認してみないことには、これだけでは判断のしようがないからである。
舌も「した」と呼ぶ前に「はた」と呼んでいたかどうか、説得力に欠けるといわざるをえない。そもそも私の口では機能障害があるせいなのか否か、「舌を上顎に叩きつける」ことなど、何度やってもできそうにない。むしろ舌を予め硬蓋音に密着させておいて、急に大きく口を開けば、「たっ」という音が出る。それでも、この音に舌の名称が由来したかどうか、即断はできないように思えるのだ。
足も「た」と呼んだとあるが、一方では「し」(脚)の先端「あ」に位置することから「あ」+「し」で「あし」と呼んだと説明されている。すると、足を「た」と呼んだ一音語は合成語の中に残るほかはいつしか廃れ、「あし」という二音語に取って代わられた経緯があるのかも知れない。ここらも説明が欲しいところである。
こうしてみると、望月の語源説明にいちいち難癖ばかり付けているようでいささか気が引けるのだが、日本語の起源について一音語という新たな世界を開拓した望月の功は何ら減ずるものではないことを強調しておかなければならない。(つづく)★