
 |
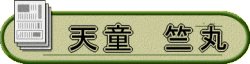
![]()
![]() ツラン魂は健在なり 8
ツラン魂は健在なり 8
(世界戦略情報「みち」平成18年(2666)7月15日第232号)
●望月長與が一音語こそ日本語の祖型だと気づく発端になったのは、日本の古代建築に用いられた日本独自の尺度が存在していて、その長さが日本人の身体の長さを基準とし、名称も日本人が身体各部を呼んだ一音語に由来することを発見したからであった。これを望月は「日本身度尺」と呼んだのだが、では「日本身度尺」とは具体的にどういうものであったのか。
望月はこう言っている。
古事記や日本書紀、風土記の編纂された七世紀頃まで残っていた日本の度称が、いかにも原始的で身体についている原始名称と関連性のある呼び名であることに驚かされるのです。
いまその例をあげますと、中国の尺度度称の、丈・尺・寸・分(漢の時代に確定された度称)が渡来する以前から、発生慣用されていた、つえ(和訓称都枝)つか(都加)あた(阿多)ひろ(比呂)きだ(伎陀)などがあります。これらはいずれも日本原始人の身度すなわち身長とか、身体の一部の長さの度合から発生したもので、同種族間には共通の標準長として容認されて、ことばと同じように普遍化されていったのです。……
日本に漢字が入ってからは、度称のあたは咫(シ)に、ひろは尋(ジン)に、つかは握(アク)に、つえは杖(ジョウ)にあてはめられたので、支那中国の度称のようにみえますが、実際は日本原始語で表現されている日本原始度称です。(『一音語のなぞ』四三~四四頁)
以下に、望月の説明を借用しながら各名称についてみてみよう。
◎「あた」(咫)……この身度尺呼称は手を「あた」と呼んでいたものを、そのまま用いたのである。手首付根から中指の先端までの長さをいう。なにゆえに手が「あた」と呼ばれるのか、すでに先々号で紹介してあるが、念のためもう一度まとめておく。
「あた」(手)は一音語「あ」+「た」の合成語で、この場合、物の先端ないし端を意味する「あ」は基幹語の「た」を修飾ないし限定する形容語であり、意味の中心は「た」にある。
「た」は「タッ」という音を発することから、まず「舌」の名称として用いられた。ところが他にも「た」と呼ぶ身体部分があるので、「大本の」「第一の」という意味の「ひ」を前に冠して「ひた」と呼ぶようになる。この「ひ」が訛って「し」と発音されるようになり、舌は「した」となった。
足を踏み鳴らせば、「タンタン」という音が出ることから、足も「た」と呼ばれた。「たび」(足袋)にその名残がある。だが足を意味した「た」は、脚を「し」と呼んだことから、その先端部分であることを表示する「あ」を冠して「あ」+「し」で「あし」と呼ぶ呼称によって早くに取って代わられたらしい。
一音語を作ったわが祖先たちには、手を叩いたときの音も「ハタハタ」とか「タッタッ」とか「た」音が顕(た)って聞こえたようである。はじめ手もまた「た」と呼ばれたが、同じく「た」と呼ばれている足と区別するために、「た」を捨てて「て」と呼ばれるようになった、と望月は解釈している。
ところが、咫は「あて」とは呼ばれない。あくまで「あた」である。これは、手の先端部分を意味する言葉が、まだ手の全体を「た」と呼んでいた頃に成立したことを教えている。
面白いことには、同じく手の一部の腕を言い表すのに、「た」ではなく「で」(「て」の転訛?)を基幹語として、それに「う」を前に付け「う」+「で」で「うで」と呼んでいる。「うで」という名称が生まれた一音語の発展段階においては、手の呼び名がすでに、「た」→「て」→「で」と変遷していたことを窺わせる。
なぜ「うで」と呼んだのか気になるところだが、「う」および「で」の意味については、残念ながら望月も詳しい解釈を記していない。
◎「つか」(握)……「つか」とは、「つ」(指)を曲げて力を入れ「か」(堅い、堅く)の状態にした拳固のことをいう。身度尺のひとつとしては、この状態で親指を除く四指掌(小指の端から人差指の端まで)の長さを「あた」とした。人の体の構造上、「つか」は「あた」の半分の長さになる。
指を曲げて力を入れ、物をしっかりと手に取ることを「つか・む」というのは、「つか」の動詞への展開である。言葉の発生順序からすれば、一般的にまず感嘆詞や名詞が誕生し、それから動詞や形容詞へと発展したと考えられるが、日本語祖語が一音語から出発したことを前提にすれば、一音語から二音語さらに三音語や多音語への展開がそのままそれぞれ多音語の中に残っていることが分かる。
これは実に、驚くべきことである。日本語の発生以来の秘密がそれぞれの言葉の中に眠っているのだ。とすれば、日本語の語彙のひとつ一つの成り立ちを慎重に解き明かしていけば、日本語の言語意識の成熟の諸段階をも跡づけることができることになる。
つまり、最初はある特定の物や状態を意味する一音語が、先に述べたような「拡充」や「転用」を経ると、同じ音でありながら、まったく別の新しい意味をもつ一音語を誕生させることができる。さらには、「双称法」「合成法」などの手法を用いることによって一音語同士を組みあわせ、ある物の部分をより正確に指示したり、特殊な状態をより精密に表現できるようになる。
それだけではない。やがていくつかの言葉が集まって文をなすようになるはずだが、その文の中における役割、すなわち文法上の機能を果すために、合成語を作る際に特殊な規則が用いられるようになる経緯までが分かるのである。
さらに想像をたくましくするならば、どのようにして動詞が生まれたのか、形容詞が必要となったのか、そもそも助辞とは何であるのか、それぞれの文法機能の発生の事情までもが明らかになってくる可能性がある。
おそらくそれは、漢字がセットとして一挙に誕生した劇的な状況にも比肩すべき、言語意識の爆発とでも名づけるほかないような一大事件であったに違いない。しかも日本語の場合、その言語発展上の大事件は一度きりでなく何度も起きたと思われる。
一音語の「つ」や「か」さらに「む」から「つ・か・む」(掴む)が誕生した経緯に鑑みるだけで、このような想像を促してくれるのである。
われわれの一音語研究の前には、誰も想像できないほどの豊かな未開の沃野が拡がっているのだ。
◎「ひろ」(尋)……両手を大きく開いて水平に上げ、一直線にした状態、これが「ひろ」である。この状態で、左右の手先の間の距離を測ったものが長さの単位としての「ひろ」である。
これを「ひろ」つまり「ひ」+「ろ」で呼ぶことについての望月長與の説明はいささか舌足らずというべく、明快さに欠ける。
らという語は広いという意味です。手を開くと手の平といって、広く平面的なものがえられます。これが原始人の発想したらの観念でしょう。手の裏を返すなどというときのうらは、物を掴む方の手の平のことで、その反対の、両手を正常に垂れたとき外側へ向いた方がおもてです。
らは広いところですから、空、原など際限のない広い場所も総称しますが、その広い場所をある一定の面積に区切られた場所をろといっています。ろ(炉)・むろ(室)・くろ(畔)・しろ(城)・ところ(所)などにろのついているところから、その意味が受けとれます。
いま両手を左右に開いて、その限定された長さをはかると、同種族間ではほぼ同長の標準度がえられます。この度長がひろ(尋)ですが、ひらの制限されたものとして、ひろ(尋)という度称となったなりゆきが判断できます。 (同書四四~四五頁)
この説明によれば、広い場所を「ら」といい、一定の範囲に区切って限定された場所を「ろ」といっているのだが、それは納得できる。「ひら」と「ひろ」も広い場所とより限定された狭い場所という関係にある関連語なのであろう。
だが、ここにともに用いられている「ひ」の説明がないので、いまひとつ腑に落ちないのである。
例によって「一音語意味表」を見ても、「ひ」の解説には、「はじめの意味」として「陽」「第一」、「二次的な意味」として「火」とあるばかりで、これでは「ひろ」や「ひら」の「ひ」は解けそうにない。
望月の解説の中に登場する「開く」(ひ・ら・く)や「広い」(ひ・ろ・い)、さらには容易に思い浮かぶ「拡げる」(ひ・ろ・げ・る)や「平ら」(た・ひ・ら)なども同じ意味系列の言葉だと思われるのだが、これらの合成語を構成する共通基幹語となっている肝心の「ひ」の意味が明らかでないので、得心できないのである。
◎「つえ」(杖)……「つえ」とは、「つ」(指)で握ってもつ「え」(枝)の意味だと望月はいう。そして、それが度尺として古代日本人の標準身長の長さを表わしていたのだ、と。
人の身長を古代の日本人は「たけ」とも名づけたと望月は紹介している。その「たけ」とは、「た」(足)と「け」(毛)から成り、「足の爪先から頭のてっぺんの髪の毛までの長さ」という意味で非常に分かりやすい。ちなみに、毛をなぜ「け」と呼んだかというと、「け」はもともと「欠如した状態」を意味して、わが祖先たちにとっては、毛は細く貧弱で栄養が欠如したものと見えたから「け」と命名したのだと望月は解釈している。
では、なぜ手にもつ「つえ」(杖)が身長と同じ長さになるのか。望月の説明を聞いてみよう。
原始時代、ことに狩猟時代には、原始人は猟具として弓矢を使いました。弓の大きさは自由に作れるのですが、もっとも威力を発揮でき、もっとも使いよい弓の大きさは、その人の身長大の大きさです。それで弓を身長に合わせて作る習慣ができたようです。弓はまた山野を跋渉する場合つえ(杖)にも使えるのです。ジャングルのような枝のさくそうしているところをとおりぬけるには、杖を握って前方に差し出して歩くことによって、顔面、ことに目などを保護することに役立ちます。この意味で弓はただちに杖に使用されていたわけです。
つえ(杖)は漢土でも木偏に丈(身の丈)をならべた文字になっています。日本の古典では枝の字をあてています。日本の皇室には古来から臣下に与えられた宮中杖というものがありますが、国家の功労者で八十歳を越えた老人が宮中へ参内するとき許された杖で、その人の身のたけ(丈)と同じ長さに作られているのです。
また、現存する資料として、聖武天皇がご愛用されたという呉竹鞘の御杖刀が正倉院北倉に伝えられていますが、私の推定では天皇の御身の丈に作られているのではないかと思われます。今日の尺で五尺二寸三分(一・五八五メートル)あります。
中国の杖も木で身の丈と同じ長さに作られたということが、文字のうえから察せられます。
日本原始人もまた弓や杖を身長と同じに作っていたようです。
その結果、身長の度称がつえとなったのでしょう。しかし、日本ではこのつえに枝の字をあてています。この字はえだ(枝)です。記紀や祝詞の神祭りの条のなかによく出てくる、しもつえ(下枝)になにを、かみつえ(上枝)にないを捧げるという場合のえは枝のことです。
この意味からすると、えは木の枝のことで、これは木の幹から直接生えたものをさし、さらにそのえ(枝)から生えた細かい枝をだと呼んだようです。
えは枝の名称で、つえ(杖)は、始め人々が木の枝をとって使用したところから、この枝の文字をあてはめられたのでしょう。このことは、今日でもこうした土俗的な習慣が田舎などにのこっていることからもうなづけることです。
さて、ここで原始度称のつえ(都枝)を、一音語に分解してみます。つはまえに述べたようにつ(指)でえはえ(枝)です。つえは指で木のえ(枝)を握ってついて歩く用具をさすことばとなります。これが身長と同じ長さに作られて、度長の基準となったのが度称のつえ(都枝)なのです。
(同書四五~四七頁)
木の「え」(枝)を適当な長さにして手にもち「つ」(指)でしっかり握って突いて歩く道具にした、そこから「つ」+「え」で「つえ」と呼んだと望月は解釈する。そして、その杖の長さは使用する人の身長に合わせたのだという。そこから「つえ」が身長を意味して、これが身度尺のひとつとして長さの基準になったのだった。
望月の解釈はいちおう辻褄は合っているように思われるのだが、杖の長さを身長と同じとしたという根拠がいまひとつ説得に欠けるようにも思える。何も身長と同じにしなくても、立派な杖はできるからである。現代の老人たちが使っている杖に身長ほど長いものは見あたらない。修験山伏らが使う錫杖は相当に長いが、身長と同じにする決まりがあるのかどうか、寡聞にして知らない。
さて、ここでも「え」(枝)の原義が明快に説明されていれば、もう少しすっきりするのであろうが、その説明はない。「一音語意味表」では、「え」の原義を「上の方向へ」とし、二次的意味として「枝」と「栄える」を挙げているが、枝をなぜ「え」と呼んだのか、そこのところをもっと突っこんで知りたいものである。
ちなみに、日本身度尺にいう「つえ」の長さは「ひろ」と同じであると望月はいう。「つか」が「あた」の半分の長さだということはすでに述べたが、その「つか」ないし「ひろ」の長さは「あた」の十倍に当たると日本の古代人たちは「実験的に認識していました」とも、望月は付言する。
身度尺相互の関係も半分とか十倍とか、明確に捉えられていたのだ。これまた驚くべきことである。
◎「き」「きだ」(寸)……身度尺の長さとしては、はっきりしている。指一本の横幅の長さである。だが、望月の説明はここに用いられている「き」についても「だ」についても、隔靴掻痒の感が沸き起こってくるほどにもどかしい。あるいは的外れではないのかとも疑いたくなるのである。
き(寸)もまた、日本原始度称のひとつです。日本ではきまたはきだに寸の字を当て字していますが、漢土式の十寸爲尺という一尺の十分の一の一寸とは異なるものです。日本のきは一本の指巾の寸法です。指四本のならんだ長さがつか(握)ですが、つか(握)が四本の指に分割されている状態がきだです。
きだは馬の背丈をはかる尺度に使われています。馬の背丈をはかるには、た(足)の下から前肢の付け根の、肩上部の固い骨の上までをはかるのです。その場合曲尺の四尺を基礎として、その上何寸あるかをはかるのです。その場合何きあるというのですが、ひときといえば四尺と指一本、ときといえば四尺と指十本の背丈という表示法をとっています。ですから、ひときは実長約六分(十八ミリ)ぐらいです。以前、私などが幼少の頃、病気したとき医師からもらう水薬のびんに、一回に飲む分量の目盛りがしてあって、その一段一段をきだといっていました。このような習慣で、き・きだなどの古度があったことが理解されます。
きという一音語の発生源は、固いもので他のものに傷をつけるときに発する、きーという音のその音感をとらえたもので、引掻き傷の跡をきというようになったと思います。その結果、あまり固くない、例えば爪のようなもので土、土器に線条や文様を付けてもきといわれ、その形はきづといわれたのです。草木の木には年輪があります。木材をみても年輪が木目としてはっきり現われています。年輪や木目は、きの概念に一致するでしょう。きの概念は石や土や草にはすくなく、特に木に顕著であるところから、木の特徴としてとらえられ、き(木)という呼称がついたと考えられます。
きり(錐)という道具がありますが、このきり(錐)のりは尖った物たとえば針、銛、槍のようなものについています。きり(錐)は傷を付けるのに役立つもので、この名前がついたと考えられます。 (同書四七~四九頁)
以上が身度尺「き」および「きだ」に関する望月の説明のすべてである。「き」が傷を意味したであろうことは分かる。しからば、「だ」とは何を意味したのか、「きだ」とはどんな意味なのか、一音語ならではのユニークな解釈を期待しても、肩すかしを喰らうだけなのである。
だが、逆に考えれば、望月長與の炯眼をもってしても、「き」や「きだ」について明快な解釈を成し遂げられなかったということになる。それほどに「き」「きだ」は難解なのだと思えばよい。
つまりわれわれの挑戦を待っている謎だということである。そう考えれば、参考になりそうないくつかの使用例を望月が見つけてくれたことだけでも、感謝すべきであろう。
広辞苑では「きだ」に「段」の字を宛てて「わかち」「きれめ」「わかれめ」などの意味を挙げ、「八段(きだ)に斬りて」という用例を引いている。不確かな記憶であるが、何かの本で「きだきだに切る」という珍しい表現に出会ったことがあるような気がする。
広辞苑にはまた、魚の鰓を「きだ」と呼ぶとも紹介している。
いろんな例をとくと考え合わせてみると、「きだ」とはこれを構成する元の一音語それぞれの原義はさておき、「バラバラに別れた状態」を意味するのではなかろうか。「き」や「きだ」が指一本の幅の長さをいう身度尺だとすれば、それは指そのものとは関係なく、手を揃えて伏せたとき、四本の指が三つの間隙によってバラバラに別れている状を表わしたものではないか。魚の鰓を「きだ」と呼ぶのは、まさにこの「バラバラに別れた」という意味がぴったりではないか。
すると、「きり」(錐)のばあいの「き」は小さな傷ないしは穴を意味するのであろうが、「きだ」の場合には、「き」は線条によって縦長の細片に分割された状態を謂うのだと考えられる。
望月も「一音語意味表」の「き」の欄で、原義として「刻む」二次的意味として「木」「傷」「線」を挙げているが、その「線」という意味がここではもっとも当て嵌まる。
同じ表で「だ」は原義に「重なる」、二次的意味として「段」と説明されている。これは一音語「だ」の元の意味が「バラバラに分割されて並んでいる状態」と考えれば、「重なる」も「段」もひとつの概念に包摂されるのではないだろうか。
●思えば、脱線に次ぐ大脱線で、ただ最初はハンガリーのツラン問題に関するウェブサイトを紹介しようと思っただけなのだが、そこでシュメール語が重要な鍵であることを教えられたせいで、はるばるととんでもない地点まで飛んでしまったことである。羊頭狗肉を地で行ったようなもので、長々とお付き合いして読んで下さった読者には深くお詫びしたい。ただ、私としては、とんでもない大脱線のおかげで、望月長與という先達が提唱する日本語祖語としての一音語に出会って、興奮冷めやらぬ思いなのである。(おわり)★