
 |
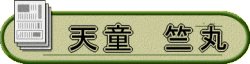
![]()
![]() 「宮原昭「その土地本来の森を」 1
「宮原昭「その土地本来の森を」 1
(世界戦略情報「みち」平成19年(2667)7月1日第253号)
●同志の林廣から「宮脇昭さんは凄いよ」と教えられたのは、もう随分と前のことであった。せっかく教えてもらったのだから名前を忘れてはいけないので急いでメモに書き、机の脇に貼っておいた。ところが、何日か経ってメモを見ると、さぁ誰だったか、何のためにメモにしたのか忘れている。
困ったことだと思いながら、仲間に聞いてみたが分からない。奇妙なことに肝心の林廣だけに聞かなかったのである。
その後しばらく経ってから、林さんがこれはと思う番組を録画して戴いたDVDが相当に溜まっていたので、今日こそはじっくり見てみようと、山の中から一つを取りだしたところ、何とそれが「植物生態学者宮脇昭」さんの活動を紹介したDVDだった。こうして私は宮脇昭さんと出会ったのである。
それは二〇〇五年六月と七月にかけてNHK教育テレビ「知るを楽しむ」という番組で、「この人この世界──日本一多くの木を植えた男」と題して放送された一回二五分、全八回の番組の録画を一枚のDVDに八回分まとめて編集したものだった。
それを一気に見て、心から感動した。宮脇さんが森や木について語っていることに、私は深い共感を感じた。
それで、林さんにお願いしてさらに何枚か余分に作ってもらって、御縁のある人に配って観てもらった。
さて、ぜひとも本欄でご紹介したいと思って探してみると、一枚も手許に残っていない。胡乱の限りだが、幸いにも先に観たとき簡単なメモを取っておいた。それを手がかりに、宮脇昭さんについて書く。
本稿を書く上で、ネットで収集した資料も含めて、もっとも参考になったのは、旭硝子財団が宮脇さんに平成一八年度「ブループラネット賞」を贈ったときの「受賞者記念講演」であった。特に断わらない限りは、引用は同財団のホームページの歴代受賞者欄二〇〇六年度に宮脇昭さんの名前と写真があり、その右側に公開されているその講演記録(http://www.af-info.or.jp/jpn/honor/pdf/2006lect-j.pdf)から引用して使わせていただいた。
●私は林廣に教えてもらうまで宮脇さんの名前を知らなかった。ところが、知らないのは私だけで、植物生態学者の宮脇昭の名前は世界的にも有名であるらしい。
日本ばかりでなく世界の各地で樹を植えること一五〇〇個所以上、宮脇昭さんの植樹指導によって世界中で植えられた木は三〇〇〇万本に上るという。「三〇〇〇万本の木を植えた男」とは宮脇昭さんのニックネームともなっているのだ。
そして、インターネット上のフリー百科事典『ウィキペディア』にも紹介記事が載っている。その記事によれば、次のように紹介されている。
宮脇昭(みやわきあきら、一九二八年[昭和三年]一月二九日~)は岡山県川上郡成羽町(現・高梁市成羽町)出身の生態学者。
広島文理科大学生物学科卒業。ドイツ国立植生図研究所で潜在自然植生理論を学び、横浜国立大学教授、国際生態学会会長などを経て、一九九三年より財団法人国際生態学センター研究所長。横浜国立大学名誉教授。
国内外で土地本来の木を中心に、多数の種類の種を混ぜて植樹する「混植・密植型植樹」を提唱し活動している。(一部表記を改めた)
この宮脇昭さんの植樹指導の根幹にあるのが、「その土地本来の森を」という信念である。それは一朝一夕に成った信念ではない。
宮脇さんは日本各地のどんなところにどんな植物が植わっているのか、すでに広島文理科大学(現広島大学)の三回生の頃から夜行列車で各地に足を運んでは調べていた。卒業論文にも「雑草生態学」をテーマにしたい、と指導教授に申し出たときに、その堀川芳雄教授から言われた言葉は今に忘れられないという。
「おお、雑草か。それは大事だぞ。理学と農学の接点で、あまり人がやっていないから面白い。ただ、宮脇、雑草生態学なんかやったら一生陽の目を見ないし、多分誰にも相手にされないよ。それでもお前が生涯かける気なら、是非やりたまえ」
言葉は突き放したようで厳しいが、雑草研究に賛成してくれたのは、この堀川芳雄教授たった一人だった。堀川教授自身、植物の分布を調べて日本中を歩き回っている現場主義の人だった。宮脇さんの申し出はいわば恩師の衣鉢を継ぎたいと言ったようなものだが、だからこそ、堀川教授はあえて厳しい戒めを語ったのであろう。
堀川芳雄教授を「生涯の恩師です」と番組で語る宮脇さんの目頭が心なしか潤んで見えたのは、私の気のせいであろうか。
宮脇昭さんが大学を卒業したのは、戦後間もない昭和二七年である。日本はいち早く戦災から復興する途を歩みはじめてはいたが、まだまだその痛手から癒えきっていない時代であった。そんな時代に「雑草生態学」(!)をやろうと目指したというのだ。
しかし、なぜよりにもよって雑草なのか。その動機を宮脇さんはこう語る。
私の実家が農家でしてね。私は幼いころから体が弱くて、三歳のときに脊椎カリエスを患ったり、腎臓に疾患があったりで寝込んでいることが多かった。それでよく自宅の二階の窓から、雑草取りをする家族の姿をボーッと眺めていたんですよ。そんなときには、いつも「農薬をかけずに雑草をうまくコントロールできたら、農家はどんなに楽になるだろう」と考えていました。自分が手伝えないことに対する負い目もあって、強く心に刻まれていたんですね。そうした思いが、雑草をテーマに選ばせたということです。
草取りの苦労を少しでもなくす方法を探すために、宮脇昭さんは岡山県に三つあった農林学校の内の一つである岡山県立新見農林学校に入学する。そこを卒業すると、東京高等農林学校(現在の東京農工大学)へ進学するが、終戦直後の食糧難の時代、食物もなく始終腹を空かせていたという。
小学校の教科書で見た黒い煙の立ち上がる都会に憧れて、飛行機の爆音が毎日聞こえるようなところに住みたいというのが、東京に遊学した偽らざる動機だったと、宮脇さんは正直に語っている。
卒業後に郷里に帰り母校の農林学校で一年間生物と英語の教師を務めた後、もう少し勉強したいと広島文理科大学へ入った。
日本中を駆けめぐって雑草を調べて回った日々のことを、宮脇さんはこう回想している。
雑草は生育が早い。したがって春、夏、秋、冬の各季節に調査する必要があります。一年に六〇日ずつ四回、計二四〇日、南は鹿児島から北は北海道の音威子府(おといねっぷ)まで、夜汽車に泊まりながら雑草群落の調査を続けました。音威子府は当時稲作の北限の地でした。
広島文理科大学を卒業すると、教授の推薦により東京大学大学院(小倉謙教授の形態学研究室)に入学、翌年には横浜国立大学の助手も務めながら、以後六年間をもっぱら雑草群落の研究に没頭する。
この間に「水分差による雑草の形態学的、生態学的相違」に関する論文をドイツ語で書いたものが、当時ドイツの国立植生図研究所の所長をしていたラインホルト・チュクセン(Reinhold Tuexen一八九九~一九八〇)の目に止まり、「雑草は人間生活と緑の自然との接点にあって極めて重要である。俺もやっているから、ぜひ来い」という手紙が舞いこんできた。
ぜひ来いと言われても、当時の宮脇さんの助手の月給九千円からすると、ドイツ往復の航空運賃四五万円という額は年収のおよそ四年分に相当する。とても実現する話ではなかった。
ところが、チュクセン教授の方が諦めなかった。ドイツ政府やフンボルト財団を動かして渡航の費用を出させ、宮脇さんをドイツに招くことに成功したのだ。こうして、チュクセン教授は宮脇さんにとってもう一人の「生涯の恩師」となった。
ところで、先に分子生物学者渡辺格さんのことを紹介したとき、ノーベル生理学・医学賞の授賞式で平家物語の冒頭にある「祇園精舎の鐘の声……」を英訳して出席者に配ったマックス・デルブリュックに触れたが、その援助と薫陶を受けて学者となったゴードン・ヒサシ・サトウ博士は、旭硝子財団が毎年贈る「ブループラネット賞」の一昨年の受賞者だった。昨年の受賞者に撰ばれたのが、宮脇昭さんなのだ。伯楽ともいうべきドイツ人学者の目に止まって大きな恩義を受け、大成して同じ賞に撰ばれている。奇しき因縁と言うほかない。
昭和三三年の九月末にドイツに渡った宮脇さんは、さっそく翌日から現地調査に駆り出された。今でこそ「現場、現場、現場」と口を酸っぱくして言う宮脇さんだが、当時は若気の至りからか考えが足りず、ラインホルト教授に厳しくたしなめられたと反省している。
小雨交じりの木枯らしが吹く厳しい条件の中、植物や土壌断面の野外調査ばかりの毎日に少し疑問を感じた私は、一ヶ月ほどたった頃、チュクセン教授に「もう少し科学的な研究をしたい」とおそるおそる申し出ました。チュクセン教授はゲルマンの最後の古武士のような厳しい人でした。青い目でじっと私を見て、「何が科学的か」と問うたのです。
「たとえばベルリン工科大学でこの教授の講義を聞きたい。ボン大学でこの本も読みたい」
と答えると、
「まだ君は人の話を聞いたり本を読んだりするのは早い。現場に出てみろ、三〇数億年の命の歴史と巨大な太陽のエネルギーのもとにドイツ政府が何百万マルク研究費をくれてもできない本物の命のドラマが展開している。それを自分の体を測定器にして、目で見、手で触れ、においをかぎ、舐めて触って調べろ」
と言って、私は徹底的に現場で植物を見る術を叩き込まれました。
人物が人物に逢うというのは、こういう瞬間のことを指して言うのかも知れない。それにしても、チュクセンの言葉は凄い。「三〇数億年の命の歴史と巨大な太陽のエネルギーのもとに……本物の命のドラマが展開している。それを自分の体を測定器にして、目で見、手で触れ、においをかぎ、舐めて触って調べろ」とは、唸らせる言葉ではないか。
そして、この徹底した現場主義の中で、チュクセン教授自身の提唱している「潜在自然植生」という考えを叩きこまれるのである。
雑草群落に関する最初の学位論文を発表したころ、チュクセン教授は、「雑草も大事だけれど、雑草は俺のひげと同じで取るから生える。大事なことは、その土地がどのような植生を支える能力をもっているかという潜在自然植生の概念である」と言って、一九五六年にチュクセン教授自身が発表した潜在自然植生、土地本来の素肌、素顔の緑について、現場で徹底的に教え込まれました。
ヨーロッパでも日本でも、ほとんどの緑はさまざまな人間活動の影響下に変えられ、土地本来の緑である本物の森はほとんど失われています。土地本来の潜在自然植生を判別するのは、まるで着物の上から体の中身を見るような感じで、なかなかわからない。はじめは忍術ではないかと思ったほどでした。
このチュクセンの「潜在自然植生」概念から「その土地本来の森を」という宮脇方式が出てくる。ドイツで夜半の夢うつつの意識の中に登場し、それに気づかせてくれたのは、郷里にある御崎神社の境内に聳え立つアカガシやウラジロガシの大木だった。
帰国が近づいたある日夜中に目が覚めて、ふと子どものときのお祭りが頭に浮かびました。私の郷里で一一月の初めに行なわれる御前(おんざき)神社のお祭りは、当時、草深い村の唯一の娯楽でした。夜の一二時から始まる備中神楽がはじけて朝の四時半頃狭い境内に出ると、明けかけた夜空に黒々と枝が伸びている。身震いするような感動で仰ぎ見たあの大木こそ、土地本来の潜在自然植生の主木ではないか、とひらめいたのです。
畏れというものを忘れた人間の傲慢に痛めつけられ怒っている日本の国土が宮脇昭の登場を待っていたと言っても過言ではあるまい。
●宮脇方式の「その土地本来の森」とは、杉や松など単一の木の群生を指すのではない。高い木も中ぐらいの木も低い木も混ざり、そして地面にはシダや雑草やコケが生えている森をいう。元々その土地に生えていた木こそが「本物の木」であるが、その背の高い「親分の木」だけでは本来の森は成り立たない。親分の木があって、その下に子分となる沢山の木があってはじめて、本来の森となる。
卑近な例で言えば、「駕篭に乗る人、担ぐ人、そのまた草鞋を作る人」という諺の意味するところと同じだろう。
だから、植樹する際にも、一種類の木だけを植えて事足れりとしてはいけない。その土地に本来あった色々な木を混ぜて植える、それが本来の森を甦らせる適切な方法なのだ。
こうした宮脇方式に対し、「本来の植生を重視するあまり、人間との関わりの中で成立し、独特の生態系を有する二次林の自然史的・文化的意義を不当に貶めるもの」だと批判する向きもあるようだが、もはやそんな悠長な批判を行なっている場合ではない。宮脇さんが日本全土を一〇メートル四方に区画して隈なく調べた結果、日本全体で本来の植生が残っているのはわずか〇・〇六%にすぎないところまで来ている。歴史に鑑みると、文明が滅びるのと森が滅びるのは軌を一にしている。支那も西洋も森を食い尽くし荒らし尽くす原理しかない。わが日本文明には、もともと森と共に生きるという考えがある。人類が種として滅びないためには日本の文明原理に拠るしかない。★