
 |
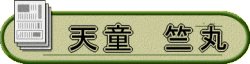
![]()
![]() キルギス人日本人同祖説 3
キルギス人日本人同祖説 3
(世界戦略情報「みち」平成20年(2668)3月1日第267号)
●かつて草原の道に往来した人たちの日本人に対する親愛の情は、初対面の大川記者にスイカを御馳走して日本人に会えたことを心底喜んだキルギスのおじさん一人に限られた感情ではない。すでに本誌では折にふれて、草原の道に往還した遊牧民族に由来するトルコやスオミの国フィンランド、さらにはハンガリーやウズベキスタンなどの国々の親日感情や言語・文化の余りの酷似に注目し、「ツラン文明圏」の壮大なる広がりを再確認してきた。
そこには、溢れるばかりの親愛の情を日本人に寄せる、心熱い人々が大勢いるのである。はるかな昔に草原地帯から東西に南に相別れた兄弟たちが永い別離の果てに相まみえたとき、互いに感じるのは、感涙に咽ぶほどの親愛の情と懐かしさではなかろうか。あの遙かなユーラシアの奥深い中央アジアの草原こそは、紛れもなくわが日本人のルーツの一つ、北方ルートの源郷に違いない。
私は大川佳弘記者の記事を読んで、あのキルギスのおじさんに航空運賃と滞在経費などの費用を贈り日本に招待したいと切に願ったものである。ただ一言、「よくぞ兄弟を忘れずにいてくれた。日本人に親切にしてくれた」とお礼を言いたいがためである。それは貧乏書生におよそ叶わぬ分に過ぎたる願いながら、もしも将来、可能ならば是非とも実現したい夢である。
●日本人に特別親愛の情を寄せてくれるのは、草原の道に縁ある民族ばかりではない。もう一つの日本人のルーツ、「黒潮の道」に沿う地域の人々もまた日本人の兄弟である。とくに台湾は、日本と切っても切れない関係にある。近・現代の政治的な歴史がどうであれ、あるいは現在の支那との「両岸関係」がどうあろうと、兄弟の絆、いや親子の絆というべき深い関係が昨日や今日の出来事で急に消えるものではない。台湾の人々が日本人に寄せてくれる格別の思いは、今更ここで云々するまでもない。黒潮の道の源郷であるインドネシアの人々も、タイやマレーシアの人々も本当は日本人に親愛と信頼の情を抱いている。
●それがなぜ、かくも日本人は嫌われ、人気がないのか。身をもってアジアの人々と付き合ったことのある日本人は知っているが、実はそれは現実のありさまではない。支那と韓国の徹底した反日教育と、それに率先迎合してきた共産党・社会党(現社民党)・日教組などの反日組織や朝日新聞・岩波書店などの反日メディアが垂れ流した虚像にすぎない。もういい加減に、虚説に振りまわされるのは、止めにしたいものである。
支那や韓国が反日教育を最重要視するのは、それぞれのお家の事情から、無理からぬ所ではある。中国共産党の統治の正当性は、「侵略国家日本から祖国を解放した」という神話を持ちだす以外、どこにも求めようがないからである。右顧左眄の事大主義に国家の延命を託してきた韓国が日本を嫌い、占領国米国に迎合するのも当然だろう。しかし、そうした政策もそろそろ賞味期限が切れている。反日だけに政権の正統性を求めるのは、どだい無理なのである。IMFによる金融搾取の軛の下では、韓国の反日も色褪せ、何の益も齎さない。韓国と日本もまた、古来培ってきた隣国としての特別の伝統的関係をしっかり踏まえ政策レベルでも親しい関係を築くべきである。目を深きに転じれば、そのような親しい関係が連綿として続いているではないか。
●他人事を論う前に、もっとも目を覚ますべきは、わが日本人自身である。寡頭勢力による世界戦略の詳細と機微を透徹し、しかしながらそれに与するのでも、振りまわされるのでもなく、神国たるべき日本の道義を内外に貫かなければならない。
神国に生まれた恩沢を噛みしめ喜ぶと雖も、それを外に向って夜郎自大に誇る尊大さは、厳に戒めるべきことである。神国の民はあくまでも謙虚に、慎ましくあらねばならない。
大東亜戦争は欧米列強によるアジア植民地化の戦争に終止符を打つための「アジア解放の戦争」であったことに紛れはないが、満洲国の経営や台湾・朝鮮の統治に当たった官僚・軍人・民間人の中に、傲岸に他の民族を侮蔑し、神国日本の道義をみずから踏みにじる輩がいたことも事実である。国家として奉じる大義が何であれ、傲岸不遜、とくに他民族に対する尊大は神国の末端を汚す行為であったと反省しなければならぬ。
本号の栗原稿「歴史の闇を禊祓う」の掉尾に説くように、しょせん「人は五十歩百歩」であり、神格に倣い学んで「競わず争わず常に自ら禊祓を怠らず励行しない限り」、神国の道義を貫くことはできない。
●鎖国による一国文明成熟への専心は、ある意味では日本的な慎ましさの戦略的表現だったとも言えよう。しかし、第一次のグローバリズムともいうべき世界植民地争奪戦に狂奔する欧米列強の横暴の前には、門戸を閉ざし続けることはできず、日本は開国を余儀なくされ、植民地化の危機にさらされた。亡国の危機を克服する方策として西欧文明に倣った「富国強兵」が国策とされたのは止むなしとしても、彼を高しとし我を低しと見て、西欧文物を摂り入れることを「文明開化」と称賛したのは、軽薄の極みであり根本的な誤りであった。
国を挙げてのこの文明的倒錯の危うさに気づき警鐘を鳴らした達識の要路者は稀で、西欧文明の陋劣を嘲笑したのはわずかに南洲西郷を数えるのみ。神国の風雅の高尚と卓越を信じた熊本敬神党や大国隆正ら「国学者」を抹殺する形で、わが国の近代化が推進されたからである。もっとも、この文明的倒錯こそが「近代化」の内実なのではあるが……。だが、この変則・跛行の歴史は、何としても正さなければならない。
●こうした文明的倒錯の一大潮流の中にあって、日本人一般の関心がもっぱら西欧へと向うのは自然の勢いだった。悲しいことに、わが近代において進歩とは、西欧の猿真似のことであった。科(とが)の学である科学の分野はもちろんのこと、人文学の分野においても、地理学・言語学・民俗学・文明学など世界認識の最終的大枠は英国東印度会社の世界戦略に従って用意された。司令塔が「王立~協会」である。その成果の最たるものが「文字」の出現をもって文明の始まりと見る倒錯的文明観であり、さらに害を為したのが自らの世界支配を正当化するため「アーリア人」「アーリア語」なる神話をデッチ上げたことだった。
それはインドに植民地教育官僚として赴任し赫々たる成果を挙げて貴族に列せられたトマス・マコーレー(一八〇〇~五九)がインドの人々の聖典であるヴェーダを歪曲するためにドイツ人ヴェーダ学者マックス・ミューラー(一八二三~一九〇〇)をロンドンに高給を以て招聘し、ミューラーがその期待にみごと応えて築き上げた学問的成果だった。
無念ながら、わが国の印度学仏教学も明治初年に洋行しロンドンに留学、他ならぬこのマックス・ミューラーに師事した南条文雄(一八七六年)と、高楠順次郎(一八九〇年)という二人の碩学によって基礎が築かれた。その学問を、かくいう私も大学で学んだ者であることを恥ずかしく思う。
しかも、この妄説は、印刷・鉄道・通信の手段を寡占的独占する世界権力によって意図的に世界中に流布され、蔓延していったのである。
●だから、文明とはギリシア・ローマに繋がるメソポタミヤ文明とエジプト文明、インダス文明の流れが主であり、黄河文明は植民地支配という黒い意図を隠すためのアリバイ証明的粉飾の用として祭り上げられているに過ぎない。世界の言語も、「アーリア語」が世界の支配的言語で、爾余の言語は「その他大勢」といった扱いなのである。
この滔々たる「学問潮流」に抗して、「ウラル・アルタイ語」という言語のグループが存在することを創唱したのは、フィンランドの学者たちだった。また、「アーリア民族」なる虚説に対抗し「ツラン民族」なる民族グループを提唱したのは、西欧列強による植民地争奪戦の餌食となり亡国の危機に瀕したトルコやハンガリーの愛国者たちだった。
わが国においても、英語がもっとも学ばれ、いまや小学校から教科に採り入れようなどという妄説も出るほどに至っているが、本来なら近しい関係にある蒙古語やエヴェンキ語を勉強しようなどと言うと、奇人変人と見なされるのがオチである。
こうした状況にあっては、世界日報の大川佳弘記者がキルギスについて「この旅に来るまで名前ぐらいしか知らなかった」としても、何の不思議もない。だが、キルギスの人は日本人という兄弟を忘れていなかったのだ。★