
 |
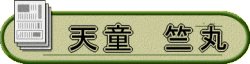
![]()
![]() 反支那地帯を行く ──西川一三の秘境西域潜行 5
反支那地帯を行く ──西川一三の秘境西域潜行 5
(世界戦略情報「みち」平成20年(2008)8月1日第277号)
●もし再び米国と戦うことになったら今度は絶対に負けない。勝つと見通しが立つまではジッと隠忍自重して牙を研く──そういう思いを新たにする時期が今年もやってきた。先の戦争に関する番組が特集される時期でもある。それにつけて、いつも思うのは、わが作戦指導がいかに将兵の命を軽んじたかということだ。そして、それにも拘わらず、わが将兵たちがいかに勇敢に戦ったかということだ。
将兵の命を軽んじる弊風は、敗戦に際して戦闘を停止し撤退せよとの命令を等閑にしたことにも、端的に表われている。西川一三も木村肥佐男も敵地および敵後背地に潜入した諜報工作員であったから、彼らに撤退命令が届かなかったのも無理はない。だが理解に苦しむのは、そもそも撤退命令を発しようという動きすらどこにもなかったことである。諜報工作員の命など使い捨てだったのか。ここにも将兵の命を余りにも軽視したわが軍の弊風を見るのである。
●祖国は敗れたとの風評に接しても、「日本が敗れるはずがない」という想いが打ち消した。西川一三が日本敗戦を否定しようのない現実として認めたのは、チベットからヒマラヤを越えてインド側の高原の町カーレンンボンで木村肥佐男に再会し数々のニュースを知らされたからである。カーレンボンはダージリンの東方にあるチベットインド間を結ぶ交易の要衝であった。木村は昭和二〇年の一〇月中旬にここに到着し、同地で「チベット新聞社」を経営するラダック出身チベット人のタルチン・バーブー氏に認められ同社の雑役として職を得ていたのだ。西川は木村の集めていた英語や支那語の新聞・雑誌によって「広島、長崎に投下された原爆、その原爆の威力、米軍の沖縄上陸、怨むべきソビエトの参戦、ミズリー号においての無条件降伏に至った祖国敗戦の実相を知った」のだった。カルカッタの町に出れば日本領事館もあるし、日本が本当はどうなっているのか判るだろうと、インド仏蹟巡礼に託けチベットを発った旅の途中だった。
●木村から祖国敗戦の確かな情報を見せられても、蒙古人ラマと偽って旅を続けている西川は連れの同僚蒙古ラマの手前もあり急に日本人にもどることができない。そのまま旅を続けるほかないのだった。そして、カルカッタに着いたとき、必死で日の丸の旗を探すのだが、どこにもない。それも道理、戦争の勃発と同時にカルカッタ駐在の日本領事館員や居留民一時抑留の後に強制退去させられていたのだ。それが分かったとき、西川はこうつぶやく。
これまで張りつめていた心は、まったく気抜けしてしまった。そして、自分に課せられていた責任から一応解放され自由の身になったような、ホッとした気分だった。一方今まで、喜びにつけ、悲しみにつけ、励ましてくれた国家が消えてしまったような、なんともいえない心細さを感ぜずにはいられなかった。
ああ、父母のもとを離れて父母の恩を知り、国を離れて国の恩を知る。それらがいかに自分にとって大きな心の灯であったかを、痛いほど身にしみて感じたのであった。
西川一三が偉いのは、祖国敗戦のショックと明日からどう生きるかの不安に苛まれながらも、とにかく生きるのだ、どうかして生きるのだ。明日から再出発だぞ!と心機一転、さらに潜行を続けようと決心した点である。(つづく)★