
 |
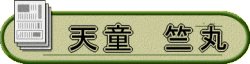
![]()
![]() 反支那地帯を行く ──西川一三の秘境西域潜行 6
反支那地帯を行く ──西川一三の秘境西域潜行 6
(世界戦略情報「みち」平成20年(2008)9月1日第278号)
●祖国が敗れたという意気阻喪させる確かな報に接しても、西川一三はなお敵後背地での潜行を止めようとはしなかった。とはいえ、敗戦のショックは西川を強かに打ちのめした。しばらくは為すこともなく、カーレンボンの町で乞食の群れに身を投じて地上生活を送ったのも、深い虚脱感の然らしむるところだったろう。
その絶望の底で一念発起して、こうなったら本物のラマ僧になってやろうと考えたところが西川の常人と異なる点である。それから、チベット三大寺の一つであるレポン寺に入門、内蒙古綏遠トムト旗出身の蒙古人ラマとして一万名近くのラマ僧の中で厳しい修行の日々を送ることになる。
『秘境西域八年の潜行』の中公文庫版第三巻の前半部分「チベット後編」は、実際にラマ教の修行に身をもって打ちこんだ体験から得られた貴重な記録である。そこには寺院の組織から経済、日常と特別の法会の様子、日々のラマ僧の生活の裏表までが注意深い観察眼によって活写されている。
●同じ蒙古人である慈愛深い俊才青年ラマ「イシ」を師匠としてレポン寺での修行生活は始まった。西川は「入蔵以来、半年間の放浪や乞食生活で、会話の方はどうにか不自由しなくなっていた」が、チベット文字についてはまったく無知だった。というのも、当時のチベットでは、日常生活にほとんど文字を必要としなかったからだ。
西川の蒙昧に驚き呆れた師匠だったが、「この有様では、……俺の弟子として、俺の顔がたたないから、せめて教典が読めるようになるまで俺が教えてやる」と言ってチベット語のイロハ(文字の発音と書き方)から教えてくれた。
イロハが終わると、今度は経典の丸暗記である。「シャブロー」という、礼賛の経典の四句をまず暗記することから始まった。「先生の名を辱めない弟子になろうとの意気に燃えている」西川にとっては、四句が八句になり、一二句になっても何ほどのこともない。ほどなく経典の紙(チベット語経典は木版刷の紙を綴じないで重ねたもの)を二枚、三枚と暗記するようになる。文字もイシ先生以上に上手に書けるようになる。すると、「先生は驚きかつ喜ばれ」るし、僧舎のラマ僧たちの間でも「凄い奴だ」と評判になる。
礼賛の経典が終わると、「般若心経やロルマー、モンラム等の経典を、またたくまに暗記した」と言うのだから、西川の真剣さが分かろうというもの。入門して二ヶ月も経つころには、数種の重要経典を暗記し、どんな経文でも一応読めるようになっていた。
●その年、昭和二一年の四月一五日にレポン寺に入山した西川は、一一月の新学期からは二年生に進級した。
その頃になると廟の法会の様子にはひと通りなれて、ラマとしての自信もつき、蒙古ラマからは信用されて、「日本人だ!」と疑われる心配も、まったくなくなった。ただチベット語の勉強という希望に燃え、ザンパー粥をすする貧乏生活ではあったが、生活は安定し、平和な日々が続いていた。(下巻、一九九~二〇〇頁)
そのまま修行を続けていれば、西川は蒙古人ラマとしてレポン寺の高僧に昇っていたかも知れない。だが、五年後には中共軍のラサ侵攻、さらにその八年後にはダライ・ラマもチベットを脱出、インドで亡命政府を樹立するという激動が待ち受けており、いずれにせよ西川の静かな修行生活は続かない運命にあった。しかし、実際に西川の静謐を破ったのは歴史の動乱ではなく、同志木村肥佐男からその年の大晦日に届けられた一通の手紙であった。
●「至急会いたい」という木村の手紙に何事ならんと心配しながら明けた元旦のその日に、西川は木村に会った。
木村はカーレンボンでの勤め先であるチベット新聞社の社長から「西康省のターチェンロー(打箭炉)とユシュ(玉樹)の、シナ側の状況を探索して来る」という仕事を依頼され引き受けた。だが、貰った前金の五〇〇ルピーの大半はとうに使い果たし、インド側には帰れないし、行くとしても西康は生きて帰れないかも知れない秘境地帯。いっそこのままドロンして内蒙に逃げて帰ろうか、と煩悶しての相談だった。
木村が危険な仕事を余りにも安易に引き受けたことに、西川は呆れる思いだったようだ。
しかし、行くもならず退くもならず苦悶するばかりの木村を前にしては、
「それなら俺も、君の仕事を手伝おう」と元気づけるほかはなかった。
異国の空の下で心の許すことのできる者は、ただのふたりきりの私達には、それが当然のことであった。この機会に日本人の、まして外国人も足跡未踏の西康省を踏破することは、いつかは国家のために役に立つかも知れぬ──という祖国愛と冒険心、否、死生など眼中にない、私の熱い血潮がたぎってもいたのである。(同二〇四頁)
●一方で西川は、木村がチベット新聞の社長タルチン・バーブー氏から依頼されたこの仕事の性格を冷静に見抜いていた。それは英国の情報機関が発注した仕事だったのだ。
第二次世界大戦はチベット高原で睨み合っていた英国と中国との眼を外に向けさせ、チベットには大戦中はまったく平和な風が吹いていたのであったが、終戦と共に再び両国の睨み合い、探り合いが始まったのである。英国としては自分自身でチベットに潜入できないため、常にチベット人を使って、シナのチベットへの前進基地ターチェンロー(打箭炉)と回教徒のチベットへの侵入基地ユシュ(玉樹)の敵情を探らせていたが、チベット人達は前金を貰うとドロンをきめ、いい情報は得られなかった。ところが、印蔵国境のカーレンボン一帯に網を張っていた英国の情報機関が獲物を捕えたのである。この網にかかったのが木村君で、それを知らせたのは、ほかならぬ、当時カーレンボンに住んでいたひとりの青海蒙古のラマであった。彼は英国情報機関の下で、ブータン、インド国境方面の情報収集に当たっていたが、終戦の年カーレンボンに出て来た木村君を日本人と見破り、通報した。狡猾な英国情報機関は、木村君が日本人であることを知っていて知らぬ顔をし、蒙古人木村として、目的地(打箭炉、玉樹)まで行って来たら、前金の外に五百ルピーを出すと相談を持ちかけたものである。こうして木村君のラサ出現となった。なお木村君を英国側に通報した青海蒙古人は、ブータンに潜入中、誰に殺られたのか、後頭部に一撃をくらってあえない最期を遂げたということである。(同二〇四~二〇五頁)
すなわち、青海省や西康省(現在は四川省に統合)も含む広義のチベットは、英国と支那が鎬を削る、諜報戦の最前線だったのである。そんな中で、前金たった五〇〇ルピーの端金を貰って敵地に出かけようと言うのだから、西川が木村に呆れるのも無理はない。
●何よりも西川を困らせたのは、慈愛溢れるイシ先生の信頼を裏切らざるをえなくなることであった。また、人々から信用されて落ち着いた環境の中で真剣に取り組んでいたチベット語や経典の学習がせっかく軌道に乗ってきたのを中途で諦めることだった。だが、それよりもっと苦しいのは、同じ目的を抱いて秘境に潜入した同志の木村を見捨ててしまうことだった、と西川は書いている。多くの困難を物ともせずに出かけた西康の旅は、西川自身が「生きていたということが不思議なくらいだった。潜行八年の間、これほど苦しい旅をしたことも初めてだった」と洩らすほどの苦難の連続であった。だが、その成果は充分にあった、と私は高く評価する。その一つは西康人(カンバー)の気質に直に接したことである。ラサ中心の中部チベット人から強盗だと西康人は嫌われていたが、それは産物に恵まれない自然の悪条件から来るので、付き合うと性格は竹を割ったようにあっさりしていて、確かに強盗もするが恵んでくれる慈悲心も持っている、と西川は証言する。同じチベット族ではあっても西康人と中部チベット人はまったく性格が異なるのだ。中共軍が大自然の要害を克服してラサに侵攻したのも、自国の中央政府や軍隊の悪政を恨み憎んでいた西康の一般民衆によって勝敗が決せられたからだ、とまで西川は解釈している。
●これから日本がアジアの盟主としての責任を全うしようとするなら、先人たちが生命をも顧みず万難を排して踏査探索した情報を徹底的に活用しなければならない。その意味で、西川一三の西域潜行から得られた情報は第一級の輝きを何時までも失わないだろう。いずれ支那は崩壊する。そのときには、モンゴルやウイグル、チベットなど、現在支那に囲い込まれ民族絶滅の危機に曝されている人々と日本は直に付き合うことになる。揺るぎない絆を結ぶことを、今からじっくりと、備え育んでおきたいものである。 (おわり)★