
 |
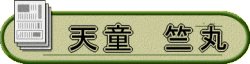
![]()
![]() ツランの足跡 ─ 大化改新から壬申の乱へ 4
ツランの足跡 ─ 大化改新から壬申の乱へ 4
(世界戦略情報「みち」平成22年(2670)11月15日第327号)
●渡辺豊和の『扶桑国王蘇我一族の真実』によれば、江上波夫による「騎馬民族渡来説」の最大の欠点は騎馬民族の渡来経路を「朝鮮半島を南下し九州に上陸し、それから次第に東征して、ついに大和・河内に入り大和朝廷を樹立したと考える」点にあると批判する。つまり、渡来説そのものは支持するが、侵入の経路が違う、と言うのである。満洲中部を故地とする扶余族が高句麗に追われて朝鮮半島を次第に南下し、半島南部に百済を建国した後、さらに扶余族の分流が海峡を渡って九州に上陸したと江上説は考えるが、江上説にまず異論を唱えたのが東北大学教授であった高橋富雄である。
●もし騎馬民族が九州に上陸し、中国地方を通って機内に入ってきたのであれば、西国一帯に馬飼育の痕跡が多数存在してよさそうなのに、それがない。馬を飼育したのは東北、特に北東北地方であり、良馬は東北の産と相場が決まっていた。騎馬民族は北東北に上陸し、そこから関東、中部地方を通って機内に入ったのではないかというのが高橋の考えである。
では、その勢力は何と呼ばれていたのか。高橋は「日高見(ひたかみ)」や「日本(ひのもと)」という東北地方全域を指す名称を挙げているだけで、そこの住民たる蝦夷と渡来勢力とがどういう関係にあったまでは述べていないが、その着想を具体的に深化させたのが渡辺豊和である。
●渡辺は言う。弥生時代から古墳時代の中期以降にかけて、日本には九州・出雲・畿内と三つの拮抗する政治勢力があったことがほぼ確実だが、古墳時代の後期ごろになると、もう一つ強力な勢力が存在していた気配がある。そうした気配を伝える証拠として渡辺が持ち出してくるのが支那南北朝時代の南朝の粱(五〇二~五五七)の歴史書『梁書』である。『梁書』に登場する当時の日本にあったとされる国名は、「倭国」「文身国」「大漢国」「扶桑国」の四つである。百済の漢城から新羅の慶州まで五千里とあるのを基準に渡辺が倭国(九州の阿蘇にあったと渡辺は考える)よりの距離から各国の位置を割り出すと、文身国は出雲、大漢国は河内、扶桑国は北海道の渡島半島近辺となるという。
●さらに『梁書』によれば、倭国が梁と通行していたのに対して、扶桑国は北朝の北魏と通行していて、その首都洛陽には「扶桑館」なるものが建造されていて、扶桑国は北魏から優遇を受けていたという。
ちなみに、『梁書』は通行していた倭についての記事よりも扶桑国関連の記事の分量がもっとも多いが、それは「南斉の永元元年(四九九)に扶桑国の僧慧深(えしん)が荊州に来て語った」からであるという。
この時代に扶桑国には僧侶がいたとは驚きであるが、南斉に先立つ南宋の大明二年(四五八)に罽賓(けいひん)国(ガンダーラもしくはカシミール)の僧五人が扶桑国に来て経典・仏像を伝え、仏教を広めて人々を出家させたことにより、やがてその風俗も変わったとも書かれているようだ。
●日本の古代史に「扶桑国」なるものはふつう登場しない。それは右に述べたような内容が荒唐無稽として歴史学者から無視されているからだと、渡辺は憤懣遣る方ない。支那の正史にあるものを妄りに無視してよいのかと言うのだが、その正史に荒唐無稽のことが多いのも事実である。だが、「扶桑国」についての記述は、簡単に斥けられない内容を含んでいると思われる。(つづく)★