
 |
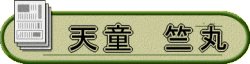
![]()
![]() 「神やぶれたまはず」
「神やぶれたまはず」
(世界戦略情報「みち」平成12年(2660)4月1日第93号)
●まだ肌寒い雨上がりの夕闇の中に、まがうことのない春の気配がひそんでいた。電車から降り、いつもの道を家路に向かうと、その途中に公園がある。公園に入って木々のない空間に出たとき、桜の木のつぼみの中で営々と用意されている花の意気込みや木々の樹液を流れる旺盛な精気があふれ出て、何もないその空間に横溢していた。
天まで突き抜けた空間の中心まで来たとき、急に歩けなくなってしまった。そこで立ち止まり、薄闇の空を振り仰いだ。かすかにほの赤く色づいた灰色の空から静かに闇が降りてきて、あたりは夕闇から夜の闇へと変わっていく。空を見上げながら、先ほどから抑えに抑えていた熱い波をもう解き放ってもよいという気がした。肺腑の底から次々に突き上げてくる波に身を任せると、全身に震えが来た。そして泣いた。涙が滂沱としてあふれ、天を仰いで慟哭した。そして「神やぶれたまはず」という思いが全身を浸していくのを感じていた。
●藤原源太郎が別れぎわに「ぜひ読め!」といって渡してくれた雑誌のある論文を電車の中で読み終わってから、ずーっと感極まった状態がつづいていて、人前で醜態をさらしてはならないと必至にこらえていた。それが、春の息吹を濃密に孕んだ公園の空間に来て、ついにあふれ出たのであった。
その論文とは『正論』四月号に載った長谷川三千子さんの「神やぶれたまはず」である。読み終わると、長谷川さんが立言してくれた「神やぶれたまはず」ということばが胸の中に叫喚し、次第に感動の渦が湧いてきたのである。
そして感動の大きなうねりにもまれながら、このことばに込められた長谷川さんのたおやかにして揺るぎない意志に気がついたのであった。
それは、後に続く者を信じて散華した英霊たちの遺志を継ぐという信念でもある。彼らが清明ともいえるような明るく決然とした態度をもって戦いに赴き若き命を捧げることができたのは、必ずや後に続く者がその死を踏み越えて社稷の守りを継いでくれるものと、絶対的に信じていたからである。
その信念を一言で言えば、「神洲不滅」であり、「神やぶれたまはず」であった。たとえその身が滅びても、神国たるわが日本は絶対に滅びないと信じていたのだ。
英霊に続くとはまず、「神やぶれたまはず」との信念を同じくすることにほかならない。
「そうだ! 神やぶれたまはず!」
私も全身全霊の共感をもって心中で叫んでいた。
●こういえば、「だって、日本は戦争に負けて無条件降伏したではないか。『神洲不滅』なんて、日本全体が異常心理に陥って、軍部の精神主義押しつけに易々と引っかかって信じこまされた結果じゃないか。事実は無謀な侵略戦争に駆り出されて、案の定アメリカにやられてしまったではないか。『神やぶれたまはず』だって! 日本が負けたんだから、日本の神々も負けたんだよ。いまさら何を血迷いごとを言う。事実誤認も甚だしい!」という識者の訳知り声が聞こえてきそうである。
ところがそうではないのだ。大東亜戦争の敗北、たしかにこれだけは残念ながら冷厳なる事実である。しかし、だからといって、日本の神々も敗れたのだと断定することは間違いなのだ。そしてこの一点こそ、社稷の根幹、日本民族の意志の根本にかかわる大きな問題なのである。
大東亜戦争の敗北、それはたしかに大きな衝撃であった。だから、大方の日本人は昭和天皇陛下の終戦の御詔勅を聞いたとき、文字通り「慟哭」とでもいうほかないような痛恨の激情に襲われたのであった。そこから自然に、「神洲不滅」の信念が忘れられ、無言のうちに「神もまたやぶれたまふ」と思ってしまったとしても、無理からぬことである。だが、やはりそれは違うのだ、と長谷川さんは言う。われわれには、「神やぶれたまはず」とする確かな根拠がすでに存在するのだと。
●長谷川三千子さんが「神やぶれたまはず」という貴重な一語を生むきっかけになったのは、折口信夫=釈超空が敗戦直後に詠んだ長歌「神やぶれたまふ」に対する「奇妙で複雑な感動」であった。
神こゝに 敗れたまひぬ──。
すさのをも おほくにぬしも
青垣の内(ウチ)つ御庭(ミニハ)の
宮出でゝ さすらひたまふ──。
くそ 嘔吐(タグリ) ゆまり流れて
蛆 蠅(ハヘ)の 集(タカ)り 群起(ムラダ)つ
直土(ヒタツチ)に──人は臥(コ)い臥(フ)し
青人草 すべて色なし──。
村も 野も 山も 一色(ヒトイロ)──
ひたすらに青みわたれど
たゞ虚し。青の一色
海 空もおなじ 青いろ──。
長谷川さんは上のように始まる折口の長歌に「絶望の極まつた末の美しさ、酸鼻のきはみのはてに現はれる森と静まりかへつた美しさといふものがある」と感じ、「昭和二十年八月十五日正午の、『あのシーンとした国民の心の一瞬』のかたちが、これらの詩句のうちにくつきりと灼きつけられてゐる」と評価する。詩歌に対しては、おそらくは絶賛ともいうべき最大級の評価である。
詩歌なれば、その美しい調べに感動すれば事足りる。しかし、詩人釈超空は単に詩人・歌詠みであったばかりでなく、國學院大學において「神道概論」を講じ、「神職講習会」で講演をし、「神社新報」に寄稿する折口信夫という神道学者でもあった。いわばわが国の信仰の在り方を指し示す責任を担っていた神学者だったのである。
その折口信夫が「神やぶれたまひぬ」と長歌に詠ったのみならず、神道学者としての活動においても、この断定を出発点として戦後の新しい神道を構想し、人にも語ったのである。先述の長歌は、長谷川さんのことばで言えば、「来たるべき新しい『神学』の到来を告げるべき序曲」として発表されたのであった。
となれば、折口信夫の「神敗れたまひぬ」という断定が正当なものであるかどうか、何よりも神道界でいち早く検討・検証が行なわれるべきであったのだ。だがそれは行なわれなかった。そして、折口信夫の予断に満ちた断定の誤りを指摘し、われわれの信仰のあるべき道筋を示し、ひいては揺らいだままに等閑にされてきたわが国の社稷の礎を据えなおしたのが、長谷川三千子さんの論文なのである。
●長谷川さんは折口信夫が「神敗れたまひぬ」と予断するに至った経緯を折口の心の内側にまで立ち入って丁寧に追うことによって、実に行き届いた理解を示している。その委細を辿ることは紙幅の関係からできないのが残念ではあるが、そこから導き出された結論は、折口の断定が誤りであることをはっきりと示している。
折口信夫の「神敗れたまひぬ」という断定は、能登一宮の気多神社の社家の出である愛弟子藤井春洋を硫黄島の激戦で失った悲嘆のあまりの深さゆえに、目が曇ってしまい、女々しい繰り言に終始してその悲嘆と屈折を突き抜けて真実に到達できなかったばかりか、その屈折を新しい神学へと持ちこもうとして生まれたものである。
●さらに重大なことには、折口信夫は自らの悲嘆にかまけるあまりに、「まさに新しい日本の神学の出発点とすべき地点を」見落としてしまったのである。それは何か? 長谷川さんは言う。
それは、この終戦の詔書、あるいは戦争終結の御聖断といふものが、天皇御自身の命を捨てる御覚悟に支へられたものであつた、といふことである。
さらに長谷川さんは、陛下の御決意の激しさ、堅さをもの語るものとして、終戦の御製といわれるお歌のうちの二首を引いている。
爆撃にたふれゆく民の上をおもひ いくさとめけり身はいかならむとも
身はいかになるともいくさとどめけり ただたふれゆく民をおもひて
そのうえで、長谷川さんは言う。
たしかに、古来、亀山上皇の元寇に際しての祈願にも見られるとほり、天皇や上皇がわが身をもつて国難を救はうと志すことは、日本の皇室伝統であつたと言つてよい。そのかぎりで、昭和天皇もまたその伝統に忠実であられたのだと言へる。けれども、いかにそれが古来の伝統であろうとも、それを今わが身に引受けて、自らの命を現実に投げ出す覚悟を決めるときには、或る種『精神の武者ぶるひ』といつたものがともなふに相違ない。これらの御製にあらはれてゐるのは、まさにそうした生身の御覚悟のさまである。そして、これはまた、『桜花』や『回天』に搭乗して突つ込んでいつた若者たちの精神、あるいは、玉砕を期して硫黄島の地下坑道にこもつた守備隊の将兵たちの精神とも、ぴたりと形を同じくするものである。
●長谷川さんが言うように、まさにここにこそ、われわれの出発点がある。「深い覚悟をもつて自らの命を絶望的な戦ひのうちに捧げた」若者たちの信にみごとに応えて、天皇陛下御自らが自らの命を投げ出されたのである。神話や伝説ならいざしらず、このようなことが、どこの世界にありえよう。日本で現実にそれが起こった。奇跡はすでに起こっていたのである。戦争に敗れたとはいえ、社稷再建の礎は陛下がすでに据えてくださっていた。ただわれわれがその意味に気付かなかっただけだ。
長谷川さんはこう結んでいる。
われわれは、信うすくして奇跡を呼びえなかつたのでもなければ、敗戦によつて神を失つたのでもない。われわれは、まさに敗戦の瞬間に奇跡を得、神を得たのである。そこから出発する以外に、われわれの出発点といふものはない。……いま私が感謝をこめて折口氏に送り届けたい言葉は、ひとこと「神やぶれたまはず」である。
★