
 |
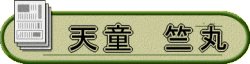
![]()
![]() ツラン魂は健在なり 7
ツラン魂は健在なり 7
(世界戦略情報「みち」平成18年(2666)7月1日第231号)
●日本語で体の各部を呼ぶのに一音語が多く使われていて、しかもこの名称がおそらく発生以来ほとんど変化していないことに着目した望月長與の発見は、日本語がどのようにして生まれたのか、その起源の謎に迫る多くの卓見に満ちている。引きつづき望月長與が解く身体名称の一音語の意味に耳を傾けつつ、日本語の起源について考えてみよう。
鼻は、な(穴)が二つ[は──天童]並んでいるのではなと呼ばれたのです[は(二つの)+な(穴)]。この二つがもっと離れた位置にあったなら、みみ(耳)やちち(乳)やもも、ほほなどのように、ななと呼ばれたかもしれません。(『一音語のなぞ』三二頁)
鼻が「なな」と呼ばれたかも知れないという指摘は面白い。体の左右対称に二つある器官、みみ(耳)ちち(乳)もも(腿)ほほ(頬)などの名称は、確かに一音語を二つ重ねてある。この造語原理からすれば、左右対称に二つのな(穴)が並んでいるのであるから、「なな」と呼んでも良かりそうなものである。しかし、実際には鼻は「なな」と呼ばれることはなかった。
なぜか? そこには日本語の造語における精妙かつ絶妙の識別感覚が働いていたようなのである。
望月自身「この二つがもっと離れた位置にあったなら」と言っているが、一音語の重複によってある器官が名づけられるには、左右対称に二つある状態ではあるが、それぞれがある程度の距離を隔てて位置していることが条件らしい。
鼻の穴のように、あまりに近接していて、ほとんど一体と見える場合には、一音語重複の造語原理は適用されないのである。
いま仮に一音語の重複によって命名する造語の原理を「双称法」(これは望月の用語ではない──念のため)と呼ぶとすれば、「双称法」が適用されるのは、「ある距離をもって左右対称に離れて位置する二つの器官」に対してだけ、ということになる。
明らかに鼻に対しては、これとは別の造語の原理が適用されたのである。鼻には二つの穴が接近して存在するが、鼻とは単にそれだけではない。鼻の形状を仔細に観察すれば、この二つの穴を仕切っている鼻橋、周囲を取り巻く尾翼、眉間まで鼻孔を覆っている鼻梁など多くの部分から成っている。その中で、日本語の祖型を作ったわが祖先たちが着目したのは、顔の真ん中に空いた「二つの穴」というもっとも顕著な特徴だった。
そこで、人間が生存する上で不可欠の息が出たり入ったりするこの器官を「は」(二つの)+「な」(穴)と命名したのである。
ここで用いられている造語の原理は「双称法」ではない。顔の真ん中に空いた気息の出入りする穴という事実を、より詳しく規定する、ないし説明する音を頭に冠して、穴は穴でも特殊な穴であることを識別したのである。すなわち、一音から成るある言葉に別の一音語を冠することによって特殊な状態にある事物を命名するという造語原理である。
この造語原理は、ある距離をもって並んでいる同じものを、一音語を重ねることによって命名する「双称法」に比べれば、はるかに複雑で進んだ造語原理と言わなければならない。
既存の一音語を二つくっつけることによって新しい言葉を創造するというこの造語原理を、仮に「合成法」と名づけることができる。「は+な」(鼻)の場合は、先に立つ一音語の「は」が後ろの一音語「な」を形容・修飾する関係にあることから、「合成法」造語原理の中でも特に「形容合成法」と呼んでもよいかもしれない。
日本語の祖型が造語原理としてこの「合成法」を手にしたことは、実は言葉として途方もない一大飛躍を遂げるきっかけともなる大事件だったと想像される。
われわれ人間の体の器官や身の回りの自然の事物を呼ぶのに一音語で命名するには、その事物のもっとも顕著な特徴や形状を的確に観察して、誰もがああ成程と共感をもって呼べるような命名でなければならない。
言葉の発展過程からすれば、それは言葉のもっとも原初的な誕生そのものであるといってよい。日本語の基本的な語彙の中に、そうした一音語がいまだに残っていることは、驚くべきことである。
人間が成長する過程に擬えていうと、一音語が誕生する状態とは、嬰児が誕生してやっと這い這いできるようになる段階に相当するかも知れない。這い這いに過ぎないとはいえ、放っておけば嬰児は相当広い範囲をどこへでも行く。危険なところもお構いなしである。這い這いする途中で出会う事物に対して、嬰児はジッと見つめたり、触ったり掴んだり、口に持っていって舐めてみたりする。それは拙いけれど、嬰児なりに世界を触知する方法なのである。だが、そこには紛れもなく次第に一つの世界が形成される、と言ってよい。
それと同じように、一音語の世界も、人間が身の回りの自然や人間の事物との新鮮な出会いから創造した、一箇の確たる世界であった。
そこから出発して、「双称法」という造語原理を入手する段階は、同じく人間の成長に擬えれば、よちよち歩きの段階といえようか。嬰児が立って歩くようになると一挙に世界が拡がるのと同様に、同音重複とはいえ二音語をもつに至って、日本語は一挙に豊かになり、次なる発展への端緒に立つことになったのである。
そして、日本語が造語原理として、「合成法」手に入れた段階は、嬰児が物に掴まって伝い歩きするのでなく、自分の二つの脚でしっかりと立って歩くさまに似ていよう。もはやそれは、嬰児と呼ぶ段階を過ぎて、幼児と呼ばなければならない発達であろう。
日本語が造語原理として「合成法」に気づいたことは、それほど画期的なことだったのだろうと推測されるのである。
さて、「双称法」だの「合成法」だのと、勝手な造語を捏ねくりまわしたりすれば、当たり前の決まり切った日本語の常識に対し御大層に言い立てるものよ、と顰蹙を招くかも知れない。だが、ここで私が「仮に」と断わりながらもあえて耳慣れない言葉をデッチあげて日本語祖語の造語原理なるものに拘泥しているのは、もともと一音語たる日本語が二音語や三音語へと語彙を拡げるときに、必ずや一定の造語原理が働いていたに違いないと予感するからである。
そうした造語原理が積み重なって、最終的には纏まりのある一つの体系を為したはずだと思うのである。それはいまだはっきりとは見えてこないが、漢字の造成について支那後漢代の文字学者許慎が『説文解字』で明らかにした「六書」(指示・象形・形声・会意・転注・仮借という六つの造字原理)のような(ただし日本語祖語の場合は一音語の組合せ原理となる)造語原理の体系が予感されるのである。
取りあえずここで泥縄式に作った「双称法」「合成法」「形容合成法」などという試みも、日本語祖語の一音語が二音語、三音語へと展開する独特の造語原理を予感し、それを解明したいからに外ならない。
だがその前に、一音語自体の意味をそれぞれしっかりと把握しておく必要があることは言うまでもない。
●望月長與は「は」(二つの)「な」(穴)という一音語が組み合わさって「はな」(鼻)という言葉ができたのだと説くのであるが、そもそもなにゆえ「な」が穴を意味するようになったのであろうか。
望月は自ら纏めた「一音語意味表」(『一音語のなぞ』一八~二五頁)の中の「な」の説明には、
上顎に舌をつけて、鼻の穴を抜けるようにあ音を出すとな音が出る。ここからの発想。(二二頁)
と簡単に説明しているだけで、たったこれだけでは釈然としない。しかし、この短い説明の中に卓抜な創見が隠されているのだ。すぐ後に詳しい解説を引用するが、それを斟酌してみると、望月自身ははっきりとは書いていないが、「な」とは、もともと「鼻の穴」を意味したと思われる。
一音語の本来の原義を知るためには、却って「な」音をもつ二音語や三音語などの合成語を検証してみるのが早道である。望月もしばしばこの方法を用いる。「な」の解説もそうである。
なは第一義的には穴のことです。その穴が自然界でもっとも多く見られるものをさがしてみますと、人体の毛穴なども多い方でしょうが、ほんとの穴というのに適切なものは草葉などの穴、とくに野菜につく穴なのです。その穴は蝶の幼虫である虫に食べられた跡で、今日でもキャベツ畑などでよく見られます。あの若葉のおびただしい穴、穴、穴です。原始の時代でも、野菜類とされた軟らかい草葉は、昆虫の幼虫が発生する時期には食べられて穴があいていたでしょう。この軟らかい菜類はおおむね人間のよい食料となりますが、こういう植物を採集する場合、ほかの葉と区別するためにな(菜)と命名するようになったのです。
なは本来穴なのですが、な(菜)を名づけられてからは軟らかいという意味にも転用されるようになりました。縄をなふということばのなふは、皮をなめすなどと同じで、縄をつくるのに藁を適度な軟らかさにして縄を作る動作のことです。
なめすは皮などを力を入れて軟らかくする動作で、なむすがほんとうです。
われわれが口でなという音を出すときは舌を上顎に軟らかくあてて発音します。この動作は舌で物をなめるという言語の発生をうながします。紙に舌先をあててつば濡らし、穴をあけることが、なめるということばの根本で、これに類似な行為、たとえば茶碗をなめる、はしをなめる、指をなめるなどになめるを使っているのは、すでにこのことばの根本から、類似行動の呼称へと発展したことをあらわしています。
なの発音をよく観察しましょう。この音を出すときは鼻にかかりますので、なが鼻の穴に結びつけられたのだと思われます。
なる(鳴る)ということばもはじめは、板の抜け節の穴などを強い風が抜けるときひゅうひゅうとなるのを、体験からとらえたもので、竹などで笛をつくって吹くと、やはりその穴をとおして空気がとおるときに音を発することによって、いっそう人為的に確認されたのです。な(穴)を空気が振動させるからなる(鳴る)のです。(『一音語のなぞ』六六~六七頁)
「な」の場合も「はじめに音ありき」なのであった。「な」という音を発するときには、仔細に観察すれば、その発語の瞬間に「んな」と聞こえるように息が必ず鼻にかかる。つまり、人間が声に出す「な」の音は常に鼻に関係しているのだ。
日本語祖語をつくったわが祖先たちはよく観察してこの事実に気づいた。望月が右の傍線部分で言うように、「な」を「鼻の穴に結びつけ」たのである。
つまり、「な」とは、まず鼻を指す言葉だったと考えられる。鼻の最大の特徴は、穴である。そこから、「な」が鼻以外でも、中が空洞になっている丸い形状のもの、すなわち、穴一般を意味するようになったと考えられる。
もともとは鼻だけを指す言葉だった「な」が穴一般を指すようになると、本来の「な」であった鼻を明確に意味するためには、穴は穴でも「二つ並んである穴」と限定的に表示する必要が起こり、「な」音の前に「は」(二つの)を冠して「はな」と呼ぶようになったのであろう。
「な」という一音語のこうした意味の発展は、一音語の意味の展開が具体的な事物(鼻)から一般的な特徴・形状(穴)を指すようになる経緯を教えているように思われる。
それには、前提として、事物の観察と命名に関わる祖先たちの思考の高度な成熟がなければならなかった。すでにそれは、抽象の域に達した思考だと言ってよいだろう。
この穴とあの穴とは、大きさも丸みも空洞の深さも全然違うはずである。そこから、「中が空洞である」という特徴と「周りが丸い」という特徴とを見分けて、いずれも「穴」だと判断・命名するには、個々の事物のさまざまな特徴の中から、共通する特徴を見つけ出すという抽象の思考が行なわれているのである。
●具体的な事物から一般的な特徴・形状を指すようになるという一音語の意味の発展は「拡充」と呼んでよいように思われる。一音語の適用範囲がどんどん拡()がると同時に、意味する内容もより明瞭に意識されて充()実してくるからである。
それとは別に、望月は先の引用で、一音語の展開におけるもう一つの重要な事実を指摘している。すなわちある一音語がもともとの語義とはまったく異なる意味をもつにいたる「転用」についてである。
つまり、「な」という一音語が「穴」という本来の意味から転じ、なにゆえ「軟らかい」というまったく異なる意味をもつことができるのか、その意味が「転用」される経緯について、望月は独創的な見解を披露している。
望月の説明によれば、一音語の意味の劇的な「転用」を媒介してまったく異なる意味を発生させるのは、ここでもやはり自然の具体物であるという。
「な」の場合には、もともとは「鼻」ないしは「鼻の穴」を意味したものが、「穴」一般を意味するように「拡充」する一方で、昆虫の幼虫である虫が食べて「穴」が空いた草葉をも「な」(菜)と呼ぶようになる。
当初は「穴」のある草葉だから「な」(菜)と呼んだのであって、原義「穴」から決して大きく逸脱するような意味内容ではなかった。
ただし、菜の場合には、穴そのものを意味するのではなく、虫に食べられたたくさんの穴をもつ草葉を意味するのである。ここには、具体物から抽象的な特徴へ、そしてまた具体物へという、意味が指示する対象の「揺らぎ」がある。その意味の「揺らぎ」はまた意味の「往還」とも言い換えることができる。具体と抽象との間を往ったり還ったりするからである。
なぜ菜は虫に食べられ穴がたくさん空いてしまうのか。そのわけは、菜が虫の好んで食べたくなるほど軟らかいからである。虫が食べ穴が空いている軟らかい草葉は、人間にとっても食べやすく美味しいものだった。そこから、「な」(菜)が食材の草葉を意味するようになる。
ひとたび「な」が食材の草葉である菜を意味するようになると、穴が空いていようと空いていまいと、変わらず菜は「な」と呼ばれつづける。虫食いの穴が空いていない方が、むしろ望ましいとさえ思われるようになったのかも知れない。
事ここにいたって、菜と穴とは本来の結びつきを忘れられて、菜がもっているもう一つの特徴の「軟らかい」と「な」が結びつく。
つまり一音語「な」が原義「穴」を意味することを止め、その代わりに、「軟らかい」を意味するように「転用」されたわけである。
一音語からなる言語は、もともと音の数が限られているため、一音が多くの意味をもつこと、すなわち多義が普通である。同じ音でありながら、なぜまったく異なる意味をもつようなことが可能なのか。望月の説明は一音語における同音異義の発生つまり「転用」の仕組みを分かりやすく例証するものである。
一音語「な」は「穴」と「軟らかい」という相異なる二つの意味を併せもっているが、この二つの意味は菜という自然の具体物の二つの特徴だったのである。
つまり、一音語を駆使したわが祖先たちが、一つの一音語をまったく相異なる別の意味に使う場合には、二つの意味を媒介する自然物がある、ということになる。二つの意味はある自然物が兼ね備える別々の特徴なのであって、何でもかでもむやみやたらに同じ音で呼んだわけではないのだ。
●ここにいたって、先に本稿「ツラン魂は健在なり4」(五月十五日号)で引用したシュメール学泰斗クレイマーの指摘した「初期のシュメール人書記が洞察するに至った名案」なるものをもう一度改めて思い起こしていただきたい。
ある特定の言葉に使われている文字を、まったく意味の異なる他の言葉にも、もし二つの言葉の発音が同一であるなら、使うことができる、ということだ。
クレイマーはここでシュメール文字について語っていて、ある一つの文字は「もし二つの言葉の発音が同一であるなら」「まったく意味の異なる他の言葉にも」「使うことができる」と言うのだが、最初に私はこのクレイマーの説明に曰く言いがたい違和感を感じたのであった。事はそれほど簡単ではない、と。
そもそも本稿が「ツラン魂」の範囲を大きく逸脱して日本語祖語としての一音語へと急旋回してしまったのは、このクレイマーに対する違和感を吐露したいがために外ならなかった。
クレイマーがここでさらりと書いている「二つの言葉の発音が同一」であることには、如上に述べ来たったような、一音語の展開における深い意味があるのだと言いたかったのである。
望月長與の説明を借りながら「な」のもつ二つの相異なる意味について考えてきたのだが、この例に鑑みれば、一音語が多くの意味をもつとき、そこには必ずや「転用」という事態があるということができる。
一音語もまた、もともとはある一つの意味から発生した。そしてその意味をもちながら同時に他の特徴をも兼ね備えもつ特定の事物において、本来の意味を離れて他の特徴を意味するようになる。これが望月のいう「転用」である。
一音語「な」が「転用」されて、本来の「穴」という意味のほかに「軟らかい」という別の意味をひとたび獲得すると、今度はこの「軟らかい」という意味の系列の言葉がどんどん成立するようになる。それが「なふ」「なめす」「なむす」などの言葉である。
これらの言葉の系列では、「な」がもっていた本来の原義である穴の意味はとうに失われていて、「軟らかい」という意味が共通しているわけである。
このあたりまで来ると、われわれが日ごろ何気なく使っている普通の言葉の、その一音一音に意味があるということが、そろそろ納得されるのではないだろうか。
ところで、望月長與が「なめる」について、「穴」という意味の系列だと説明しているのは、容易には賛成しがたい。
「紙に舌先をあててつばで濡らし、穴をあけることが、なめるということばの根本」であると望月は言うのだが、そもそも「なめる」という行為よりも先に、紙が存在したかどうか、疑問である。それよりも、舌のぐにゃりとした軟らかい感触がもっと語感に活かされているように感じるのだが……。
望月も「なめる」は「ことばの根本から、類似行動の呼称へと発展した」と実感しているように、「穴」という原義より「軟らかい」という意味に「転用された」段階が「な・め・る」なのではないだろうか。(つづく)★